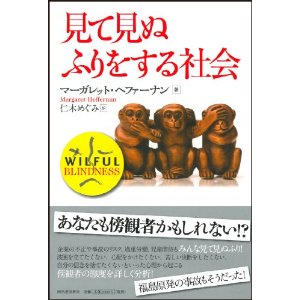Books-Sociology: 2012年1月アーカイブ
「限界集落」とは65歳以上の高齢者が人口の半数を超え、独居老人世帯が増加し、社会的共同生活が困難な集落を指す。限界を超えると人口、戸数がゼロになり「消滅集落」となる。過疎化現象の末路として80年代に問題提起され、その後2007年の参議院選挙で地域間格差の問題に絡んで再びクローズアップされた。そして国は過去7年間で191の集落が消えたと発表した。
高齢化→集落の限界→消滅。遂に過疎化も行きつくところまでいったかと、私もそう受け止めていた。ところが地域社会学者の著者は「消滅しそうな集落など、いったいどこにあるのか?」と意外な問題提起をしている。
著者は長い間常識ととらえられてきた「限界集落」というモデル自体に疑問を呈する。そして自らフィールド調査を行って、高齢化で共同生活に支障をきたして消滅に至った集落は実際には1件もないという調査結果を発表する。確かに1960~70年代には急激な人口減少と挙家離村により集落の消滅があったが、その後はダム建設とか廃鉱による廃村はあっても、自然消滅というケースは一件もみつからない。国の発表の191の村が消滅したという数字は、中身をよく調べるべきだったのだ。
生きた集落というのはしぶといらしい。高齢化が進んで戸数が減った集落でも、案外に老人たちは元気にやっている。子供世代も盆暮れ正月には帰ってくる。近くの街に住んでいる息子らが農業を手伝うためちょくちょく帰ってくる家もある。アンケートでは将来的には田舎に戻りたいという声も多いという。だから現実には、今住んでいるおじいちゃん、おばあちゃんが亡くなったからといって、ムラが消えるということにはならないのだ。
農地や山林などの家産、そして親の扶養責任、郷土意識などの責務や価値が、いったんは出て行った人々をムラにつなぎとめているという。だから少なくとも過去20年では限界集落という問題はなかったと著者は結論している。高齢化よりも、少子化によって次の世代が生まれなくなるこれからの方が危険なのだ。
限界集落の誤解はメディアのせいでもあると著者は指摘している。「限界集落はもう駄目だ」と言うイメージであおると地域もネガティブに考え始めてしまう。「かわいそうな」集落と、下りてくる国の救済的な過疎対策という図式がつくられていく。本当は、過疎地の集落の内側だけでなく、親子孫の3世代の生き方、都会と田舎の人口の還流といった全体でみなければ、本当の問題がみえてこない。
「過疎地の現場では、取材に来た記者に「大変でしょう?」と聞かれて、ついうっかり「ええ、大変です」と答えてしまっていることが多いようだ。それどころか、「問題はないか?」としつこく問う記者に、根負けしている様子さえうかがえる。場合によっては、遠いところまで来て気の毒だと、現場の方であわせてあげていることもありそうだ。実際、それに似たようなことを筆者は何度も目撃してきた。そんな取材でつくり上げられていく限界集落のイメージが、あたかも現実であるかのように一人歩きしていることに、多くの人々が困惑しているのが実情なのである。」
周辺から中心はよく見えているが、中心から周辺を見るのはきわめて難しいということが、本書の問題意識の根幹にある。
見て見ぬふりが破滅を引き起こす。エンロンの経営破綻、イラクのアブグレイブ刑務所の捕虜虐待、スペースシャトルチャレンジャーの打ち上げ失敗、BP社の製油所爆発事故など、大事故、大事件の関係者は危険を知っていたが、みな見て見ぬふりをしているうちに破綻に至っている。こうしたことは最近の日本にも多い。福島原発の危険性も、オリンパスや大王製紙の不正も、当事者は見て見ぬふりをしていた。この本は、大企業の役員会や、専門家の頭脳集団が、なぜそんな状態に陥ってしまうのかの研究だ。
世界で起きた大事故、大事件の背景に見て見ぬふりがあり、その原因として権威への服従、周囲への同化、傍観者効果、遠い距離、分業、極度の疲労、頑固な信念、倫理観の崩壊などがあるとし、それぞれ典型ケースを使って説明されている。組織文化や個の資質もあるが、私たちの脳にもひとつの原因があるらしい。
脳には愛によって活性化する領域があると同時に愛によって活性が止まる領域があることがfMRIの検査でわかっているそうだ。たとえば子供や配偶者のことを考えている間は、脳の否定的な感情や社会的判断を司る領域が不活性になる。そして我々はしばしば知ることができて、知るべきである情報があるのに、知らずにいる方が心地いいから知ろうとしない。認知不協和。こうした現象の中には神経科学で検証されているものもある。
権威への服従も見て見ぬふりの大きな原因だ。ヒエラルキーと服従は自らの生命の危険が及ぶような場面でさえ見て見ぬふりを引き起こす。飛行機の墜落事故のうちの4分の1がコックピット内の「破滅的な服従」で引き起こされている。商業路線の機長があまりに高い権威を持っているために、副操縦士や乗務員が機長の判断に異を唱えることができなかったことが事故につながっていたのだ。
悪いのは裸の王様のトップだけでもない。大きな組織の中では誤りを発見しても、構成員はトラブルメーカーだと思われたくない、どうせ何を言っても変わらないと思って黙ってしまう。傍観者だらけの組織がトップの暴走を許し、そして組織の各所が互いの欠点や悪い所を同化させていく。
「人は同じような考えの者同士で固まっていたいという本能があるせいで、違う種類の人々や価値観や経験に触れることが少なくなる。ゆっくりと、しかし確実に、自分の知っていることだけに集中し、他のすべてが見えなくなっていく。現代は以前より選択肢自体は増えたのに、狭い好みを守るようになった。」
多様性、透明性のインターネット空間だって同じだ。結局のところ人間の習性で情報交換のコミュニティには似た者同士が集まる。異なる価値観で異議を唱えるのは勇気がいるし、下手をすると排斥されてしまう。検索で異論を発見できる、容易にエビデンスをリンクで示せる、というところは希望かもしれないが。
見て見ぬふりを生みだす私たち自身の脳や集団の持つ性質を深く理解することが、見て見ぬふりを防ぐのに大切なのだと本書は教えている。