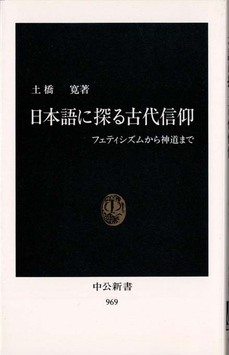Books-Religion: 2009年3月アーカイブ
「日本の古代信仰のもっとも中心的な課題は、霊魂の観念であり、それも遊離魂よりはむしろ霊力、呪力の観念であるが、日本の学界ではこの種の霊魂観念に関する問題意識が乏しく、そのために呪術・宗教のもっとも基本的な概念である「神聖」ということも、清浄なことと解して疑うことなく、賀茂祭のミアレ木や阿礼幡など、各種の儀礼に用いられる呪物も、神の依代だとする誤解が常識化している」
著者は古代の儀礼、神話、歌を資料として、霊魂と呪物・呪術に用いられた言葉を分析し、古代人の宗教意識を解明していく。最初に取り上げられているのは霊魂(タマ)の観念の分別である。古代語には呪力霊力(マナ)を表すタマと、遊離霊としてのタマがあるという話。
魂という言葉はタマシヒ(タマ=霊魂、シ=の、ヒ=霊力)からきている。平安の頃の用法ではタマシヒは霊力であり霊威であり、生まれつきの天分や才能を意味した。人魂になって飛ぶような遊離魂の意味ではなかったという。古い和歌にその使い分けがはっきりと見られることが示される。
タマやヒと並んで、神聖を表すのが「イ」「ユ」であった。それは生命力の強い自然物の接頭語として、また霊力を与える動きを意味する動詞にも使われた。イク(生)、イハフ(祝)、イム(忌)などがそうだ。神々の名前には共通する音が使われた。ヒ(ヒ、ヒル、ヒヒル、ヒレ、ヒラ、ヒロメク)、チ(チハフ、チハヤブル)、ニ(ニホフ、ニフブ)、タマが代表格として挙げられている。
「呪力の信仰は言葉にも認められ、言霊信仰では、めでたい言葉はめでたい結果を、不吉な言葉は不吉な結果をもたらすとする」という古代人の考え方によって、呪術や祭祀に係わる多くの言葉の中にこうした音が取り込まれていった。こうした言葉のフェチシズム体系が言霊の正体ということか。
呪術を信じた人々にとって、当時、言葉を操る行為は魔術に近かったのだろう。一方、現代の日本人は言葉はコミュニケーションのツールであると割り切っている。おかげで呪術的な側面をほぼなくしてしまったのだなと思う。この本を読むと、かつて日本語に備わっていた霊的パワーを考古学的に知ることができる。古事記・日本書紀が好きな人は一読の価値あり。
・日本人の禁忌―忌み言葉、鬼門、縁起かつぎ...人は何を恐れたのか
http://www.ringolab.com/note/daiya/2004/01/post-51.html
・日本の古代語を探る―詩学への道
http://www.ringolab.com/note/daiya/2005/03/post-210.html
・古代日本人・心の宇宙
http://www.ringolab.com/note/daiya/2004/05/aaulesif.html
・図説 金枝篇
http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/05/post-563.html
・聖なるもの―神的なものの観念における非合理的なもの、および合理的なものとそれとの関係について

長いタイトル...。
何かを「聖なるもの」と認識するときの"ヌミノーゼ"な感情についての論考。1917年にドイツの宗教学者ルドルフ・オットーによって書かれた宗教学の古典。ヌミノーゼはヌーメン(神性、神霊)という言葉から作られた造語。
ヌミノーゼは複合的な感覚だ。
・被造物感(絶対的なものの前にして感じる絶対依存感)
・畏るべき神秘
-優越するもの
-エネルギッシュなもの
-全く他のもの
・魅惑するもの
・不気味なもの
などの感覚が混ざっていると分析されている。
「私達たちは畏れつつ聖所を敬うが、そこから逃げようとはしないで、かえって中に入ろうとする。」とルターが言ったように、神様に対する私達の感情はアンビバレントなものだ。
私は平均的日本人の無宗教(敢えていえば仏教か)なのだが、キリスト教的なヌミノーゼの感覚はわからないでもない。私はカトリックの幼稚園に通ったが、その入り口にあった純白のマリア像が、怖くてたまらなかった。シスターや保母らに「いつでも神様がみていらっしゃるのですよ」と教え込まれた。それは悪い人間を罰すると同時に真善美の象徴だった。
ヌミノーゼの感覚能力は経験によって誘発されるが、経験に先立つアプリオリなものだと著者は考える。言語学においてチョムスキーが主張する先天的な言語能力と同じように、ヌミノーゼの感覚能力は原初的なものだとする。人間は自然の驚異に対して神的・デーモン的な畏怖を感じることによって、生き延びてくることができた種であるのかもしれない。
そして本書は「聖なるもの」の非合理的な部分と合理的な部分に関する考察である。いくつかの心理的な要素で説明しようとしているが、同時に著者はヌミノーゼなものは完全に要素に還元できるものではないと論じている。宗教は心理学や社会関係で説明できるものではなく、宗教以外の何者でもないというのである。
「宗教において非合理的な要素がいつでも活発で、生気があることは、合理主義を防ぐ備えがあることである。宗教が合理的な要素で豊かに満ちていることは、狂信や神秘狂(Mysizismus)に沈み込んだり、それに固執することを防ぎ、高級宗教、文化宗教、もしくは人類宗教になることを初めて保証する。」
だからキリスト教は偉大なのだというオチに落ち着く。
宗教はいろいろあるが根本はこのヌミノーゼの感覚にあると思う。その根深さ、複雑さが現代世界の争いに繋がっているのだとすれば、この古典は今また読まれるべき本な気がする。