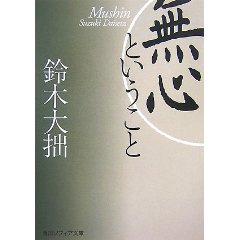Books-Religion: 2008年7月アーカイブ
遠野物語の民俗学者 柳田 國男による妖怪論。
「われわれの畏怖というものの、最も原始的な形はどんなものだったのだろうか。何がいかなる経路を通って、複雑なる人間の誤りや戯れと、結合することになったのでしょうか。幸か不幸か隣の大国から、久しきにわたってさまざまな文化を借りおりましたけれども、それだけではまだ日本の天狗や川童、または幽霊などというものの本質を、解読することはできぬように思います。」
これは昭和13,4年頃に書かれたもので、農村にはまだ電気が通じておらず、マスメディアも発達していなかった頃の研究だ。村々の伝承の中には無数の妖怪が登場した。柳田は全国の有志研究者のネットワークを組織して、それらの情報を集約した結果、そこに多くの共通性を見出した。
たとえば河童である。
「私たちの不思議とするのは、人は南北に立ち分かれて風俗も既に同じからず、言葉は時として通訳を要するほど違っているのに、どうして川童という怪物だけが、全国どこへ行ってもただ一種の生活、まるで判こで押したような悪戯を、いつまでも真似つづけているのかという点である。」
ちなみに妖怪を当時の人々はオバケと呼んだ。これは亡くなった人の霊である幽霊の類とは似て非なるものである。
柳田はまず、オバケ(妖怪)は、
・出現場所がだいたい決まっている
・相手を選ばずに現れる
・出る時刻は決まっていない
という性質を持つのに対して、
幽霊は
・向こうからやってくる、追いかけてくる
・これぞという特定の者にだけ現れる
・およそ丑三つ時ぐらいに出る
という違いがあると定義した。
幽霊は個人的なものであるのに対して、妖怪はもっと人々の広く共有する民俗や自然に根ざしたものということ。
柳田は昔の日本の農村部では「人が物を信じ得る範囲は、今よりもかつてはずっと広かった」というが、結局、何が当時の日本人にそういう想像力を働かせていたのだろうか。この本はそれを具体的に追求する小論集である。
柳田は事例の収集に凝るのみで特に結論を出すわけでもないのだが、話を総合すると、それは昔の生活には薄暗がりがよくあったことに起因するのではないかと思った。それは電灯照明が普及していないからこその薄暗がりでもあるし、メディアが未成熟であるが故の情報の薄暗がりでもある。
見たことがない他所者が夕暮れに村はずれの道を通るのに出会う、ということは村人にとってとても怖ろしいことであったという。黄昏(タソガレ)とは「誰かそれ」に由来する言葉だ。薄暗い場所で見知らぬ者と出くわす恐怖を日本人が共有していたから、できた言葉なのだ。
谷崎潤一郎は「陰影礼賛」で薄暗がりが日本人の侘びさび的感性を育んだと書いたが、妖怪を生んだのもまた同じ薄暗がりだったのではないかと思う。そうした美的感性が衰退し、妖怪がいなくなったのも、文明の光とメディアネットワークによる薄暗がりの全滅によるものだとすれば納得がいく。
・陰翳礼讃
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/005012.html
柳田が14歳のときに青空に無数の星が輝く様子を幻視した体験を告白しているところも興味深い。資料を集めて冷静に分析するだけでなく、そうした怪異をリアルに感じることができる心性を持った人だったからこそ、民俗学の祖となりえたのだろう。
妖怪というと水木しげるの妖怪論も面白いのだが創作要素が強い。本物志向を求めるならばフィールドワークから集成されたこの妖怪論がかなり濃い内容だ。巻末の妖怪の名簿(特徴説明つき)は貴重な資料と思う。
お葬式でお坊さんとゆっくり話す機会があった。いろいろな本を読むのが好きだという話になったとき、私は調子に乗って「仏教(の本)は哲学や科学と似ていて宗教っぽいくないのが好きです」と言ってしまった。お坊さんはニヤリと笑われて「いやいや、仏教は突然天から何かが降ってくるみたいなところがあるものです」と返された。冷や汗たらたらだった。
禅思想の大家 鈴木大拙の本はどれも難解なのだがこの本は講演の口述筆記を中心にまとめたものなので、すこしだけ読みやすかった。いやそれでも半分わかったという気がするレベルだが。これは「無心」ということが仏教思想の中心であり東洋思想を特徴づける重要概念だとして、大拙が8回の連続講義を行った記録である。
無心ということは木や石ころみたいな絶対的受動性の世界だ。分別を超えた無分別であり、絶対無価値の世界を指しているという。神や仏を無条件に受け入れるということでもあるのだろう。そして同時に天啓=ひらめきの舞い降りる創造的な状態でもあると思う。
「この受動性がいろいろな型となって、真宗には真宗の、禅宗には禅宗の、キリスト教にはキリスト教のそれぞれの型がある。その型で受け入れるが、ちょっと見たところでははなはだ違ったようでも、その本を探して来ると心理学的に受動性というものがいずれの宗教にもある。」
前述のお坊さんが言われた「突然天から何かが降ってくる」というのと同じ意味だと思った。私のように知的好奇心から仏教を頭で理解しようとする限り、この宗教の受動性という本質はつかみづらい。
「阿弥陀さんは、あるから信ずるのではなくして、信ずるからあるのです。信ずることができるからあるのです。その絶対の受動性の中にはいってくるから信ずるのです。受動性のものに動的性格が出てくるから、そこに一種の信なるものが出るのです。」
鈴木大拙は古今東西の思想家宗教家の無心論を縦横無尽に引用しているが、心学の祖 石田梅巌の南無阿弥陀観が興味深く読めた。
「南無阿弥陀仏になれば、我と云ふものあるべきや。我なければ虚無の如し。虚無に南無阿弥陀仏の声有て唱れば、此即ち阿弥陀仏なり。阿弥陀仏直に御名を唱玉ふは説法にあらずや。此説法の功徳に依て、弥陀を念ずる行者も、念ぜらるる方の仏も、双方ともに一体と成り、苦楽の二つを離れ終るなり。離れ終って無心無益の不可思議となる。是を名て自然悟道とも云ひ、能所不二、機法一体とも云ふにあらずや」
心を空っぽにして南無阿弥陀仏と唱えると、唱えた行者も仏も一体となって無心無益の不可思議になる、というわけだ。唱えた行者が無心になるという平面的な展開ではなく、行者と仏が観照しあってメタレベルに突き抜けた無心になるということなのだ。こうしたひらめきが舞い降りて思考のフレーム自体を根本から作り替えてしまう悟りの瞬間は宗教体験に限らず普遍なのではないかと思う。
「それゆえわれわれのいわゆる心というものは、はっきりと自覚できる面もあるが、また全く自覚できない面もある。そうしてこの無自覚方面の方が、空間的にいえば、自覚面よりもずうっと広いといってよろしい。あるいは深いといってよろしい。この深い広い無自覚面、あるいは無自覚層といってよいが、そこからいわゆる百鬼夜行的にいろんなものが自覚面へ飛び出す。飛び出たところで初めて気がつくが、その先はどこからどうして来たものか全くわからぬ。これを妄想と仏教では言う。」
この妄想をうむ我執を次元を超越して新たな安定状態を求めると無心が出てくるらしいのだが、無心というのは何もないのではなく、むしろ全部入りなのだ。物理学に似ている。百鬼夜行的いろんなものがランダムに出てくる世界をミクロの量子力学的世界とすれば、無心はマクロの世界に生じる現象である、という解釈で読めそうに思う。無意識や本能にまかせるのが無心ではないのだ。ここでいう無心はもっと洗練された人間化された安定状態を指しているのである。
この講話集ベースの本を読んで鈴木大拙が難解なのは言葉の専門性もあるが、三段論法や弁証法で話が展開しないからじゃないかなと改めて気がついた。「如何なるか是れ無心」に対して「日々是好日」でも「麻三斤」でも「解打鼓」でも正解だという禅問答と一緒なわけだ。それに慣れると二次元の絵が三次元に突然立ち上がってくるような驚きが随所に見つかる濃い内容の本であると思う。
・禅的生活
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/002275.html
・シッダールタ
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/02/post-708.html