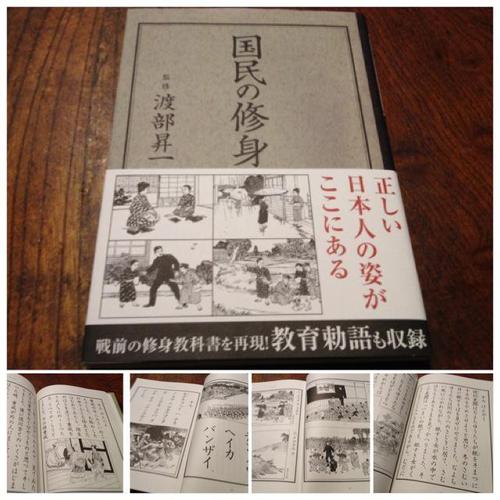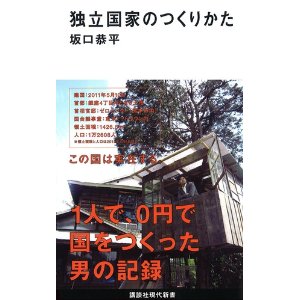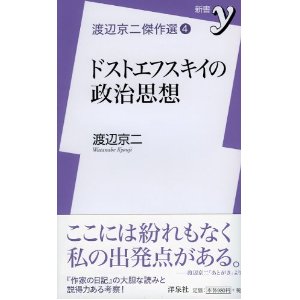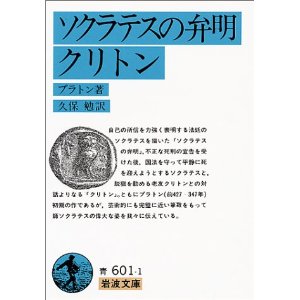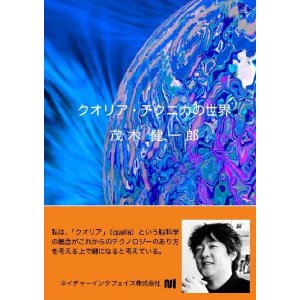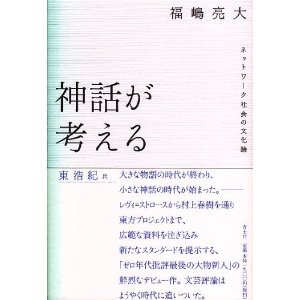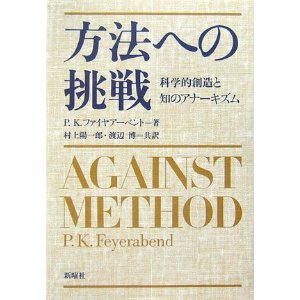Books-Philosophyの最近のブログ記事
いかにもフランス人らしい哲学的な前衛マンガ。
ある日、住民登録所で「名字も名前も神です。一般には神と短く呼ばれています」と答える人物が現れる。さまざまな取り調べや尋問にあっても神であることは疑いないことが判明して世界は騒然とする。そして群衆は巨大な裁判所を立てて、神の責任を問う「永遠の裁判」が開く。神の責任とは何か。神の能力とは何か。あらゆる職業の人々がディスカッションをする。
神は世界を創造した後、すぐに舞台裏に引っこんで、自分が発明した因果律に支配された世界の出来事を観察している存在だという見方が弁護側のスーパーの従業員から提示される。しかし、そんなことは許されない放任であって有罪ではないかと原告団は返す。終わらない議論。神は裁判官をじっとみつめて、全知であるとはどういうことかをたとえ話で説くと、裁判官は無言で退場する。神をめぐる議論をメタ視点から俯瞰する。
裁判後にはメディアによって顔写真が広められてアイドル化する神。ゴッドランドというテーマーパークができて、天国や地獄のアトラクションにキャラクターグッズ。本や映画、テレビでも神は大人気のタレントであり、コンテンツになる。神様降臨という大儲けのチャンスに誰もが群がる。現代における神を風刺している。古今東西の哲学や小説などから多数の引用や言葉遊びが仕掛けられており、読む側の教養が求められる。
大人も楽しめるというか親子揃って考えさせられる深い絵本のシリーズ。
フランスで数々の賞をとり世界19か国に翻訳されて話題になっている。
大人と子供向けの哲学教室を開く哲学博士の先生オスカー・ブルニフィエが文章を書き、ビデオゲームや舞台芸術も手掛けるイラストレーター ジャック・デプレが絵(写真)を担当した。
「結論が出ないことを尊重する」本である。
『よいこと わるいこと』は、善悪とは何かを教える内容だが、いきなり1ページ目が「よいこと わるいこと といっても ひとの考えはさまざまです ときには正反対のことだってあります」という始まり方をする。そして善悪に対しては、世の中にさまざまな考え方があることを示し最後に「あなたは?どう思いますか?」でしめくくる。何が善で、何が悪という結論は一切示しれくれないのだ。
『神さまのこと』では、神さまという概念に対してもまたさまざまな考え方があることを次々に示していく。神は実在すると考える人もいれば観念だと思っている人もいる。一神教と多神教の違いもあるし、そんなものは迷信だと退ける人もいることを示す。そしてやはり最後は「あなたは?どう思いますか?」だ。
哲学とは自ら考えることを学ぶ学問なのであって、よいこととわるいことのリストや神とは何かという定義を学ぶ学問ではない。当たり前のことだが、重要なことが、学校の教育では忘れられている気がする。子供に読ませたくなる本だ。
修身に学べ。渡部昇一監修。戦前の修身の教科書を再現。教育勅語も収録。祖国を大切に。思いやりをもとう。正直に生きよう。家族を大切にしよう。礼儀を守ろう。我慢強くなろう。時代を感じる挿絵とカタカナで書かれた文字で、修身の授業の雰囲気をそのまま味わえる。(カタカナで長文は読みにくいのでちゃんと現代の文章版も収録されている)
正直を教えるページでは、
「ある呉服屋に、正直な丁稚がありました。ある時客の買おうとした反物に傷があることを知らせたので、客は買うのをやめて帰りました。主人は大層腹を立て、すぐに丁稚の父を呼んで「この子は自分の店では使えない。」と言いました。父は自分のしたことはほめてよいと思い、連れて帰って他の店に奉公させました。この子はその後も正直であったので、大人になってから立派な商人になりました。それにひきかえて、先の呉服屋はだんだん衰えました。」
などという題材が挙がっている。子供に考えさせる要素と解説する箇所がうまく設計されている。
いや、ま、よいこと言っているのではありますが、時代が時代なのでテンノウヘイカバンザイで始まるのが修身。身を捨てて死んだ軍人の話も美化されている。戦争をはじめたのもこれらの思想であり。敢えて道徳教育を強く教える時代というのはあまりよくない時代なのかもしれないとも思った。
「欧米は道徳教育は主として教会がやることになっていたが、日本では宗派・学説・洋の東西・時の古今を問わず、万人が認める徳目を学校が教えることにしたものであった。」
とあるが現代日本において道徳というのがなじみにくいのは、宗教というベースを日本人が共有していないからだろう。
資料としては面白い本。増刷でている。産経新聞出版。
意識の進化に対して大胆な仮説を提示した名著『喪失と獲得―進化心理学から見た心と体』のニコラス ハンフリーの近刊。
トマトが赤いと意識するとはどういうことか。著者によればトマトから反射した光が目に届くと、脳は局所的に活性化し、内在化した表現反応を生み出す。"赤"する状態になる。その状態を自分自身が観察して、自身の反応から形成する表象が赤の感覚なのだという。赤いとは自分自身が赤を感じていることを観察することにほかならない。意識は自己発生的なショーである、と。
現実の空間ではありえない形状のペンローズの三角形があるとする。ある角度からみたときだけペンローズの三角形に見える立体物をつくることは可能だ。それをグレガンドラムと呼ぶ。そしてそれをみた人が生み出す内的創造物をイプサンドラムと呼ぶ。そのうえで観察者が動くと自動的にグレガンドラムも同じ幻想的外観を見せるように動くしくみがあると仮定する。
第三者がこの観察の様子を見たら、ペンローズの三角形などどこにもないわけだから、その存在を信じることはナンセンスに思える。しかし志向性をもって特定の角度からグレガンドラムを眺める人にとっては、内的に発生するイプサンドラムと矛盾しないのでペンローズの三角形を知覚する。意識とは自分を相手にしたマジックショーみたいなものだと著者はたとえる。感覚反応の内的モニタリング自体が意識を生じさせる。進化論的になぜそのようなフィードバックループが生じたのかを論じている。
「そこに存在するという感じをあなたに与える感覚は、あなたの感覚器官への刺激に対する、あなた自身の能動的な反応から生じるのだ。感覚は最初から、一種の行為を含んでいる。これはつまり、あなたの中核的自己を生じさせるのは、行為を行うあなたの自己にほかならないという重大な意味合いを持つ。あなたであるとはどいう感じかは、最も深いレベルではあなたが決めることなのだ。だが、それならば、次なる妙技として、こういうのはどうだろう?ソウルダスト、すなわち、魂の無数のまばゆいかけらを、周りじゅうのものに振りまくというのは?これも思い出してほしい。現象的特性を外部のものに投影するのは、あなたの心だ。あなたは知らないだろうが、この世界がどのように感じられるかを決めているのはあなた自身なのだ。」
私秘的な意識を自然科学がどの程度解明できるか?文学や心理学など文系の学問とも融合して総合的に論じていくスタイルは「喪失と獲得」と変わらない。結局は純粋な理系の論にならないので反証は難しい気もするけれども、著者は、人間にとってなぜ世界が美しいのか、人生が素晴らしく感じられるのか、の理由を、進化心理学にみつけようとしているのが面白い。
喪失と獲得―進化心理学から見た心と体
http://www.ringolab.com/note/daiya/2005/01/post-193.html
建築家には変な人が多い。著者は熊本に勝手に新政府を設立し、初代内閣総理大臣に就任した似非建築家だ。震災後に逃げろといわなかった政府に失望し、「プライベートパブリック」という概念を唱え、「新政府」を勝手に始めてしまった。所有権があいまいになっている土地を全国にみつけては領土としている。
とはいえ日本には、法律というものがある。内乱罪にならないように新政府活動は「芸術」と呼び、社会を変える行為としての芸術活動として、新政府をやる。トンデモのようでいながら、相当なしたたかさを持った人だ。現代の日本社会の楽しい歩き方を教えている人でもある。
お金がなくても楽しく暮らせる社会を目指す。たとえば0円特区構想。お金を稼がなくても楽しく生きていくために「態度経済」を実現せよと説く。それは「社会を変えよう、少しでもよくしようという態度を見せ続ける人間を、社会に飢え死にさせちゃまずいと考え、相互扶助を行い始める」という状態をいう。
「ただ人が歩き、話し、ハイタッチする。それで経済がつくられる。なぜなら、そこにはとても心地よい家や町や共同体があるからである。」。プロボノ的な労働や相互扶助の精神で、個人がお金も土地も所有しない幸福社会を夢想する。ただその世界はまったくの別天地に作るのではなく、現実の日本と同居しているのでもある。
現実世界の上に仮想的な新しいレイヤーを想像する力を持つことで、今の日本にいながらにして、新しい生き方の可能性を探っているようにみえる。この人は社会を転覆させるのではなく、私たちの意識、考え方を転覆させる、モダンな革命家なのである。現実的でありつつ夢想家でもあり、モノづくりに手も動かす思想家。いいなあ。
まず私がいつも感じていた弱者の味方とか一部社会運動家の胡散臭さについて
「たとえ百姓であれ労働者であれ、思想が構築される過程の端緒に立つとき、彼は必然的に普遍性へ向けての上昇を強いられるのである。これこそ知識人と民衆との断絶の原因であり、それは民衆に精通したり、民衆の習慣になじんだりすることではこんりんざい解決されえない。ドストエフスキイのいうように、そういうことは旦那の道楽にすぎないのである。」
と書かれていて深く同意。民衆の代表も、弱者の代弁者も、もはや思想を語ってしまった段階で、民衆でも弱者でもない。似非である、と思うわけです。
で、これはドストエフスキイの不評な著作『作家の日記』における民衆賛美調の政治評論を肯定評価する内容です。ドストエススキイの民衆論は、そういう薄っぺらいものではなくて、もっと複雑で意味のあるものだというのです。
ドストエスフキイは、
「誰の目にも入らぬ生活をして誰の目にも入らぬように死んでいくもの」
「この地球上に誰ひとり覚えているものもなく覚えている必要もないもの」
に対する好奇心や想像力、そして深い共感をする夢見る人であり、その民衆の政治意識に関する語りは、民衆の根源的な性質をとらえた意義のあるものだと再評価する渡辺京二がいます。
移送される罪人に民衆が小銭を投げるロシアの伝統に触れた後で、
「日本の場合もロシアの場合も、近代的な法の観念、とくに契約にもとずく義務と権利の観念は、ヨーロッパ近代文明を構成する諸要素のうち民衆にとってことになじみにくいものであったが、そのことの根底には、このような罪人に対する反応に示されるような人間観、現世的な法や規範は人間を仮にしかさばき拘束しうるものではないという或る種のアナーキーな感覚、罪人を聖なるものと感じて心情的にそれと同化するような、彼岸的ともいうべき同胞感覚が存在したのではなかろうか。」
近代市民社会と合理主義の文脈において当時の知識人に稚拙である、辟易するとされたドストエフスキイですが、実はもっと人間の深い理解に根差した想像力をはたらかせて民衆を語っていたといいたいらしいと理解しました。夢想家であり同時に政治思想家であることは可能だと。
1880年ごろドストエフスキイが書いた『作家の日記』について、その100年後に渡辺京二が再評価した本を、その出版37年後にこうして読んで、議論する。3つの時代の文脈が相当に違うわけで、我々は考古学的に知識を整理して読んで理解するというより、同時代の文脈で恣意的に読み解いて、自分たちなりの面白さを発見するのがいいのでは?と思いました。
新しい概念としての「拡張した心」を中心に意識の問題を考察する。
「第一に、人間の心のはたらきと呼ばれているもののほとんどは、環境と円環的再帰的にインタラクションすることで成立していることである。人間の身体内部のはたらきは、そのループの一部をなしているにすぎない。そして、その円環的な相互作用のなかには、より小さな円環的相互作用が入れ子状に含まれている。」
そして著者は人間的環境を5つの構成要素に分類する
1 改変環境 都市や農村、人間の手が入った森林
2 構築物 家屋や建造物
3 道具 何かの目的を達成するための道具
4 他者 共同したり競争する他者
5 社会制度 言語や法、株式会社や保険、民主政治など集団行動のしくみ
こうした環境と連続的に相互作用をするアクターズネットワークが人間の世界なのだという。そして社会的アフォーダンスに反応する能力を持つ、自律的な存在として人間をとらえている。意識はないが、全体の文脈の中に自由意思はちゃんとあるのだと。「拡張した心」は環境や文脈と一体化している相互作用プロセスなので、ここに心とか意識がありますと部分的に切り出せるものではない。
著者が「実在しない」と否定するのは、脳の中に外界で起きていることが投影されるという「チューブタイプ」の意識だ。クオリアがやり玉に挙げられる。クオリア論者は、意識とは外界刺激を取り込んで映すスクリーンのようなものという。情報が神経系を伝わって脳に集まり、脳の中の心の座で情報が解読されるとする。しかし、著者は脳に伝達されるのは実際には刺激や興奮であり、それはどこかに終点があるわけではないだろう、と反論する。クオリアという主観的な内的性質は、外界の知覚対象のあり方から抽象された観念に過ぎないと批判する。
"脳が世界を見ている"のではない。あなたの心は"環境に広がっている"というのがこの本のメッセージである。後半では、人間には世界の中に実在する社会的な意味を読みとって相互作用をする存在たと言う「社会的アフォーダンス論」が展開されている。人間と環境の複雑な相互作用するアクターズネットワークとしての世界という世界観、ここも面白かった。
吉本隆明の論考集。文学、批評、戦争、生き方、才能、日本。わかりやすく、話し言葉風に語っているので、読みやすいのだが、10ページおきくらいに、さらっと深いことが書いてあって気が抜けない本である。この思想家は老いてからのほうが、一般読者にとって魅力を増していると思う。
いくつか私が感銘したポイントを文学論中心に抜き出してみる。
■俺だけにしかわからない価値
「文句なしにいい作品というのは、そこに表現されている心の動きや人間関係というのが、俺だけにしかわからない、と読者に思わせる作品です。この人の書く、こういうことは俺だけにしかわからない、と思わせたら、それは第一級の作家だと思います。とてもシンプルな見分け方と言ってよいでしょう。」
読者に「俺と作者にしかわからない」と思わせる作家は超一流で、「俺たちの世代にしかわからない」レベルがそれに次ぐ一流で、それ以外は全部普通の作家であるという。吉本隆明の文学批評の評価軸が鮮明にわかる。
■文学の有効性
「結局、初めは自分を慰めるだけのための密かに書いたものが、何となくいつの間にか人の目に触れるようになって、固定の読者も増えていく、そうして、その固定の読者にとってもまた、作品がその人を慰めるために役立つというのが、文学の本質的な有効性ではないでしょうか。」
文学の価値とは、自分の慰めが他者の慰めになるということ。それ以上でもそれ以下でもない。エンタテイメントの基本ともいえる定義だ。まず自分が楽しい表現の営為に始まる。最初から大衆に迎合して表現するようなのは二流、三流だということでもある。
■本の毒
「小説によっては、犯罪や人間失格的なものに価値を見出す内容のものもあります。それを読んで心を動かされることはあり得るでしょう。そして、現実世界でも人間失格的なものを目指そうとする。これを、毒がまわったととるか、人間として高度になったと解釈するか、人によって意見は分かれるかもしれません。ただ、どちらにしても確実なのは、何かに熱中するということは、そのことの毒も必ず受けるということです。」
だから文学を読めば感性が豊かになるとばかり考えていると間違うぞという。豊かにもなろうが毒も回るから、毒とのつきあいかたも覚えておかないと死ぬぞと脅す。昔は自分の思想を読んで運動に身を投じて死んだ若者がいたわけだし、三島由紀夫も自らの毒がまわって死んだんだと、時代を背負っていた思想家の迫力の論が続く。文学や思想のもつ毒の役割を強調する。善悪二元論で割り切るな、と。
人間の生き方は思春期の頃の母親との関係性で大方決まってしまうとか、明るい社会は滅びに向かう特徴で世相は暗いくらいがいいとか、三島みたいに人工的なのは無理があるとか、吉本孝明の、ちょっと偏った気がしないでもないが、歯に衣着せぬストレートな物言いが心地いい。
昭和の思想の深さを見直す文庫本としては
・人間の建設
http://www.ringolab.com/note/daiya/2010/05/post-1222.html
もよかったなあ。
即興芸術の本質とはなにか?。音楽のインプロビゼーション演奏と前衛演劇の表現を題材にしながら批評家 佐々木敦が「驚くべきことは、いかにして起こるのか?」を考え抜く。
優れた即興演奏は聴く者の期待を裏切ると同時に満足させる。音楽の約束事やありがちなパターンから自由でありつつも、音楽であることを止めてはいけない。演奏者と演奏者、そして演奏者と聴取者の想像力のせめぎあいの中から、即興は生まれてくる。それは「支離滅裂」や「破綻」や「台無し」とは違う定型なき形成だ。
「「即興」には常に「予測を予測する」というメタ的な審級がある。それはいわば「先読み」のひたすらな連鎖である。「演奏者」は「聴取者」の現前の認知によって、そのような「メタ予想」の交錯に巻き込まれざるを得なくなるし、逆に「聴取者」の方もまた、刻々と脳裏に浮かぶ自らの「予測」を「演奏者」がどこかで「予測」しつつ音を紡いでいることを忘れるわけにはいかない。こうして両者の「予測」と「メタ予測」(と「メタメタ予測」......)が激しいフィードバックを繰り返しながら、ある一度ごとの「インプロ」は生成されているのである。」
そもそも完全に自由な即興なんてあるのかという問題がある。表現者はあらかじめたくさんのイディオム、語彙を持っていて、適宜繰り出すだけではないのか?。実はイディオムの介在こそが非イディオムを可能ならしめるものなのだと著者はいう。
1)「イディオム」の編成/収斂を極力拒絶し、安定的な「構造」の成立を阻害しつつも、しかし「破綻」だけは回避し、広義の「構造」化への傾向性は担保すること
2)その場に存在する「他者」との応接、関わり合いを、一方的/根底的に反故にしないこと。
演奏=クリエイション、演奏=コミュニケーションという二つの制約条件に縛られながら、共同体の文法や言語体型、価値判断からの逃走と闘争を指向する。予定調和と思われないギリギリのラインでの破壊的創造が即興なのである。
即興やライブの魅力はデジタル複製コンテンツの時代にあって、むしろ希少性と言うか「本物」として価値は高まっていくものだと思う。
「演劇もダンスも僕が興味があるものって実は同じものなのかもしれなくて、それは要するに演劇もダンスも「今ここで一回しか起きない」っていう、「今ここ」っていうものに繋ぎ止められている。基本的には可能性の縮減の方だと思うんですよ。制限。今ここで起きた事をもう一回やってって言われても、もうそれって同じじゃないじゃんというのがあるわけじゃないですか。それがもう決定的で、そこの部分っていうのをどういう風に考えるかっていうのが、いわゆる複製芸術とかって言われるものとの違いだと思うんですよ。」
言語による即興の本質の解体は難しい。DVDや録画で後からでも見られるのにライブで見たいと思う心理は万人にある。それは即興ライブへの経験に基づく期待であり、即興の価値を証明することがいかに難しくても、それは必ず存在しているはずだ。
アレクサンドロス大王の家庭教師だった哲学者アリストテレスは、プラトンの弟子で、プラトンはソクラテスの弟子だった。ソクラテスはギリシア哲学の源流だが、彼自身は著作を残しておらず、弟子のプラトンらが、その思想を後世に伝えている。
ソクラテスはちょっと空気の読めない人だったようだ。
同時代の賢者と呼ばれる人たちを訪ねては問答して、彼らが無知を暴いて回った。そして彼らが無知であることに無自覚であるのに対して、自分は無知であることを自覚しているから、自分の方が優越していると人々に説いた。その結果、怒った賢者たちによって「ソクラテスは善良な市民を惑わす教えを広めている」と告発され裁判にかけられる。自業自得な気がするが、死罪が求刑の法廷で被告人が答弁したのが『ソクラテスの弁明』である。
私は無知であることを知っているから賢者であるという思想や、自分は貧乏だがそのことこそ私が清く正しいことの証明だとか、死を逃れるよりも悪を逃れることの方が難しいぞなどと反論をするが、高所からの物言いが、裁判感や陪審員に気に入られるはずもなく、死刑が確定してしまう。
実はこの死刑はソクラテスが牢屋から逃亡すれば、容易に逃れることができるものだった。そこで親友クリトンが牢に行って脱獄しなさいと勧めると、国法を守って死ぬことの正しさを滔々と語った。それが併録されている『クリトン』だ。結局、死ななくてもよかったのに、頑固なソクラテスは信念に殉じて毒を飲んで最期を遂げたといわれている。
スピーチの天才100人 達人に学ぶ人を動かす話し方
http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/100-4.html
この本がきっかけで読んだわけだが、
"出発の時間になりました。これから私たちはそれぞれの道を行くことになります。私は死に、みなさんは生き続けます。どちらがよい道なのかは、神にしかわかりません ─── 「ソクラテスの弁明」紀元前399年、ギリシアのアテネで(プラトン著「ソクラテスの弁明」より)"
の文脈がよくわかった。
・切りとれ、あの祈る手を---〈本〉と〈革命〉をめぐる五つの夜話
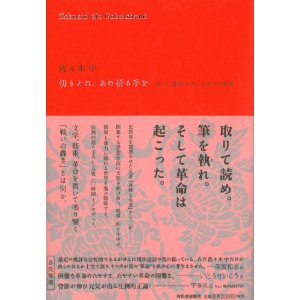
大量の情報からおいしい部分を摂取する電子書籍の時代は、深い読みが難しくなるのかもしれない。そういう時代の変わり目に、敢えて深い読書論を説く。強く響いた。
読むという行為は真剣勝負だ。そもそも他人が書いたものは読めないという。
「本を読むということは、下手をすると気が狂うくらいのことだ、と。何故人は本をまともに受け取らないのか。本に書いてあることをそのまま受け取らないのか。読んで正しいと思ったのに、そのままに受けとらず、「情報」というフィルターにかけて無害化してしまうのか。おわかりですね。狂ってしまうからです。」
ニーチェやカフカが本当の意味で読めてしまったら気が狂う。他人の夢をそのまま見るということは、正気を失うということだ。著者は世界の歴史を動かしてきたのはリテラシーにまつわる革命であったとみる。ルターやムハンマド、中世の宗教改革を振り返り、テクストを、本を、読み、読み変え、書き、書き変えること、すなわち文学(リテラシー)こそ革命の根源にあるというのがこの本の主な主張だ。
読むことや書くことが人の生き死にに関係しない社会になって久しい。ネットの時代には、ブログで書いた意見を批判されたら、翌日にスイマセン、僕、間違ってましたとかけば終わりだ。「転向」や「総括」なんてものものしい単語は死語になりつつある。
近代の思想や批評が、「「すべて」のものについてちょっとは気の利いた一言を差し挟むことができる技術」になりさがってしまったと知識人の堕落を批判する。
「ありとあらゆるものについて、「すべて」について、「それ知っているよ、これこれこういうことでしょ、それってそういうものに過ぎないよね」と脊髄反射的に言えるようになること。それによってメタレヴェルに立ち、自らの優位性を示そうとすること。これが思想や批評と呼ばれていたし、今でも呼ばれている。」
確かにいまは情報を効率よく処理して立ち回る方が、賢く見えてしまう時代だ。言葉に魂がこもらない時代には「言霊」もない。この本は読むこと、書くことの意味が軽薄になっていく今、敢えて命がけの読書の価値を再考する。
茂木健一郎のエッセイ集。表紙は河口洋一郎のCG。
『Nature Interface』誌連載をまとめたもの。タイトルのクオリア・テクニカとは、
「街頭テレビ、コンピュータゲーム、ケイタイ電話。新しいテクノロジーが登場する度に、人々を熱狂させたものは、便利さや速さやパワーではなく、それまでにないクオリアとの出会いだったのではないか。 環境や身体といった、伝統的な自然の中から生まれてくる質感が「クオリア・ナチュラレ」(自然のクオリア)だとすれば、テクノロジーの生み出す新しい質感は、「クオリア・テクニカ」(技術のクオリア)である。」
というもの、つまり、つくりものの質感のことである。都会に住んでいると、人は360度、人工物に囲まれている。さらにパソコンで仕事をする人、ゲームが好きな人、ケータイ中毒の人は長時間を、画面の中、仮想世界の中で過ごしている。人生の大半はクオリア・テクニカの世界なのだ。つくりものには違いないが、人間にとってもはやこれは本質的なものであることは間違いない。
著者は、「人間の肌のしっとりとした様子、ガラスのコップの透明な照り輝き、風に吹かれて揺れる若葉の緑、といった鮮烈なクオリアは、主観的には、どう考えてもある有限の数値で置き換えられるようには思えない。しかし、有限のビットのデジタル信号に基づく情報処理により、生々しいクオリアを感じさせることが技術的には可能である以上、そのようなクオリアも、客観的な立場からは、ある数字にマッピングが可能である、ということになる。」という。
ブルーレイやDVDの映像に私たちは感動する。リアリティを感じさせるのに有限のビットで十分なのだ。ラブプラスの二次元彼女にだって人は本気で萌える(これは一部限定ですが)。デジタルの表現力、バーチャルの可能性は無限に等しいということだろう。有限のビット数がきっかけになって脳にその情報以上のものが生み出されていくからだ。
脳におけるクオリアのはたらきの考察、創造性、イノベーション、インターネット、文明論など著者らしいテーマが続く。4ページで1つの短いエッセイが27本。どれも気づきのエッセンスだけなので、さらっと読めるが、それぞれじっくり考えさせられる内容。創造的な未来へ向かう提言も多い。
私は「イノベーションとセレンディピティ」がよかった。
「セレンディピティという概念が、現代的な文脈で注目される理由は、今日においても、イノベーションは必ずしも対象に関しての完全な知識に基づいて切り拓かれるわけではないからである。「やってみないとわからない」とよくいわれるが、まさに、十分な知識がない状態でも、知識がないからこそ、実験すること、試作してみることには意味がある。知識に基づいて新たな技術がトップダウンによって創りだされるということはむしろ稀であり、知識がないままにとりあえず「やってみる」ことで多くのイノベーションが達成されているのが実感であると考えられるのである。」
情報化の時代は、いろいろなことが、やってみるまえにわかってしまう。だからこそ、やってみることの価値、やってみないとわからないことの可能性があるのだと思う。クオリアの非加算性ということと似ている。
いま考えるべきキーワードが散りばめられた本だ。もう少し咀嚼整理されると読みやすくなると思うのだが、考えるための素材としてはこれくらいの全部入り感があったほうがいいのかもしれない。
正直書き方が難解で私には理解できなかった部分もかなりあるが、現代のネットワーク文化の本質に迫った議論を展開している、ような気がする本である。面白かったな。
著者は文化的な営みをすべて情報処理のプロセスとして見立てる。その上で、神話を「文化における情報処理の様式」ととらえる。ここでいう神話は、レヴィストロースの神話というより、日々生起している現代サブカルチャーやネットカルチャー(ニコニコ動画、2ちゃんねるなど)を指している。神話とはあらゆる"ネタ"だと思う。
1 神話はコミュニケーションを通じて「理解可能性」や「意味」、あるいは「リアリティ」といったものを提供するシステムだということ
2 神話は変換、変形、圧縮、置換といった操作を内蔵したシステムだということ。
3 時間にまつわる処理が本質的である
皆が共有している神話があると、コミュニケーションが活発になって、文化がどんどん進化するということである。「ネットワークを拡張する想像の力に対して、ネットワークを凝縮する象徴の力」。神話は同時代のさまざまな変換アルゴリズムに従って変容してきた。ここではサブカルチャーとネットカルチャーを題材に、この10年くらいの変容パターンが分析されている。
文学の分析の章ではこんなことが言われている。
「戦後日本の純文学の歴史において、これまで高く評価されてきたのは大江健三郎や三島由紀夫、中上健次といった作家である。簡単にまとめれば、彼等は古典的な文芸に遡り、その資源を現実の世界に二重写しにすることによって──つまり、自分自身の肉声を一度遮断し、古い集団言語を再利用することによって──神話を構築してきた作家たちだと言ってよい。<中略>それに対して、もう少し下の世代に当たる村上龍や村上春樹は、集団言語を組成する際に、古典に遡るのではなくむしろ市場の財の助けを借りた。」
これは文学評論だけでなくて、他の評論の分野ででそうかもしれない。特にネットワーク社会で起きていることは、新しいタイプの出来事であって、古い伝統社会の物語の枠では解釈ができなくなっている。伝統的な解釈をするマスメディアの評論家よりも、ブロゴスフィアやソーシャルネットワークで、受ける(売れる)物言いができる評論家が、Webの市場で人気が出る、というのと同じだと思う。
古い神話はもともとは口承でゆっくりと伝わってきたものだと思うが、ネット時代の神話は変換・変形・圧縮・置換のスピードも速そうだ。ライフゲームのように神話素同士が発火や消滅を繰り返し、何百世代を経過していく様子が、まるで生き物のように見える。そういう様子が、この本のいう「神話が考える」という状態のことなのかなあ。まだよくわからない。
・アーキテクチャの生態系――情報環境はいかに設計されてきたか
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/08/post-1040.html
この本が好きな人はこの本もどうぞという関係。
・知識人として生きる ネガティヴ・シンキングのポジティヴ・パワー
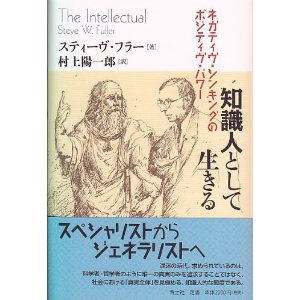
知識人であるために敢えて宗教色の強いインテリジェント・デザイン論を、裁判において支持する証言者をして物議を醸した(冒頭でなぜ支持したか釈明している)という、ユニークな経歴もある社会学者・哲学者が書いた知識人論。
そもそも現代において「知識人」と言う言葉はネガティブにもとらえられがちだが、本書が言うように、従来の知識人の果たしてきた役割に、「市場」がとってかわるようになったことと関係があるだろう。
「変わったのは、かつては責任を持った傲慢な一部の人たち(検閲者)によってなされていた「決定」が、今では多数の無邪気で無責任な人たち(消費者)の間に拡散してしまったということである。」
知識人に変わって「起業家」は市場に人々が求める商品を提示して革命を起こす。いまや知識人なんかより、グーグルやアップルの方がよほど革命的なのだ。では知識人なんてものは不要になってしまったのだろうか?。
「知識人とは、時勢における政治の実践者だ。彼等は後の世代をその支持者とする。彼等の本来の役割は、あらゆる優勢なものは常に一時的であり、覆されるものだということを示し、収支バランスを保つことである。つまり、知識人は、一般的な政治の問題において、その矛先を弱いものではなく、強いものに向けなければならないということだ。すなわち強いものを小さくするか、弱いものを大きくするかのどちらかだ。要するに、知識人は非神話化の実行者あるいはソフィストになることができる。」
著者の主張を、グーグルやアップルの神話を非神話化する役割としてこそ知識人は必要という意味に読んだ。起業家にはそれはできないことなのだ。
「...ある知識の正確な意味は、その創成の時点では、必ずしも完全には把握されていないので、知識生産に最も多く投資する人が、その主な受益者とはならないこともあり得る。それでも、これらの「労せずして稼ぐ」受益者を排除しようとすれば、なお高くつくことになろう。この逆説的な状況は、経済学者が知識を「公共財」と呼ぶ場合に意味されているものを捉えているわけだ。」
いかにも「知識人」らしく、言い回しが凝っていて、全体的に難解な書物だが、冒頭でこの本が言いたいことはやさしく要約されている。つまり、以下のようなメッセージだ。
知識人は、
1 自分自身で評価する能力はきちんと持ったままで、しかし、ものを多面的に読めることができるようにしよう
2 どんなメディアにおいても、どんな思想内容をも、自由に伝えることができるように、自らを鍛えよう
3 どんな論点も、完全に違っているとか、完全に無視できる、などとは考えないようにしよう
4 誰かの意見に対して、自らの意見を言うとき、それを強化するのではなく、むしろ、反対のバランスをとるように計らおう
5 公的な議論では、真実に対しては粘り強く論じ、しかし誤謬に関しては寛容に許容しよう
という志をもつ人であり、それは絶対的な真理を確定させる科学者や、世にでて意見を言うことがない哲学者などともスタンスが異なると定義する。
ネガティヴ・シンキングのポジティヴ・パワーという副題がついているが、実際にいると同時代的には「嫌な奴」であろう。戦争しようと皆が熱くなっているときに、一人冷静に反戦を主張できる人のことだ。だが派手なパフォーマンスはしないから目立たない。大変に損な役回りだろうし、どうやって生きていけばいいのだろうか?。著者は「知識人についてびよくある質問」として問答集でそうした疑問に対して答えている。
スペシャリストの時代から再びジェネラリストの時代へ。絶対的な一つの真実ではなく、社会における「真実全体」を追い求めよう、というメッセージは、グローバリズムとダイバシティがせめぎあう現代において、知の担い手のあるべき姿のひとつを提示している
ように思った。
・知識人とは何か
http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/01/post-517.html
・知識の社会史
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/09/post-1069.html
・インターネットはいかに知の秩序を変えるか? - デジタルの無秩序がもつ力
http://www.ringolab.com/note/daiya/2010/04/post-1210.html
孤高の天才科学哲学者ファイヤアーベントの代表作。知のアナーキズム。ゲーデルの不完全性定理やドーキンスの生命機械論並みに、人生観を変えるくらいのインパクトがある本。
「科学は本質的にアナーキスト的な営為である。すなわち理論的アナーキズムは、これに代わる法と秩序による諸方策よりも人間主義的であり、また一層確実に進歩を助長する。」よって、進歩を妨げない唯一の原理は、anything goes(なんでもかまわない)であるというのがこの本の理論である。
ファイヤアーベントは、科学は一般にどこまでも合理的と考えられているが、実は神話に近いものであり、人類の数多くの思考形式のひとつに過ぎず、特別なもの、最良なものというわけではないと論ずる。なぜなら科学の進歩は、古い合理性の外側からやってきた非合理な発見によって牽引されてきたからである。
「繰り返して言うが、この束縛解放の実践は、単に科学史上の事実であるというだけではない。それは理にかなっていると同時に、知識の発展のために絶対的に必要とされるものである。もっと詳しく言うと、次のことを示すことができる。すなわち、科学にとってどんなに「基本的」であれ、ないしは「必要な」ものであれ、ある規則があったとすると、単にその規則を無視することのみならず、その反対のものを採用することが賢明であるような、そうした状況が必ずあるのである。」
あらゆる方法論が普遍の地位を与えられてはならず、狂気や遊戯、トンデモ科学やきまぐれのようなハチャメチャさにこそ、方法論が真に進化する可能性が秘められているという。秩序ではなく無秩序こそ重要ということになる。
「これらの「逸脱」、これらの「誤謬」は進歩の必要条件なのである。それらはわれわれが住んでいる複雑で困難な世界の中で知識が生きのびることを可能にし、われわれが自由で幸せな行為主体であることを可能にする。「混沌」がなければ、知識はない。理性の度重なる解任がなければ、進歩はない。今日科学の他ならぬその基礎を形成している観念は、ひとえに、先入見、うぬぼれ、情熱のようなものが存在したために、現存しているのである。」
発見の文脈と正当化の文脈の区別、観察語と理論語との区別、共約不可能性といった観点から、完全に合理的で普遍的な方法論よりも、アナーキーになんでもありの方法論の方が、知識の発展において価値があるということを証明していく。結構な大著だが、全体が理性という権威に対する反抗の意思に満ちており、とても血の騒ぐ熱い本である。
遊びや例外はいつだってなきゃいけないのである、それこそ本質なのである、四角定規でなんでも測れると思ったら大間違いなのである。「あらゆる方法論は限界をもち、生き残る唯一の「規則」は「なんでもかまわない(だから好きなようにしろ)なのである。」だそうだ。秩序のない現代にドロップキック万歳。
・理性の限界――不可能性・不確定性・不完全性 -
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/10/post-1099.html
・パラダイムとは何か クーンの科学史革命
http://www.ringolab.com/note/daiya/2010/02/post-1150.html
・知識の社会史
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/09/post-1069.html