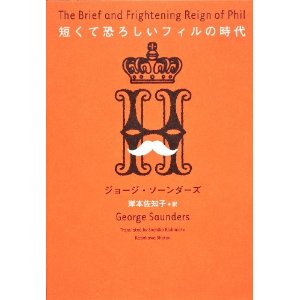Books-Fiction: 2012年1月アーカイブ
これは大傑作。
南北戦争前のヴァージニア州マンチェスター郡で黒人奴隷のオーガスタスは一生懸命に働いて金を貯める。所有者の白人ロビンズから、自分と家族の自由を意味する解放証明書を買うために。そして家長の必死の思いが実って一家は自由の身になった。しかし、少年の頃、ロビンズに可愛がられて育ったオーガスタスの息子ヘンリーは、成長すると黒人奴隷を購入し、奴隷制を嫌う両親と激しく対立する。(黒人が黒人を奴隷として所有することができたという史実にもとづく)。
独立した青年ヘンリーは奴隷を増やし、農園経営で経済的な成功を手にするが、ある日、妻カルドニアと大勢の奴隷を残して突然に他界してしまう。残された妻も彼らを解放することはせず、古くからいる黒人奴隷のモーゼズと逢瀬を楽しむようになる。
人間が人間を所有することが公に認められている世界。白人が黒人を奴隷として所有するだけでなく黒人が黒人を奴隷として所有する。親が子供を奴隷として所有する。愛人を奴隷として所有する。所有者が別の所有者へ商品として売り飛ばす。そんなことが平然と行われていた世界で、ヘンリー周辺の数十人の黒人奴隷たちの過酷な人生を描く壮大な群像劇。
奴隷制度というのは人類史上あらゆる地域で古代から、最近まで一般的に存在していた。人が人を所有しない歴史の方が短いのだ。ここに描かれた奴隷達の境遇は人間にとって何千年間も普遍的にあったドラマなのかもしれない。そして著者は、法律と観念に縛られた不自由な人間たちの人生を、時空を俯瞰した神の視点から物語を記述する。それはまるで私たちが信じている自由や意思もまた相対的なもので、運命から逃れることはできないちっぽけな存在なのだとでもいうように。
長編だがこれといった歴史的な大事件と言うのは起きない。淡々と奴隷の日々を綴っていくだけだ。だが所有者に生殺与奪の権利を持たれている奴隷にとっては、手際が悪くて主人を怒らせたり、命令書を持たず外出して逃亡と間違われたり、などという小さな過ちが命取りになることもある。日常がずっしり重たい。
ピュリツァー賞、全米批評家協会賞、国際IMPACダブリン文学賞受賞作品。
マッカーサー賞受賞の鬼才ジョージ・ソーンダーズによる大人の寓話。テーマは国家の独裁と虐殺と重たいのだけれど、設定がおそろしくシュールで、ユーモラスな語り口で進むので、読みやすい。
こんな風に物語は始まる。
「国が小さい、というのはよくある話だが、<内ホーナー国>の小ささときたら、国民が一度に一人しか入れなくて、残りの六人は<内ホーナー国>を取り囲んでいる<外ホーナー国>の領土内に小さくなって立ち、自分の国に住む順番を待っていなければならないほどだった。 外ホーナー人たちは、<一時滞在ゾーン>にこそこそ身を寄せあって立っている内ホーナー人たちを見るたびに何となく胸糞がわるくなったが、同時に、ああ外ホーナー人でよかったとしみじみ幸せをかみしめた。見ろよ、内ホーナー人の卑屈でみじめったらしくて厚かましことといったら。」
国土がものすごく小さくて、痩せてひ弱な国民が、数学の証明問題を解いている内ホーナー国。それを取り囲む大国外ホーナー国の国民たちは、大きく太っていて色つやがよく、カフェで高級なコーヒーを飲むのが楽しみ。
あるとき、外ホーナー国で革命が起きて、新しい大統領に就任したフィルは、弱小の内ホーナー国を軽蔑しており、国民がうちの領地へはみだしたと言いがかりをつけて弾圧を始める。常に外ホーナー国に言い分はあるが、強者が弱者を力で従わせる構図に正義はない。
後半で第3の国を登場させることで、2つの国の関係を相対化してみせるのも鮮やか。世界認識や価値観がまったく異なる同士では、コミュニケーションがかみあわず、相互理解は極めて難しい。現実の国際関係というのも結局はこどもの社会のいじめみたいなものかもなあと思えてくる。
内政干渉、侵略、虐殺、マスメディアの腐敗、宗教問題...。さまざまなテーマが含まれているが、それらすべてを寓話化して、相対化して、笑い飛ばしていく。真の多様性の時代に必要なのは、こういう軽やかなメタ視点なのかもしれない。
スティーヴン・キングの短編集。原著は85年の出版。キングが18歳の時に書いた『死神』などごく初期の作品も含めて6編。
映画『ミスト』の原作となった中編『霧』が収録されている。これ目当てで読んだ。
突然の嵐の後、湖畔の町に白い霧が降りてくる。主人公と幼い息子は車でスーパーマーケットへ買い物に行き、商品を見ている間に、店は視界を閉ざすほど濃い霧に包まれる。外から血まみれの男がかけこんできて霧の中に何かがいるぞと叫ぶ。不気味ななにかによって外へでた人々が惨殺されていく。閉じ込められた数十人のお客と店員たちは、恐怖の数日間を過ごす。得体のしれない怪物が襲ってくる怖さに加えて閉じ込められて追い込まれた人間たちが、派閥に分かれて争う様子がリアルに描かれていて怖い。
それからアメリカ人にとってのサバイバルというのは銃と車がポイントなのだなと改めて思う。このふたつがないと物語が成り立たない。日本のホラーパニックとの大きな違いをうんでいる気がするなあ。
この映画はパニックものとして傑作。エンディングほかいくつか変更もあるものの進行は原作のとおりにつくられている。女教祖は映像の方が怖い。テキストでは想像力にまかされていた怪物をこれでもかとばかりに映像化しているVFXも素晴らしい。監督は『ショーシャンクの空に 』『グリーンマイル』のフランク・ダラボン。