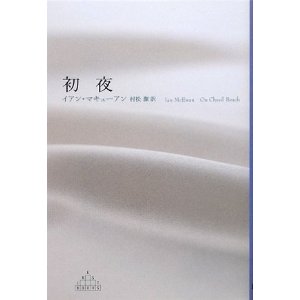Books-Fiction: 2010年9月アーカイブ
文体が面白くて一気読み。
「一九五六年三月十六日深夜、私は仮死状態で生まれました。産声を挙げたのは次の日の朝でした。しかしそういう言い方だけだと判らない事実が実は、そこに隠れていました。正確に言うと、───。 一九五六年三月十六日深夜ひとりの赤ん坊が生まれてすぐ死にました。その死体に私は宿りました。自分でも判らない衝動からです。というか神の御心のままに、そうしたのです。」
神憑り電波系中年女性による独白長編小説。
登場人物は"私"だけ。本当は人間ではなくて"金毘羅"なのに、人間世界に降りてきたせいで、幼少より生きづらい生を送ってきたことへの恨みつらみ、そして自分の真の霊的正体を知った時のカタルシスを延々と語る。そうした事実をを知ることがない世間の人々への高笑い。偶然や幻覚を神意と結び付けて、超恣意的な世界認識を構築して、その中にひきこもる女がいる。
熱っぽい一人語りの地の文が独特で、なんじゃこりゃあと思いつつも、よいテンポで序盤を読まされてしまう。
一見すると、現実の生きづらさからの逃避として、宗教知識を使った内面的な辻褄合わせをしているだけのようにも思える。金毘羅、象頭山、大国主、大物主、少彦名、サルタヒコ、アメノウズメ...少し歪曲されながら、日本のカミサマ論が延々と展開されている。その宗教知識の披露をよく読んでいくと、思いがけない深みにはまっていくのがこの作品の後半の魅力。
この本は、ある程度、日本の神道と仏教の歴史について予備知識を得てから読んだ方が面白い。そういう身勝手で恣意的な宗教意識が、実は日本人の伝統的な宗教意識そのものなのだということが見えてくる。土着の宗教と仏教を同一視する「神仏習合」や、日本のカミサマと仏の化身を対応させる「本地垂迹」など、身勝手な私の辻褄思考は、日本人の宗教思考とおもいっきり重なっている。
「我は神、我は幸い、その名は金毘羅、我執をも叶える、鰐と翼の神」
結局、この電波女は日本の宗教が必然的に生み出してしまうモンスターなのである。
第16回伊藤整文学賞受賞作品
詩人 茨木のり子の自選作品集全3巻が文庫化された。この第一巻には1950~60年代の詩、エッセイ、ラジオドラマ、童話、民話、評伝が収録されている。詩が書かれた背景を知ることができて、主な作品をだいたい読んだことがあるファンでも面白い(まあ、ファンしか買わないような本ではあるけれど)。
「第一詩集を出した頃」と「櫂小史」は24歳で詩を書きはじめて、27歳で川崎洋とともに同人誌「櫂」を立ち上げたころの回想エッセイだ。谷川俊太郎、岸田 衿子、川崎洋、吉野弘、大岡信など日本の現代詩の大物が登場する。
1950年~60年代ということもあって戦争による喪失をテーマにした作品も多い。「はたちが敗戦」の年齢。教科書に掲載されて有名になった「私が一番きれいだったとき」や「根府川の海」(最近の新聞でも取り上げられていた)が書かれたのがこの時期。茨木の凛とした態度は反戦詩に向いている。中国人強制連行体験者の実話をもとにした超長編詩「りゅうりぇんれんの物語」はドラマティック。他に「私のカメラ」「あほらしい唄」のような、らしくない甘い恋愛詩や、日本書紀の野見宿禰を題材にしたラジオドラマ「埴輪」、評伝「山之口 獏」など収録作品はバリエーションに富んでいる。
個人的には教育ということの本質を突いた詩「こどもたち」がベスト。「悪童たち」の「やさしい言葉で人を征服するのは なんてむつかしく しんどい仕事だろう」にもしびれた。
第2巻は1970年代~80年代。第3巻は90年代以降の作品を扱う。時代とともに作風がどう変わっていったか楽しみ。
・思索の淵にて―詩と哲学のデュオ
http://www.ringolab.com/note/daiya/2006/06/post-398.html
・詩のこころを読む
http://www.ringolab.com/note/daiya/2006/06/post-406.html
自分ほどわからないものはないよね、っていうアイディティティ融解パニック小説。
他人の携帯電話を手に入れたなりゆきで俺俺詐欺に手を染めた俺は、そこから俺がいっぱいいる俺俺の異世界へと引き込まれていく。我思うゆえに我ありというデカルトの言葉のように、自分の存在だけは疑わないのが人間の常だ。だが俺が複数存在しているというのもかなり困る。自我が崩壊するんじゃなくて自我が融合してしまうという、想像したこともなかった事態に陥って、俺は大いに焦る。
俺と同じ感性の俺は最高の仲間だが、自分と同じ思考をする人間が敵だったら最高に手ごわい。相手の次の手が読めそうで読めない。自分のことって、よくわかっているようで、わからないのだ。俺が増殖することで自分の持つ不条理性が果てしなく増幅されていく。
サスペンス小説なのかと思って読み始めたら、SF小説であり、パニックであり、ある種のホラーであり、パロディであり、究極の観念論なのであった。この本を読むまで、俺ということについて、ここまで突き詰めて具体的且つ網羅的に考えたことがなかった気がする。
娯楽小説に分類されそうだが根底にかなり深い哲学を読み取ることもできる中身の濃い作品である。就活なんかで"自分探し"をしている人はぜひ読むといい。自分を持たない自分が、自分を持つ自分を、自分の中に探すなんて、矛盾以外の何物でもないってわかるから。
喜劇のような悲劇、あるいは、悲劇のような喜劇。イアン。マーキュアン作。
「彼らは若く、教育もあったが、ふたりともこれについては、つまり新婚初夜については、なんの心得もなく、彼らが生きたこの時代には、セックスの悩みについて話し合うことなど不可能だった。いつの時代でも、それは簡単なことではないけれど、彼らはジョージアン様式のホテルの二階の小さな居間で、夕食のテーブルに着いたところだった。隣の部屋には、ひらいたドア越しに四柱式のベッドが見える。幅はやや狭めだが、ベッドカバーは純白で、しわひとつなくピンと張り、人の手で整えたとは思えないくらいだった。」
という出だしから始まる。
1962年、まだ保守の空気が濃厚だった英国で、ある夫婦の結婚初夜の事件について、ゆっくりと語られて、それだけで一冊が終わる。歴史学者志望の夫エドワードとバイオリニストの妻フローレンス。新潮クレストなので終始、上品で優美さは失わないのだけれど、あまりに深刻に童貞と処女の悩みが語られるものだから、吹き出しそうになる。
初体験であるがゆえの焦りや過剰反応のもたらす滑稽さ。それが二人の人生に致命的な結果をもたらしてしまう。若いときの深刻な決断って性に限らず、往々にして、はたから見たら滑稽なのだけれど、それが分かる頃にはもう若くない。青春のままならなさを描いた作品ともいえるわけですが。
純文学×恋愛×官能×喜劇×悲劇×歴史×... ユニークな作風が強く印象に残って、面白かった。ストレートじゃない独特な恋愛小説を読みたい人におすすめ。読みやすい。