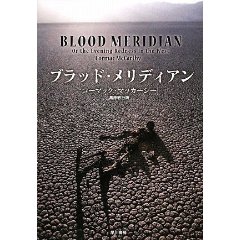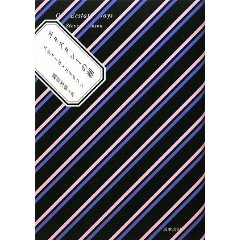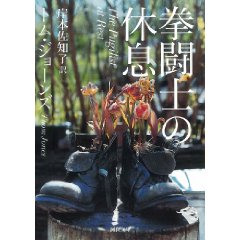Books-Fiction: 2010年2月アーカイブ
現代アメリカ文学の巨匠コーマック・マッカーシーの長編。
アメリカ開拓時代、インディアン討伐隊に加わった少年が体験する無法と殺戮の旅路。
インディアンを殺して持ち帰った頭皮の数だけ、町から報奨金をもらうという契約を結んだならず者たちは、インディアンを見つけ次第に惨殺しながら荒野を前進していく。力だけがすべてのような世界で、「判事」と呼ばれる2メートル超の巨漢の男は哲学や科学の知識で信望を集める。しかし同時に判事は冷酷な殺戮者でもあり、邪魔なものはインディアンでも仲間でも容赦なく消していく。
少年がたどる荒野の旅路という点では『ロード』と同じなのだけれど、同行するのが息子をどこまでも守ろうとする父親ではなく、怪物的な判事であるという点が違う。このどこの判事なのか定かでない通称の「判事」は、ヨーロッパ的な知性の化けの皮をはがしたようなものとして描かれている。
「倫理というのは強者から権利を奪い去る弱者を助けるために人類がでっちあげたものだ、と判事は言った。歴史の法則はつねに倫理規範を破る。倫理を重んじる世界観は究極的にはどんな試験によっても正しいとも間違っているとも証明できない。決闘に負けて死んだからといってその人間の世界観が間違っていたとみなされるわけではない。むしろ決闘という試行に参加したこと自体が新たな広い物の見方を変えが採用したことの根拠になる。」と判事は言う。
話せばわかるという前提ではなくて、話せば殺しあいになる世界で、勝ったからといって善とも悪ともいえないということ。「生か死か、何が存在しつづけ何が存在をやめるかという問題の前では正しいかどうかの問題など無力だ。この大きな選択に倫理、精神、自然に関する下位の問題はすべて従属しているんだ」と判事。世界の本質的などうにもならなさをむきだしにする衝撃作品。うなった。
・ザ・ロード
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/09/post-831.html
・ザ・ロード 映画
http://theroad-movie.com/
今年日本公開が決定している。
スティーブ・エリクソンの前衛世界文学の和訳最新刊。これまた大変な奇書である。
筋がよく分からなかったのに、強烈な印象を残して、いつまでも引きずる映画っていうのがある。たとえばデヴィッド・リンチ監督の『インラインドエンパイア』などかがまさにそうだ。現実と劇中で撮影中の映画の筋が錯綜し、何が現実なのかわからなくなっていく。精神錯乱状態で見る悪夢のような内容なのだが、映像の持つ強いイメージ喚起力は、トラウマの如く記憶に刻まれる。エクスタシーの湖もこれに似ていて、読者の脳裏にいつまでもこびりつくタイプのやっかいなビジョン小説だ。
ハリウッドの交差点にできた小さな水たまりが、次第に成長してロサンゼルス全域をのみこんでいく。謎の湖にゴンドラから飛び込んだ女は、湖底を突き抜けて向こう側の世界の湖面へ浮上する。湖に浮かぶ廃墟のような建物で、女はSMの女王として君臨する。前の世界にゴンドラに残してきた幼い息子のことを思いながら、名前と役割を転々とする数奇な人生を生きる。話の筋を追えなくなるほど話は混乱と錯綜を極めていく。
カオスな内容だけでなく、テキスト表現の前衛アプローチも見事に翻訳・再現されている。まず一目見てかなりおかしな本なのだ。水中に落ちていく女の物語は、一行のテキストとしてひたすらまっすぐ、何百ページもまたいで突き抜けていく。女の水中への落下と並行して、フォントとレイアウトを頻繁に変化させながら、錯綜した物語は進んでいく。どう読むべきかまず悩むところからとりかかる。表現の奇抜さと挑戦読書度はともにジェイムズ・ジョイス級。ちょっと気力体力いるのだが、とてつもない読書体験を保証できる。
私が読んだエリクソン本では「黒い時計の旅」や「ルビコンビーチ」の方がとっつきやすいが、ビジョンの強烈さははるかに「エクスタシーの湖」が強いと思った。最初にこれでもいいのかも。
死と隣り合わせのベトナム戦争の兵士、高額報酬と引き換えに危険な深海に潜る潜水士、ガンと戦う初老の女性、癲癇と記憶喪失でインドを放浪する男など、人生の苦難と戦う人たちの姿を描いた短編集。トム・ジョーンズ。表題作は93年にO・ヘンリー賞を受賞。日本では96年に新潮社から単行本で出版されていたものが、2009年9月に河出書房で文庫化。
虚しく終わる闘いだとわかっていながら、運命に抗いのたうちまわっていると、ふと見えてくる至高の境地みたいなもの。アドレナリンが沸騰して感覚が限界を超越する"紫の領域"の戦士。長距離ランナーが感じるという苦しさの末の至福でハイな状態みたいなものを描く作品が多い。暗い話なのにどこかに明るさを残す。
著者の経歴は相当にユニーク。アマチュアボクサーとして150以上の試合に出場し、海兵隊に入隊するが、ボクシングで負った傷がもとで側頭葉てんかんを患い除隊、大学の創作科に学ぶが小説家としては売れず、用務員の仕事をして暮らす。糖尿病、アル中、薬物依存に10年間苦しんだ。あるとき、2万5千通に3編しか採用されないといわれる『ニューヨーカー』誌に掲載が決まって、突如売れ始めた。この本に収録された10編には10人の、性別も年齢も職業も異なる、いろいろな境遇の主人公が登場するが、おそらくすべてに著者の経験が反映されている。だから濃い。
ショーペンハウアーの言葉が何度も引用される。一般にペシミストで皮肉屋に分類されがちなショーペンハウアーだが、この作品の文脈では、その言葉が希望であり真理のように響く。
「若き日に、来るべき未来に思いを馳せるとき、我々はさながら開幕前の劇場に座り、カーテンが上がるのを胸ときめかせて待っている子供である。待ち受けている現実を知らずにいることは、我々にとっては幸いである」(ショーペンハウアー)。
・読書について
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/01/post-913.html