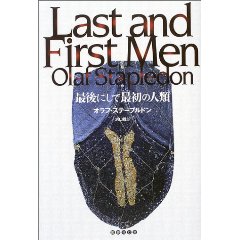Books-Fiction: 2010年1月アーカイブ
・小説 ファイナルファンタジーXIII エピソード0 -約束-

大ヒット中のPS3のRPGゲーム ファイナルファンタジー13の書きおろし小説。
FF13はストーリーが第1章、第2章...と小説のように区切られているが、この小説エピソードゼロが描くのは第1章以前の世界。だからこの小説のエピローグはゲームのプロローグに当たる。主要登場人物たちはまだ出会っておらず、共通の"使命"も帯びていない。多くの登場人物たちは最初は平和にそれぞれの人生を生きている。
FF13の開発は、まず舞台となる世界の神話体系を創造することから始まったそうで、厚みのある世界観が確立されている。同じ神話が関連作品としてリリース予定の『アギト』と『ヴェルサス』も共有するそうだ。ゲーム内でも、ストーリーが進行するのに従って、背景情報がテキストで明かされていくのだが、あれだけ膨大な情報をテレビ画面で読むのは面倒だ。登場人物たちの背景だけでなく、モンスターや小物(武器やアクセサリー)、コクーンとパルスについても詳しく書かれている。だから、この小説を読むとプレイ中に曖昧だった部分がすんなりと入ってくるようになる。
私の場合はゲームが第11章まで進んだところで、この小説を読んだが、本編ストーリーの楽しみを損なうようなネタバレはなかった。むしろ、本編ストーリーに深みを与える部分が多い。小説ではモンスターの容姿はわかりにくいので、ゲームをちょっとやってから読むとイメージがわきやすい。結論としては、ゲームと同時進行で読むのがおすすめ。それでゲーム進行が有利になるということは、まったくないのだが。
ノベライズ作品というと文章が低レベルなものも多いのだが、この作品は筆力のある作家がちゃんと書いているため、結構長いのだけれども、飽きずに楽しく読めた。ひとつだけ不満をあげるとすれば、ゲーム内のヴァニラの能天気なブリッコキャラクターは、小説では再現されていないように思えた。ゲームでも浮いているわけだから、まあ、しょうがないのか。
・新春ポッドキャスト 「ツイてる!ポッドキャスト新春2010」3日目 と ファイナルファンタジーXIII
http://www.ringolab.com/note/daiya/2010/01/2010xiii.html
世界で1000万部を突破したベストセラー。
自閉症の秀才の視点で書かれたという設定のミステリ風小説。主人公のクリストファーは養護学校に通う自閉症児。他者の感情を読み取ることができず、対人プレッシャーがかかるとすぐパニックを起こしてしまう。その一方で数学の能力は飛びぬけていて、もうすぐ大学レベルの上級試験を受けようとしている。
母親は亡くなっており、面倒を見てくれる父親と二人で、閉じられた世界の中で静かに暮らしていた。ある日、隣の家の犬が何者かによって殺されるという事件が起きる。クリストファーはその第一発見者になるが、説明が誤解されて犯人扱いされてしまう。調べに来た警官を殴って警察へ連行されてしまう。
濡れ衣を晴らすというよりも、事件という難解なパズルを解くことに興味を覚えるクリストファーは、犬殺しの犯人を捜すべく、自ら近隣の聞き込みを始めることにした。その捜査はまたトラブルを招き、多くの騒動を巻き起こすが、やがて意外な真実を明らかにする。
健常者は他人が笑ったり、涙を流していれば、直感的に相手の感情を感じることができる。しかし、自閉症の患者は、その表情や態度を客観的にデータとして分析しないと、他人の心理が理解できない。ああ、この人は大きな声を出しているから怒っているのだ、とか、眉毛を上げたということは気に入らないという合図だとか、論理的に感情を推測する必要がある。
すべてが終わった後に事件を振り返って、劇中の主人公のクリストファーが書いた小説ということになっているが、本当は自閉症児とのつきあいが深かった著者が書いたフィクションである。その観察に基づいて不自由な他者認識を完全シミュレートしたのがこの作品なのだ。マイノリティの世界認識では世の中すべてが奇妙なミステリみたいなものだということがよくわかる。
橋本治の小説。
「自分のしていることが無意味でもあるのかもしれないということを、どこかで忠市は理解していた。しかし、その理解を認めてしまったら、一切が瓦解してしまう。遠い以前から、自分の存在は無意味になっていて、無意味になっている自分が必死になって足掻いている─その足掻きを誰からも助けてもらえない。絶望とはただ、誰ともつながらず、誰からも助けられず、ただ独りで無意味の中に足掻く、その苦しさ。」
近隣住民との対話を頑なに拒否するゴミ屋敷の主人の屈折した半生をたどる。
テレビのワイドショーを見ていると、この作品の登場人物のようなゴミ屋敷の老人や、騒音をまき散らすおばさんがテーマになっていることがある。レポーターは本人を追い回すが、ほとんどの場合、意味不明なコメントしか取れない。テレビ的にはそれでいいみたいだ。その奇行に込み入った事情があるより、話が通じず、怒鳴り散らす老人というのが困った問題を象徴していて、絵的にはわかりやすいから。
この作品、戦後を生真面目に生きてきた男のなれの果てがゴミ屋敷の主という、やりきれない話なのだが、テレビと違って、そこには深い事情があるのだということがわかって、すっきりとする。おそらく現実のゴミ屋敷の一つ一つにだって、相当に深いドラマがあるのだろう。それをわかりやすさ追究のテレビ映像では表現できないだけなのだ。
大多数の人間にとっては高度成長と繁栄の時代だった昭和をうまく生きられなかった男の哀しい精神史。興味本位で読ませる出だしと、悲喜こもごもの男の半世紀、しみじみとして泣かせるラスト。とてもよく構成された上質な小説。いいものを読んだ。
ところで一軒家の持ち家を維持できた昭和の狂人は恵まれていたよなあと思う。平成のゴミ屋敷はバーチャルかもしれませんね。私も老後にゴミブログにならないように気をつけよう...。
年始にふさわしい壮大な話を読もうと思って今年はこれにした。
オラフ・ステープルドンの人類20億年未来史。素晴らしい。うっとりした。
20億年後の最後の人類(第18期人類)が、遠い昔の最初の人類である我々に語りかける形式で書かれている。現代の人類はこれから1千万年くらい生きた後に絶滅して、さらに進化した第2期人類の時代に入る。
火星人との接触の記述には思わずうなった。これほど現実的にファーストコンタクトを想像した作家が20世紀初期にいたなんて驚きだ。あまりに異なる生命(空を漂うアメーバのような生物)の様式を持った火星人と地球人は、お互いの高度な知性を認識することができない。その数億年先では第5期人類が別の星の知性と出会うが、このときにも相互理解に失敗する。
最後の人類は振り返ってこう語っている。「しかしこの議論はクラゲや微生物にもあてはまるだろう。入手できる証拠をもとに判断が下されねばならなかった。どのみち人間がその問題に判断を下しうる限り、人間がより高次の存在であるのは間違いなかったのである。」。結局、判断基準を設定するものが高次なのだ。
人類と火星人は相互理解には失敗するものの、第一期人類の細胞に入り込んだミトコンドリア(太古には別の生命体だったといわれる)との関係に似た共生関係に入り、共進化を進めていく。しかしそれもたかたか数千万年の間の人類史の初期の出来事。すべてが終わったところから眺めると、第一期と第二期人類などはさして重要な存在ではなかった。
やがて人類は地球を捨てて宇宙へと飛翔する。自らの種を改造して新しい形態に進化していく。私利私欲を制御して高い精神性を持った人類の時代が訪れる。それでも惑星レベルの危機は数億年単位でやってきて、人類の歴史は思わぬ方向へと展開していく。
すべてが地質学的年代のスケールで描かれるため、この長大な物語に名前を持った登場人物は一人もいない。固有名詞もほぼ出てこない(最初の数章には国名がいくつか出てくるが)。世紀の大事件も20億年の大河においては一滴の水に過ぎない。人類史を大きく変えた大発明も、結局は遠からず誰かがそのうち見つけるのだから、誰が見つけたというのはあまり意味がない話になる。
グーグルアースで自分の自宅近辺の地図から、市や県、国、地域、そして地球、宇宙と表示を拡大していくと、自分の見えている空間はなんてちっぽけなんだろうと思ったりするが、この本は、その遠近スケール体験を極限的に味わうツールである。
ステープルドンが代表作となるこの作品を書いたのは1930年のこと。「エーテル」のように科学的な誤りだとか、実際にはそうはならなかった20世紀の歴史予測が含まれるが、話のスケールがあまりに大きいため、そんな多少の間違いは歴史の流れにまったく関係がない。重要なのは人類の普遍的な性質と宇宙レベルの年代スケールである。想像力の限界に挑んだ歴史的な奇書。
・スターメイカー
http://www.ringolab.com/note/daiya/2006/10/post-470.html
『最後にして最初の人類』の次は宇宙の最後を五千億年のスケールで描くステープルドンの究極「スターメイカー」をおすすめ。
この小説は傑作なのだが、外山恒一の都知事選の政見放送も今思い返しても傑作だった。
・東京都知事候補 外山恒一 政権放送
「諸君。私は諸君を軽蔑している。
このくだらない国を、そのシステムを、支えてきたのは諸君に他ならないからだ。
正確に言えば、諸君の中の多数派は私の敵だ!
私は、諸君の中の少数派に呼びかけている。
少数派の諸君。今こそ団結し、立ち上がらなければならない。
奴ら多数派はやりたい放題だ!
我々少数派が、いよいよもって生きにくい世の中が作られようとしている!
少数派の諸君。選挙で何かが変わると思ったら大間違いだ!
しょせん選挙なんか、多数派のお祭りにすぎない!
我々少数派にとって、選挙ほどばかばかしいものはない!
多数決で決めれば、多数派が勝つに決まってるじゃないか!」
外山氏の言う多数派というのがマインド的にはこの作品の中の「増大派」に近い。勝ち目がない外山恒一氏は「減少派」の典型サンプルだ。私はつねづね人間は100%、イヌ(タヌキ)系、ネコ(キツネ)系に弁別できるなあと思っていたのだが、増大派と減少派に分けることも可能なのだな。
主人公の少年は片目をつぶって、つぶったほうの目の闇を、見えている目の光景に重ね合わせる。そういう見方で周りの人間を見て、闇が深く見える人は増大派、薄い人は減少派だ。団地に棲みつく妄想凶ホームレスと、父親の暴力に追い込まれた少年の二人の減少派同士の危うい関係が、やがて最悪な感じのカタストロフィーを呼び込んでしまう。
悲壮な話なんだけれど、なんだかふきだしてしまう。自分は減少派だと思っている人にはそんなふうに苦面白い小説である。というか、これを読んで面白いと思う人が減少派なのだ。増大派減少派の診断ツールでもある。
日本ファンタジーのベル大賞受賞