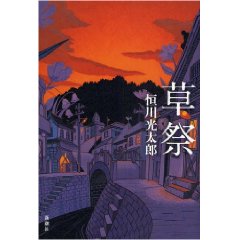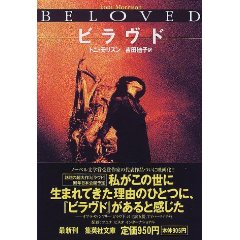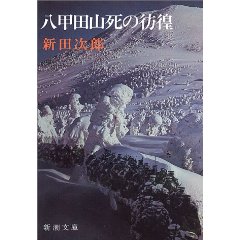Books-Fiction: 2008年12月アーカイブ
現代世界文学の最先端をいくリチャード・パワーズの最新邦訳。上下巻で千ページを超える大傑作。ニューヨークタイムズ紙(2006年度)、シカゴ・トリビューン紙ほか世界のメディアで年間ベスト作品に選ばれている話題作。年末年始の連休読書におすすめ。
20世紀前半、人種差別の激しいアメリカで黒人歌手のディーリアとユダヤ系ドイツ人で亡命物理学者のデイヴィッドが恋に落ち、二人の間には3人の混血児が誕生した。家族は歌を愛し毎晩のように楽曲をごちゃまぜにして合唱する遊び「クレージー引用合戦」を楽しんだ。外の世界には差別と迫害の嵐が吹き荒れていたが、家族は家の中で多声が調和する音楽の世界に浸って厳しい現実をやり過ごす日々。
だが音楽が家族をひとつに結びつけていた幸せな時間はあっという間に過ぎ去っていった。やがて両親の与えた英才教育によって才能を開花させた色白の長男ジョナは天才的なテノール声楽家として世界に羽ばたいていく。次男の「私」には平凡な才能しかなかったが共に音楽の道に進み伴奏者としてピアノを弾くようになる。妹のルースは白人的な文化に激しく反発して黒人過激派運動に身を投じていく。黒人でもなく白人でもない子供達は自らのアイデンティティーと居場所を求めて長い旅に出ることになる。
ディーリアとデイヴィッドの時代と"私"の時代が対位法のように交互に語られる。人種問題、音楽、時間の3つの主題が通奏低音として終始響いている。黒人とユダヤ人の混血家族が黒人と白人、敵と味方という二元論の時代をなんとか生き延び、孫達の世代がハイブリッドでポリフォニックな未来を予感するまでの家系の歴史である。
バロック音楽、オペラ、ゴスペル、ブルース、ジャズ、ヒップホップなどあらゆる音楽がそれぞれの時代や登場人物の人生を彩る。音はジャンルの垣根を越えて次第に混ざり合って、新たな時代の音楽を生み出していく。現実世界でも混血の大統領が誕生しようとしているアメリカの姿を、音楽をモチーフに描いているのだとも言える。
この作品は文学的であると同時に娯楽性もある読み物として最高レベル。ずっしりとした文学作品を読み切った充実の読後感がある。2008年の翻訳物としてベスト。なおこの物語は前奏的な上巻の後、下巻で激動の時代に突入し本格的に動き始める。長いが必ず最後まで読み通す価値のある傑作である。
「夜市」「雷の季節の終わりに」「秋の牢獄」と異界物の傑作を書き続けてきた恒川光太郎の最新刊。今回もクラシックな湿り気のある妖怪譚と、モダンな平行世界のアイデアが絶妙にブレンドされた恒川ワールドが読者を引き込む。どこか懐かしい感じのする不思議な町、美奥町を舞台にした連作。
「けものはら」
中学3年の夏、雄也は行方不明になった友達の春を探して心当たりのある場所へと向かった。そこはかつて二人で一度だけ迷い込んだことのある団地の奥の用水路の先の、誰も知らない野原だった。果たして春はそこにいたのだけれど何か様子がおかしくて...。
「屋根猩猩」
夜になると瓦屋根の上を屋根猩猩が通り過ぎていく。猩猩は町の守り神で屋根の上で宴会をして、人間と取引をしに降りてくることもあるという。ある日私は上からひらりと降りてきた不思議な少年と仲良くなった。
「くさのゆめがたり」
「オロチバナはヤマタノオロチが血を流したところに咲くといわれる花だ。どこにでもあるものではないし、五感のみで生きている者は通りがかっても視えぬ。禁断の神薬、クサナギを作るのに使うという」
「天化の宿」
「<天化>のルールについて言葉で完全に説明することは困難です。<天化>は、カードと苦解き盤がセットで一つの世界を作っており、麻雀牌を一度も見たことがない人間に、役の説明をするのが困難なのと同じです」。
「朝の朧町」
トロッコ列車に乗ってひとり美奥町にやってきた加奈江には誰にも言えない暗い過去があった。彼女は知り合いの長船さんに連れられて、ぼんやりと靄がかかった町にはいっていった。
今回は過去の作品でいうならばデビュー作「夜市」や「風の古道」に近いかなと思った。「のらぬら」とか「クサナギ」など最初は名前だけ登場して、なんだかよくわからない魑魅魍魎や怪奇現象が、繰り返し登場するうちになじみ深い世界観の一部になってくるのが連作の面白さであり、読み終わるのが惜しい作品集となっている。
・秋の牢獄
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/07/post-776.html
・雷の季節の終わりに
http://www.ringolab.com/note/daiya/2006/11/post-489.html
93年度ノーベル文学賞受賞作家トニ・モリスンの代表作。南北戦争の頃のアメリカで、白人によってすべてを奪われた黒人奴隷達の魂の苦悩を幻想的に描く物語。
わたしは、わたしの民でなかったものを、わたしの民と呼び、愛されなかった者を、愛されし者と呼ぶだろう (ローマ人の手紙 第九章二十五節)
逃亡奴隷のセサは絶望の中で殺した実の娘の墓碑に「Beloved(愛されし者)」と刻印した。だが殺された赤ん坊の恨みは収まらず、セサの家に取り憑いて家族を悩ませた。長い時間が経過し残った家族も悲惨な状態で離散していった。寂しい生活を送るセサと末娘の前に忽然と「ビラヴド」と名乗る正体不明の女が現れた。彼女は本当にあの世から生き返ったあの娘なのだろうか。セサは過去の償いをするようにビラヴドを溺愛し始める。
ノーベル文学賞作家として初の黒人女性トニ・モリスンは、この小説を6千万人の祖先達に捧げている。ビラヴドは愛されず死んでいったものたちの象徴であり、忘れ去れていたものたちの怨念が実体化したものだ。
物語の中で何度か繰り返される「人から人へ伝える物語ではなかった」というフレーズが印象的だった。あまりにも悪意に満ちていて残酷な過去は、セサにとって忘れたいものであると同時に語りたいものでもある。その深い葛藤が炎となって燃え上がり、すべてを焼き尽くしていくような、激烈で悲しい物語。かつての黒人奴隷に限らず差別や虐待、愛の不在を普遍的に描いているように思った。
不覚にも100万部売れてから読んだ。これ傑作ではないか。
なぜ今までこの本を読まなかったのかといえば、作者の水野さんを知っていたからだ。
私の記憶では、4年以上前、彼は持っている服を全部浜辺で燃やして全裸で海に浸かりながら「リボーン」と叫ぶ"ミズノンノ"であり、竹刀を片手に性愛を語る熱血教師水野愛也だった。何度か私と田口さんが主宰するイベントにきてしゃべってもらったことがあった。
・2004年05月21日 おしゃれ会議 満員御礼に感謝 報告第1弾
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/001557.html
「ミズノンノって誰?という方は勉強が足りません。あのミズノンノです。上のURLで確認してください。まあ、そういう事情で、持っている服をすべて燃やしてしまい、過去の手持ち服にとらわれないファッションの達人になると宣言しリボーン!した彼なので、今日も服がないのでジャージで登場。なにか叫んでいたのですが、すいません、覚えてません。彼自身がエンタテイメントなので、何か叫んでいたで十分でしょう。言葉を超えています。事情を知っている人は大爆笑、知らない人はあっけにとられて口をポカーンとされていました。成功です。彼はすでにベストセラー作家なのですが(ついでに言うと慶応出のインテリのはずなのですが)、おしゃる技術でリボーンして新たな前人未到の世界を切り拓こうとしています。今年後半で、もしかするとメディアで大ブレイク、来年の今頃は雲の上の人である可能性ありで、無敵会議実行委員会としては、彼に賭けており、その行く末を今後も見守らせていただこうっていうか次回も出てください、と思っております。」
このミズノンノが夢をかなえるゾウの作者の水野敬也氏である。4年ほど経ってミリオンセラー作家、本当に「雲の上の人」になってしまった。私はうっかり年下の変人が書いた自己啓発本だからということで、不覚にも昨日まで読まなかったのであった。
自分を変えたい"僕"の前に突然現れたぐうたらなゾウの神様ガネーシャは、自分を変えるための課題を毎日一つ出してくる。課題の中身は「靴を磨く」「募金する」「人を喜ばせる」など誰にでもできる当たり前の内容ばかり、本当にこんな神様の言うことで自分を変えることができるのだろうか?。半信半疑に思いながら部屋に居着いたガネーシャと奇妙な共同生活を始めるというストーリー。
僕とガネーシャのコントのような軽妙なやりとりの中で、現代人の人間心理の深く分析する記述が次々に出てきて驚かされる。なぜ自分はなかなか変えられないのかというところから始まって、変わるとはどういうことなのか、そもそも変わることに意味があるのか、という根源的な問いかけにまでおりていく。成功哲学本にありがちな成功者の嫌らしさがなくて万人が受け入れやすい内容になっている。万人というか100万人が読んだわけだが。
というわけで万人におすすめ。
ド迫力。
日露戦争前夜の1902年に起きた八甲田雪中行軍遭難事件を題材にした新田次郎の小説。映画化もされた。日本陸軍の冬季訓練中に参加者210人のうち199人が死亡した日本の登山史上で最悪の遭難事件である。
真冬の八甲田山は地元民でさえ怖がって立ち入らない地域であったが、帝国陸軍は対ロシア戦に備えてこの厳寒の山での長距離行軍訓練を行うことを決定する。ふたつの聯隊が選ばれて同じ日程で逆の行路を行くことになった。事実上の競争である。
「この雪中行軍が死の行軍になるか、輝かしい凱旋になるかは、この行軍に加わる人によって決ります。雪地獄の中で一人の落伍者が出ればこれを救うために十人の落伍者が出、十人の落伍者を助けるために小隊は全滅するでしょう。雪地獄とはそういうものです」
出発前より指揮官らは人間や組織が重要だと気がついてはいたが聯隊間の競争意識で目が曇った。面子を賭け大部隊での行軍を選んだ第31聯隊は、指揮系統の混乱により悲惨な壊滅状態へと陥っていく。上官らの判断ミスに兵卒が服従することによって状況をみるみるうちに悪化させてしまう。ピラミッド型の命令系統を持つ組織の致命的な問題点を浮かび上がらせた。
現実の八甲田山の遭難での階級別の生存者率は以下の通りだった。服従した兵卒達が圧倒的に高い割合で死んでいる。
准士官以上(16人)の生存者数 5人に1人
下士官(38人)の生存者数 13人に1人
兵卒(156人)の生存者の割合 31人に1人
真冬の八甲田山も怖ろしいが、200人の大部分を殺したのは明らかに人間の組織であったように思える。そして、こうした組織的な判断による破滅は、現代の企業組織にもよく見られるように思う。リーダーが読むべき失敗学の参考書として経営者にもおすすめ。