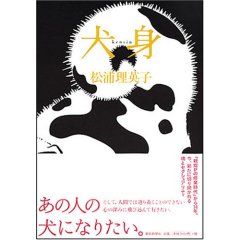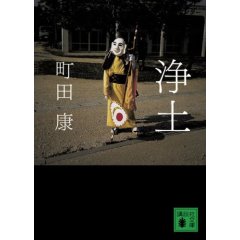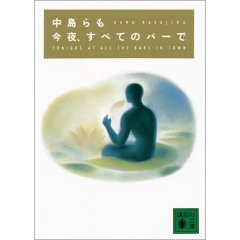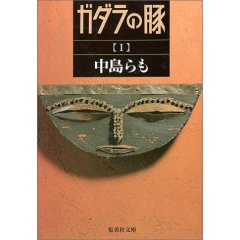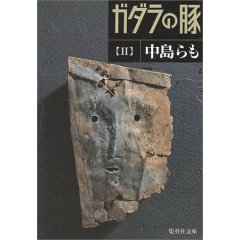Books-Fiction: 2008年6月アーカイブ
「親指Pの修行時代」の松浦理恵、2008年度読売文学賞受賞作。
この本は話題になっていたから買ったのだけれど半年くらい床に積んでいた。帯に「あの人の犬になりたい」、背表紙(帯)には「さまよえる犬の魂」と書いてある。つまりSM系と獣系の複合官能小説だろうか?と思ったが、読売文学賞?いまひとつ中身が想像できない上に500ページもあるので、先週まで手つかずになっていた。ところが読み始めたら止まらなかった。もっと早く読めば良かったと後悔。
主人公の房江は強い「犬化願望」を持っている30代の女性陶芸家。本来自分は犬に生まれてくるべきだったのにと感じながら人生を生きている。
「性同一性障害ってあるじゃない?『障害』っていうか、体の示す性別と心の性別が一致していないっていうセクシュアリティね。それと似てるのかな。わたしは種同一性障害なんだと思う。」
「こういうわたしにセクシュアリティというものがあるとしたら、それはホモセクシュアルでもヘテロセクシュアルでもない、これは今自分でつくったことばだけど、ドッグセクシュアルとでも言うべきなんじゃないかと思う。」
こんな房江がある日、本当に犬になってしまう。人が犬になってしまうというのはどういうことかというと、それはネタばれになるので読んでいただくとして、房江は残りの人生を犬生として犬の視点で生きる。愛する飼い主との触れあう幸せに浸りつつ、飼い主を取り巻く複雑な人間模様を足下から見守る。
前半の犬と人間の幸せな相互依存をユーモラスに語っている部分は犬好きにはたまらない魅力。そして登場する人間同士の不幸な相互依存は次第に緊張度を強めていき後半に波乱のドラマを引き起こす。常に身近に寄り添う犬はすべての目撃者になる。
吾輩は猫である、とか、高みの見物(北杜夫、ゴキブリが主役の傑作)とか、人間と共生関係にある生き物視点で人間模様を語る小説は昔からあるのだけれど、だいたいはナレーターのような客観的語り部として生き物が出ていた。この作品では語り手自身が元人間であるが故に、登場人物たちに深く共感しながら物語に参加していく。これはやはり人と相互依存しやすい犬だから成り立つ設定だったろう。
・電子書籍 『犬身 第一回』松浦 理英子|Timebook Town
http://www.timebooktown.jp/Service/bookinfo.asp?cont_id=CBJPPL1B0046100S
この小説は初出が電子書籍だ。一流の作家が電子書籍で出版して文学賞を受賞するというのは文学のIT化が着実にするんでいるということだなあ。
文庫化されたタイミングで読書。天才町田康の短編集、読者の心をつかみ、ゆさぶり、首しめるような全7編。
とりわけ「どぶさらえ」が最高。
「先ほどから、「ビバ!カッパ!」という文言が気に入って、家の中をぐるぐる歩きまわりながら「ビバ!カッパ!」「ビバ!カッパ!」と叫んでいる。 なぜ気に入ったかというと、単純に「ビバ!カッパ!」という音の響きが連なりが気に入ったからだけれども、ただそれだけならこんなに何度も言わせない。せいぜい水道水をカップに入れ、ぐいと飲み干したる後、「ビバ!カッパ!」と一声叫んでそれで終わりだろう、それをばこうして何度も何度も言うというのは、そのビバ、カッパ。という文章に明確なビジョンが伴っているからである。」という出だしで始まる怨念の小説。
この感覚、実によくわかるのだ。この現象は私にもときどき起こるから。私の場合「寒山拾得」「六根清浄」「十返舎一九」など小さな「っ」が入って且つ古くさい感じの言葉が一度心に浮かんでくると、リフレインが止まらなくなってしまうことがある。この言葉は意味なんだっけと思いながら何百回も唱えることになる。こういうの、結構一般的な現象なのだろうか?。
この作品でも町田康が捕まっているのは「っ」が入っているフレーズなのだった。尊敬する作家と共通点が見つかって単純にうれしくなってしまう。だが作家が凄いのはそうした困った現象をも表現技法に取り入れることだ。「どぶさらい」では、頭の中をぐるぐるまわる言葉が、渦を巻いて大きくなって、主人公を駆り立て、やがて外の世界に飛び出していく。いつもの町田節が冒頭から炸裂している。
それから「どぶさらい」と並んで「あぱぱ踊り」も傑作だと思う。社会に生きていると、こいつは正座させて小一時間問い詰めたい奴すなわちトンデモ勘違い野郎がいるものだが、そういう「俺様」をムキになって徹底的に追い詰めていく。その追い詰めプロセスを楽しむ独特の娯楽作品である。かなり笑えた。
最初から最後までいつもの如く人を喰った作風。解説で松岡正剛氏が指摘しているように、そもそも「浄土」というタイトルの作品が収録されていないし、その説明もない。たぶん、町田康は確信犯的に、説明しない効果を狙ってニヤニヤしているのだろうなあと思うと悔しいけれども、本は面白かった。
・悪人
http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/07/post-603.html
・告白
http://www.ringolab.com/note/daiya/2006/10/post-474.html
・フォトグラフール
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/04/post-745.html
・土間の四十八滝
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/04/post-733.html
中島らも、1990年発表、吉川英治文学新人賞受賞作。35歳のときの深刻なアルコール依存症による入院体験を小説に書いたわけだが、らも氏はその14年後に酔っぱらって階段から落ちて死んでしまった。お酒を愛し追究しそして翻弄された作家の、本物アル中フィクション。
「退屈がないところにアルコールがはいり込むすき間はない。アルコールは空白の時間を嗅ぎ当てると迷わずそこにすべり込んでくる。あるいは創造的な仕事にもはいり込みやすい。創造的な仕事では、時間の流れの中に「序破急」あるいは「起承転結」といった、質の違い、密度の違いがある。イマジネイションの到来を七転八倒しながら待ち焦がれているとき、アルコールは、援助を申し出る才能あふれる友人のようなふりをして近づいてくる。事実、適度のアルコールを摂取して柔らかくなった脳が、論理の枠を踏みはずした奇想を生むことはよくある。」
クリエイティブな業績があるアーティストは、お酒もクスリも創造性の源としてしばしば引き合いに出される。だが、飲まないで面白いものを書く人もいるわけだから言訳に過ぎないと言える。だから、要は作家としていかにかっこよくそれを言うかだろう。自堕落でかっこよい言訳の小説なのだ、これは。
「「教養」のない人間には酒を飲むことくらいしか残されていない。「教養」とは学歴のことではなく、「一人で時間をつぶせる能力」のことでもある。」
底なし沼の「ズブズブ」感がたまらない小説である。冷静にアルコール依存症という病気を分析している部分もあるのに、気を抜くとやっぱり飲んでいる。わかっちゃいるけどやめられないまま、また飲む言訳を探す。これはアルコールに限らない。依存する人間の弱さと怖さが魅力の入院小説。
・ガダラの豚
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/06/post-762.html
昭和30年 第32回の芥川賞を受賞した庄野潤三の初期代表作を含む短編集。
夕食前にプールで泳ぎ、大きな白い犬と一緒にマイホームへ帰っていく家族。絵に描いたような幸せそうな家族だが、実態は経済的にも愛情的にも、破滅の秒読みが始まっているのだった。「プールサイド小景」はモーレツに日本人が働いていた時期に書かれた作品だ。置き去りにされた妻はこんな風につぶやく。
「男は退屈すると、棍棒を手にして外へ出て行き、野獣を見つけると走って行って躍りかかり、格闘してこれを倒す。そいつを背中に引っかついで帰って来て、火の上に吊す。女子供はその火の廻りに寄って来て、それが焼けるのを待つ。もしそういう風な生活が出来るのだったら、その方がずっといいに決まっている。男が毎朝背広に着替えて電車に乗って遠い勤め先まで出かけて行き、夜になるとすっかり消耗して不機嫌な顔をして戻ってくるという生活様式が、そもそも不幸のもとではないだろうか。彼女は、そんなことを考えるようになった。」
労働というものが家庭と完全に切り離されて、ワークライフバランスの問題の原点をみるような気がした。今は女性も働くが、仕事と家庭の両立の難しさは、昭和も平成も本質的には変わっていないような気がする。
収録一作目の「舞踏」は、夫の浮気に気がつきながら、それを夫に言い出すことができないでいる妻との微妙な関係を描いた秀作。冒頭の語り部分からひきこまれる。
「家庭の危機というものは、台所の天窓にへばりついている守宮のようなものだ。それは何時からと云うことなしに、そこにいる。その姿は不吉で油断がならない。しかし、それはあたかも家屋の内部の調度品の一つであるかの如くそこにいるので、つい人々はその存在に馴れてしまう。それに、誰だってイヤなものは見ないでいようとするものだ。」
登場人物の主観の文と、客観的視点の文が入り交じる「二元描写」の技法が、ストーリーを立体化するのが特徴。ドキュメンタリ番組のように頭の中に物語が映像化される感覚がある。
男と女、仕事と家庭、ささやかな幸せというのは微妙なバランスの上で成り立っていて、均衡が崩れると、いっきに奈落に暗転するかもしれない。日常というのは緩いようでいながら、実は張り詰めているんだということを書くのがうまい作家だと思った。
「アフリカにおける呪術医の研究でみごとな業績を示す民族学学者・大生部多一郎はテレビの人気タレント教授。彼の著書「呪術パワー・念で殺す」は超能力ブームにのってベストセラーになった。8年前に調査地の東アフリカで長女の志織が気球から落ちて死んで以来、大生部はアル中に。妻の逸美は神経を病み、奇跡が売りの新興宗教にのめり込む。大生部は奇術師のミラクルと共に逸美の奪還を企てるが...。超能力・占い・宗教。現代の闇を抉る物語。まじりけなしの大エンターテイメント。日本推理作家協会賞受賞作。」
中島らもの大傑作小説。圧倒的に凄いものを読んだ感じがする。
中島らもといえば1984年から10年間も朝日新聞に連載された「明るい悩み相談室」が有名だ。本人には深刻だが一般的にはどうでもよい悩みの相談に対して、親身に相談に乗りながら、いつのまにやら常識とズレた落とし所に話を持ていって、読むものを笑わせるという内容。コピーライターとして活躍したこともある中島らもの明るい表の顔であった。
一方で、中島らもは、作家でロックアーティストで劇団主宰というエッジの立った表現者であり、学生の頃からひたすらに放蕩人生を生きた。アル中であり、フリーセックス、フリードラッグを地でいった。そして晩年は大麻で逮捕投獄された揚句に、泥酔して飲み屋の階段から落ちて死んでしまった享年52歳。世の中の光も闇も知り尽くした芸術家であった。
ガダラの豚は冷静に物語の全体構造を設計する表のらもと、人間の心の闇を知り尽くした裏のらもが、総力をあげて作り上げた大作だ。娯楽作品であると同時に深い闇がある。
主人公は大槻教授と吉村教授を足して2で割ったような、超常現象をテレビで否定する役割をこなしながら、呪術のフィールドワークを行う大学教授である。超能力者や似非教祖らとの激しい論争の中で、だましのからくりを次々に暴いていく。第1部は実際の事件や人物がモチーフになっていて、ぐいぐいひきこまれる。
第2部では教授たちはテレビ番組制作のために、調査チームを結成してアフリカへフィールドワークの旅にでかける。そこで遂に、教授にも正体が暴けない強力な呪術が登場する。人が人を呪い殺す魔術は本物なのか偽物なのか。やがて旅の一行は死の呪いとの決死の戦いを余儀なくされる。
ガダラの豚は大傑作と呼ぶべき代表作だが、第3部で突然ドタバタ劇になってしまうのは少し残念だ。映像化しやすい娯楽作品として完結させようとしたのだろうか。第1部と第2部のような、じわじわと迫りくる凄みが第3部にはない。スピーディーなハリウッド映画のような、わかりやすくて派手なエンディングで物語は幕を引く。評論家の間でも、第3部については賛否両論があるようだ。
しかし、作品全体としては100点満点で、
第1巻 120点
第2巻 120点
第3巻 60点
という感想で、全体としては満点である。フレーザーの呪術研究あたりに興味のある人には絶対的におすすめである。読まないと損である。
・図説 金枝篇
http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/05/post-563.html
・中島らも オフィシャルサイト
http://www.ramo-nakajima.com/top.html