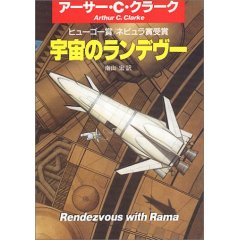Books-Fiction: 2007年5月アーカイブ
宇宙のランデヴー 続編
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004864.html
「西暦2130年、忽然と太陽系に現われた謎の飛行物体―ラーマと名づけられたこの物体は巨大な宇宙船と判明した。内部への侵入に成功した調査隊の必死の努力にもかかわらず、この異星人の構築物は人類の理解をはるかに超え、多くの謎を残したまま太陽系を去っていった。それから70年後、第2のラーマが太陽系に姿を現わしたが…名作『宇宙のランデヴー』で解明されぬまま残された謎に人類が再び挑む、ファン待望の続篇。」
アーサー・C・クラークが傑作「宇宙のランデヴー」を1973年に書いてから16年後の1989年に出版された、まさかの続編。しかも当時既にSFの権威であったクラークが、NASAジェット推進研究所主任研究員のジェントリー・リーとの共著として書いた。物語の舞台は前作から70年後、再び別のラーマが地球に接近する。今度は十分に準備を重ねた調査チームが組織され、2つめのラーマの謎に迫っていく。
ラーマを主役にして人間ドラマの要素が薄かった前作に対して、この続編では探査メンバー間の葛藤が物語の核となっている。映画を意識していたのだろうか、登場人物の性格や関係がわかりやすいのだが、深みがない。そのため、この続編の批評家たちの評価は決して高くないのだが、前作のラーマの世界観にヤられてしまった人は読まざるを得ないのである。
進化レベルがまったく異なる知的生命体が接触した場合、高次の存在は下位の存在をどうとらえるだろうか。もしかすると、人間がアリの巣をみかけても話しかけたりはしないように、高次な知的生命体も人類に敢えてコンタクトしたりはしないかもしれない。前作では人類の接触に反応せずに悠々と太陽系を通過していったラーマだったが、2回目の接触では何が起きるか、が読者の最大の関心であろう。その基本部分では満足できた。宇宙のランデヴー3も読もうと思った。
共著者ジェントリー・リーには22世紀までの未来を予想したこんな著作もある。
・22世紀から回顧する21世紀全史
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000419.html
・宇宙のランデヴー
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004864.html
この作品の発表は1973年で、私が和訳を文庫で読んだのはもう20年前になる。当時は読み終わったあとしばらく絶句してしまうような衝撃的な体験だったことを覚えている。そしてこの本がきっかけでSF小説を読むようになった。私にとって特別な本である。
この正月にはじめて読み返してみた。20年はこどもが生まれて成人する時間だから、結末を含めて物語の筋は忘れていた。だから、今回もまた感動してしまった。次は60歳になったら読み返そうと思う。
2130年、太陽系に直径40キロの円筒状の人工物が接近する。近くを航行する軍の宇宙船にその正体を調べる指令がくだされる。この人工物体は宇宙を100万年間もの長旅をした末に、太陽系を通過するのである。古代の神の名をとってそれはラーマと名づけられた。ラーマから人類には何のメッセージも送られてはこない。
ノートン中佐ら探査メンバーはラーマにドッキングして、未知の内部空間へと侵入していく。ラーマの軌道が太陽系を離脱するまでに残された時間はわずかである。ラーマとはいったい何なのか?、知的生命との遭遇はあるのか?、ラーマの太陽系接近の目的は?。ラーマが次々に見せる驚異は隊員たちの理解を遥かに超えて謎は一層深まっていく。
映画の原作「2001年宇宙の旅」が特に有名なアーサー・C・クラークだが、私はこの作品が一番好きだ。最高傑作だと思う。人間ドラマが描けていないという批判もあるようだが、ラーマを主役に宇宙の神秘が見事に描かれている。この作品では人間は物語の道具に過ぎないのだと思う。それでいいのだ。
「これは何なのだ」「いったいどうなってしまうんだ?」という読み手の好奇心をクラークは、ラーマの神秘を少しずつ開示することによって刺激し続ける。センス・オブ・ワンダー全開の物語。
人類が月面着陸を果たしたのは1969年である。1973年の段階で宇宙に対してここまでの想像力を発揮していた著者の頭脳も驚異である。ヒューゴー賞/ネビュラ賞ほか多数を受賞した古典。80年代になってから続編(2,3,4)も発表されている。今年の正月に再読の勢いで4まで2700ページ超を全部読んだので、近日、続編も書評をアップしたい。
The Arthur c. Clarke Foundation
http://www.clarkefoundation.org/
「人工授精やフリーセックスによる家庭の否定、条件反射的教育で管理される階級社会---かくてバラ色の陶酔に包まれ、とどまるところを知らぬ機械文明の発達が行きついた”すばらしい新世界”!人間が自らの尊厳を見失うその恐るべき逆ユートピアの姿を、諧謔と皮肉の文体でリアルに描いた文明論的SF小説」
オルダス・ハックスリーによる1932年発表の作品だが、その機械文明風刺の矛先は、科学が進んだ21世紀において一層、、鋭く時代に突き刺さっているように思える。作品中の”すばらしい”新世界では、人々は人工孵化で生まれて、与えられた階級の役割を果たすように条件付けされる。心が生まれながらに統制されているから、住人達は現在に不満も疑いも持つことがない。
「万人は万人のもの」という思想が徹底され、特定のだれかを愛することは恥ずかしいこと、結婚して子供を産むなんて野蛮なことと皆が信じている。社会構造の全般的理解は必要悪で最低限にとどめておくべきという倫理感が浸透しているから、階級間の闘争もなく、社会は安定している。たまに嫌なことがあったら薬物を使って即座に解消することが推奨される。こうして人々は完璧に設計された社会の一部になりきることで、幸福な人生を生きている。
新世界に紛れ込んでしまった「野蛮で未開の」男がトリックスターとして騒動を巻き起こし、この「逆ユートピア」の愚かさ、滑稽さが描き出されていく。しかし、新世界は、実は私たちの作っている現実世界の逆像なのであり、その笑いは読者の信じている価値観や道徳の基盤をも相対化していく。
この作品冒頭にこんな一文が掲げられている。
「ユートピアはかつて人が思ったよりもはるかに実現可能であるように思われる。そしてわれわれは、全く別な意味でわれわれを不安にさせる一つの問題の前に実際に立っている。「ユートピアの窮極的な実現をいかにして避くべきか」......ユートピアは実現可能である。生活はユートピアに向かって進んでいる。そしておそらく、知識人や教養ある階級がユートピアを避け、より完全ではないがより自由な、非ユートピア的社会へ還るためのさまざまの手段を夢想する、そういう新しい世紀が始るであろう。 ニコラ・ベルジャアエフ」
「より完全ではないがより自由な」。いい考え方ですね。