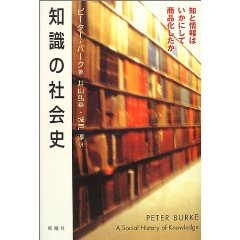Books-Culture: 2009年9月アーカイブ
古今東西の社会と知識の関係を、大きく全体像を鳥瞰すると同時に、細部も観察する。博覧強記の著者だからできた包括的な知識の歴史学。古代から現代までの知識人、首都、図書館、宗教と官僚制、出版と市場、知識と分類などがキーワードである。
冒頭、知識とは何かの定義から始まる。バークは、
「情報」(Information)= 「生の」素材 特殊で実際的なもの
「知識」(Knowledge)=「調理された」素材 思考によって体系化されたもの
としている。「生の」、「調理された」は人類学者レヴィ・ストロースのフィールドワークでの「自然」と「文化」の分類と同じ言葉である。そうすると知恵(Wisdom)とかデータも定義が欲しくなるのだが、知識の社会史は分類の歴史でもあった。
集めた情報を体系化し、再編成していくやり方は時代や地域によって大きく異なる。西洋の近代の学問体系に大きな影響を与えたベーコンは、心には3つの能力(記憶、理性、想像力)があるとして、その図式のもとにあらゆる知識を分類した。たとえば歴史を「記憶」、哲学を「理性」、詩学を「想像力」に分類した。分類思想の変遷は、大学の学部構成や、図書館・博物館の配列といった知識を生み出す制度にも影響を与えている。
知識の社会史は、知識を生み出す体制とそれを破壊するイノベーターの歴史でもある。制度化されることの重要性について、著者はこう書いている。
「一般的にいって、周縁にいる個人は輝かしい新思想を生み出しやすい。他方、その思想を実践に移すには制度を築く必要がある。たとえば、われわれが「科学」と呼んでいるものの場合、十八世紀の制度改革は学問分野の実践に大きな効果を及ぼした。しかしながら制度は遅かれ早かれ固定化し、さらなる変革への障害になる。定着した制度は既得権益の場となり、その制度に権益をもつ集団によって占められ、その知的資本を失うことへの恐怖が生まれてくる。クーンが「通常科学」と呼んだものの支配は、このようにして社会的にも制度的にも説明できるのである。」
中心と周縁、異端と正統、愛好家と専門職、改革と日常仕事、公式と非公式など、しばしば対立する二つの集団の相互作用ぎあいによって、知識を創造する社会自体が進化してきたのだ。
「読者はきっと伝統の維持者よりも改革者の肩をもちたい気になるだろうが、有給の知識の歴史においては、その二つの集団は同じくらい重要な役割を果たしてきたのである。」
バークは中盤で知識の地理学という視点を問題提起的に持ち出す。かつて「この山脈のこちら側では真理であっても、反対側の世界では誤りとなる。」とモンテーニュは言ったそうだが、歴史的にみて情報や知識は、どこにいるかによって異なるものだった。
情報がネットワークでフラット化したはずの現代だって同じである。
・ダーウィン映画、米で上映見送り=根強い進化論への批判
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2009091300077
「【ロンドン時事】進化論を確立した英博物学者チャールズ・ダーウィンを描いた映画「クリエーション」が、米国での上映を見送られる公算となった。複数の配給会社が、進化論への批判の強さを理由に配給を拒否したため。12日付の英紙フィナンシャル・タイムズが伝えた。」
こんなニュースがあったが米国内でもどの州に住むかによって、人類が猿から進化したかどうか、真理が異なる。中東と欧米では宗教によってテロや戦争を引き起こすくらいの真理の隔たりがある。重大事に関する真理は未だに知識の地理性によって決まっている。
しかし、知識の社会史を鳥瞰してみると、場所によって真理が異なること自体は悪いことともいえないようだ。世界の中心はどの時代にも、ひとつではなくていくつもあるということを理解する柔軟さが必要なのだ。
ほかに知識流通の市場の歴史や、読書における精読と速読の対立などという話も面白かった。
この知識の社会史こそ「情報学」として学校で教えたらいいのにと思った。
・読書の歴史―あるいは読者の歴史
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/08/post-1047.html
日本人の叙情精神を「歌」という切り口で平家物語から現代歌謡曲まで通史的に振り返る。短歌や俳句も「歌」であるし、琵琶法師の平家物語や瞽女唄だって「歌」である。乃木将軍の辞世の句も、サラダ記念日も、浪花節や演歌、JPOPも歌である。
だからこの本は、こんな章立てだ。 幅広い。
・空を飛ばなくなった歌?美空ひばりと尾崎豊
・「短歌的抒情」の否定と救済?小野十三郎と折口信夫
・『サラダ記念日』の衝撃?斎藤美奈子と富岡多惠子
・浪花節と演歌?朝倉喬司と春野百合子
・『平家物語』の無常観?小林秀雄、唐木順三、石母田正
・吉川英治と『平家物語』
・挽歌の伝統と「北の螢」?古賀政男と阿久悠
・西行と啄木のざわめく魂
・道元と白楽天
・親鸞の「和讃」
・親鸞和讃と今様歌謡
・瞽女唄と盲僧琵琶?小林ハルと永田法順
・西條八十と北原白秋?日本的叙情
最後の転換期は美空ひばりと尾崎豊のあたりにあると著者は指摘する。
「私は美空ひばりの歌には、いつでも独特の悲哀感が漂っていたように思う。だが尾崎豊の歌には、苦しみと怒りの叫びがいつでもこだましていた。悲哀感は、それこそ「川の流れのように」人びとの胸の裡に浸透し、その内攻する心の扉の中に融けこんでいく。世代の垣根をこえ、誰にでもある観jこうの高ぶりや不安を慰撫して、それを鎮める役割をはたす。悲哀感とは、何よりも時代の感性を生みだす母胎のようなものではなかったのか。」
古の時代から昭和まで、日本人にとって「歌」とは「身もだえの調べ」が本質であった。琵琶法師の平家物語は時の流れに無常を嘆くわけだし、親鸞の和讃は自己の罪悪性に対する悲嘆でもあった。またかつて歌には魂鎮めとしての挽歌(死者を弔う)、相聞歌(愛の歌)という要素もあった。歌謡の底流には、寂寥感や喪失感から何かを嘆く叙情、生命の高揚感や無常観が流れていた。
湿っぽい歌を我々日本人はは長い年月、脈々と愛し、育ててきたのだ。
ところが現代では、湿った叙情に対する軽蔑、敵意さえ感じられるようになった。悲嘆や身もだえは現代の歌謡には、演歌をのぞいて見られなくなった。これは日本の1000年以上の長い歌謡史において、大変な変化であり喪失なのであると著者は結論する。
ユニークな視点で歴史資料を調べ、明解な解説をされていて、まさに歌の精神史として完成されている、よい本だ、面白かった。ただ現代のポップミュージックが本当に叙情を失ったかというと個人的にはちょっと疑問符だ。
私も、確かに昔の(自分が学生だった頃の)歌謡曲は良かったなあ、今聴いても泣けるなあと感じる。それに比べると最新のオリコンチャートのJPOPでは泣けない。悲哀感を感じない。
いまどきの歌謡の歌詞というのは、たとえば
"複雑にこんがらがった社会で組織の中で頑張るサラリーマン。安直だけど純粋さが胸を打つのです。知らぬ間に築いていた「自分らしさ」の檻の中でもがいてるなら照準を絞ってステップアップしたい。とはいえ暮らしの中で、今 動き出そうとしている歯車のひとつにならなくてはなぁ。"
みたいなものだ(ミスチルのマッシュアップ)。著者が言うように「言葉が、うたう対象と距離をおくように慎重に配置されている」ように感じる。なんだか冷静なレイアウトで叙情がないように思える。
ただこれで本当に泣けないかというとどうだろうか?。歌謡というのは同時代の大衆のもの(特に若者)であって、これを聴いて育った世代は結構、これで身もだえできるんじゃないのか?とも思う。実際、著者が叙情がないと指摘する尾崎豊の歌に、私は叙情をたっぷり感じられるのである。
歌謡の伝統は代々受け継がれてきたものであり、常に新しい世代の心を動かす歌が残ってきたのだろうから、1931年生まれの著者が、今の歌謡に響かなくても、大丈夫かもしれないと思ったりもする。まあ、それはともかく日本の「歌」の精神史として非常に興味深い議論の本であった。
・放送禁止歌
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/001449.html
・案外、知らずに歌ってた童謡の謎
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003167.html
大変にユニークであり中身も濃く、面白い。5つ星の本。
人類のはじらいの文化は、野蛮から文明化社会へ、不作法から洗練へ向かったという一般的な見方(ノルベルト・エリアスの文明論に代表される)を真っ向から否定する研究書。原始社会の人々は裸体や排泄する姿を人前に晒すことに恥を感じない野蛮な社会だったというのは根拠がないウソであるという。むしろ原始社会と言われる社会の方が恥の感性は発達しており、裸体の社会的管理も厳格だったりするのである。
全裸で暮らす≪未開の≫部族は、一見、裸に対して羞恥心を持たないかのように思えるが、実は彼らはお互いの裸体を見ないように暮らしているのだ。うっかり男性自身を硬直させないよう女性に近づかないように心掛ける。もし少女の陰部をみつめたりすればその親に報復されたり、村から追放される厳しいルールがある、などということが解説されている。
男が女を見るというだけではない。たとえばいくつかの社会では父親や目上の男の陰部を見てはならない。それは大変な恥辱を与える失礼なことだった。聖書でも父ノアの陰部を見てしまったハムが呪われている。見えても視線を向けてはならなかった。
「裸の社会では、服を着た人たちより礼儀正しく振る舞わねばならない。言葉、身振り、視線もすこぶる慎重で用心深くなければならない。」
原始社会には物理的な個室の壁や衣服がない代わりに心理的な「幻の衣」をまとい、「幻の壁」を作りだして、恥を社会的に管理していたのである。羞恥心の発達は現代人以上に高度で複雑で繊細だったことに驚かされる。
たとえば排泄を見られたら死んでもおかしくなかった。
「ミクマク族の兄弟が森の中にいた時、若い娘は兄の衣服に跳ね上げた便の汚れをみつけたが、それは彼が今しがた傍らの藪の中で用を足したことを物語っていた。それを指摘された兄は、余りの恥ずかしさに大枝で首を吊ってしまったのである。」
小学校でトイレで大の用が足せない子供の感覚は人類史的には結構まともなのである。
「ニューギニアのハーゲンベルグ族は、排泄の最中を偶然見つかると恥ずかしさの余り両手で顔を覆い、首を吊るべきかどうか考える。<中略>用を足している女性を見た男性は、そばへ行き、自分といっしょに寝ないかと尋ねるのが当たり前である。普通、彼女はそれに同意する。なぜなら性交後二人はたがいに親密な関係になったため、恥はなくなるからである。」
うっかり女性が用を足しているトイレのドアを開けてしまった場合、結婚して責任をとるべき社会というのもあるのだ。なんて世界は広いのか。
中世ヨーロッパの魔女裁判の取り調べにおいても死ぬほどの羞恥心が利用された。魔女の疑いがある婦人に対して、悪魔の印がないか検査のため、毛を剃るぞと脅したのである。すると「陰部のあたりの毛を剃られるのはひどく恥ずかしかったので、多くの婦人はへなへなとなり、拷問なんかせずとも一切を白状した」という。
古代ギリシアの裸の英雄、中世の浴場、近代の水浴び、日本やロシアの裸体の扱い、ヌーディストの視線、ベッドでのはじらい、幼児の性、便器、排尿・排泄・放屁、召使いや奴隷の前での露出、刑罰、俳優と娼婦の露出など、裸体とはじらいの関係について、古今東西の文化を比較検討していく。すると裸と恥がヨーロッパだけでなく世界中の原始的社会でも密接に結びついており、はじらいとは人類に普遍の感性であることがよくわかる。恥ずかしさが文化文明を発達させてきた一因でもあるのだ。
この本は写真資料と参考文献が大量に掲載されているのが特徴だ。特に写真資料は古今東西において恥とされたり卑猥とされた絵や写真ばかりだ。学術書なので、そこまできわどいものはないが、ちょっとした珍宝館みたいである。私が一番猥褻だなと思ったのは、フランスの農夫の寝間着の写真だ。上から被るように着るものなのだが、陰部のあたりにスリットが開いている。これは宗教的に性が抑制されていたため、最低限の肌の露出で夫婦の義務を果たせるようにした工夫なのだが、逆にその目的のためだけに開いた切り込みが、いま見ると実に艶めかしく、いやらしい。
本書で人類の歴史を振り返ってみると、ヌードがメディアにあふれた現代日本は、むしろ羞恥心や社会的抑制が極めて衰退しているようにも思える面もある。だが今だって女性は黒いベールで顔を隠す国もあれば、壁のない公衆便所で並んで排泄するのが普通の国もある。どちらが文明化されて洗練されているかなんて一概にはいえないわけだ。そうした「文明化の神話」を裸体とはじらいの関係史をひもとくことで打ち壊すのが本書の著者の真のねらいなのであった。