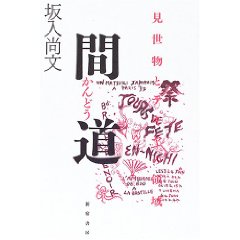Books-Culture: 2009年8月アーカイブ
人間が品種改良したからではなく、植物は自ら周囲の動物の欲望をあやつることでこそ今の姿になったのだという独特の視点に立った共進化論と歴史学のエッセイ。本書で取り上げられる4つの植物とそれらがあやつる人間の欲望は以下の通り。
リンゴ → 甘さ、甘いものが欲しい
チューリップ → 美、美しいものを手に入れたい
マリファナ → 陶酔、ハイになりたい
ジャガイモ → 管理、自然を管理したい
人間はこうした欲望を満たすために植物を利用しているが、逆に植物の視点に立てば、人間に運ばれ食べられることで広域に繁殖することに成功している。
たとえばリンゴはタネが熟すまでは目立たない緑色で甘味もない。タネには毒があって果実しか食すことはできない。だからタネは果実を食べた動物によって運ばれ、未消化のまま地面に落とされる。かくしてリンゴは動物が求める果糖と引き換えに分布域を拡大してきた。
チューリップなら引き替えにしたのは花の美であった。マリファナなら動物の脳に作用する化学物質であり、ジャガイモでは品種改良の容易さであった。
「私たちはつねづね「栽培化」という行為を自己中心的に、人間から植物への働きかけと捉えがちだ。しかしこれは同時に、植物が私たちや私たちの抱く欲望をーーー美意識というもっとも特異な欲望でさえもーーー自らの利益のために用いた戦略でもあるだろう。」
なぜ花が美しいのか。なぜ果実はおいしいのか。なぜマリファナに酔うのか。なぜジャガイモ栽培が楽しいのか。
「植物の進化にとっては、相手の生物の欲望こそがもっとも重要な鍵となったのだ。理由は単純で、相手の欲望をより多く満たすことのできる植物ほど、より多くの子孫を残すことができるからだ。こうして美は、生き残り戦略として生まれてきた。」
最近、テレビや新聞で人間の活動が原因で○○が異常大量発生などというニュースを見るが、本来、自然に異常も平常もないわけである。それは○○という種が、人間の活動をうまく利用して、繁殖に成功したというだけの話である。○○という種の歴史から見たら偉大な一歩なのである。
栽培植物もまた人間の意図や意識が作りだしたと考えられがちだが、実際には人間と植物の相互作用のなかから自然に生まれてきているのではないかと著者はいう。人間を自然の外側に置く思想では共進化の姿を理解できないからだ。
「より均整のとれた花や、より長いフライドポテトを求めて手を伸ばすたび、知らず知らずのうちに進化を決定づける一票を投じているのだ。もっとも甘いもの、もっとも美しいもの、そしてもっとも「酔わせる」ものが生き残っていくプロセスは、弁証法的に展開する。すなわち、人間の欲望と植物の可能性の宇宙のあいだに交わされるプロセスは、ギブ・アンド・テイクの繰り返しのなかで進んでいくのだ。そこで必要とされるのは二人一組のパートナーであって、決して意図や意識ではない。」
欲望を持った植物と人間の恋愛の結果が現在の自然の姿なのだ。
博学の著者は植物をめぐる多様な世界史、文化、社会、技術の話題をこの本の中で全方位で考察している。思えば、環境問題では環境"破壊"、環境"保護"など人間が自然の生殺与奪の権利能力を握っているかのような言葉が使われる。だがそれは植物の側だって握っているものなのだということを思い出させてくれる。
ヤマト王権成立の5~7世紀にはタカミムスヒが最高神で、律令国家が成立する8世紀頃にアマテラスが最高神にとってかわったのではないかという仮説である。
「四世紀までの日本には、第三章で述べるが、唯一絶対の権威をもつ至高神は存在しなかった。そこは豪族連合段階の社会にふさわしい、人間的で魅力あふれる多彩な男女の神々が自由奔放に活躍する多神教的世界だった。それは神話としての魅力には富んでいるが、先生王権が依拠する思想として適切とはいえない。それに比べると北方系の天降り神話は、唯一絶対性・至高性という点ではるかに勝っていて、統一王権を権威づけ、求心力を高める、思想的武器としての力を十分もっていた。」
日本書紀と古事記を比較して、先祖について記載のある氏の登場回数を数えると、地名を名とする半独立の伝統を持つ氏である臣・君・国造系と、職掌を名とする天皇の身内的氏である連・伴造系の2グループで、顕著な違いが見られるという指摘と分析が鋭いと思った。正史が編纂された当時の読者は何を気にしたかに着眼しているのだ。
「現在私たちが『古事記』を読むとき、このような氏の名にいちいち目を配る人はまずいないだろう。しかし、とくに天武の生存中にもしこの書が完成していたならば、おそらくその時代の支配層の人々にとっては天武自身が編纂した欽定本の歴史書に、自分の氏の名が記されているかどうかは、きわめて大きな意味をもったに違いない。ところがこの欽定本には、あきらかに臣・君・国造系にたいする極端なまでの重視、あるいは優遇と、連・伴造系に対する軽視、あるいは冷遇が見られるのである。」
そしてそれが氏族制国家の終焉と律令国家体制への移行のあらわれだという自説展開へつながる。日本書紀の「神代 上」と「神代 下」の二元構造は誰が見ても明らかだ。古い建国神話と新しい天下り神話を"国譲り"で無理矢理接着したからだと著者は分析する。
日本書紀は一君万民の国家を支える新体制のイデオロギーに必要な神話体系として編まれたとされる。その時代に、本来は皇祖神ではなく土着の太陽神であったアマテラスを格上げし、古いタカミムスヒから段階的に置き換えていったのではないかという推論がある。
記紀において武勇伝や活躍シーンの多いスサノオとかオクニヌシなどと比べると、アマテラスという神は最高神である割に、天の岩戸事件での振る舞いに象徴されるような受け身な行動が多い存在である。謎の最高神の秘密を探るミステリーの解明に挑んだ意欲的な新書。記紀好きはぜひ。
・日本語に探る古代信仰―フェティシズムから神道まで
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/03/post-959.html
・日本人の原罪
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/03/post-946.html
・[オーディオブックCD] 世界一おもしろい日本神話の物語 (CD)
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/02/cd-cd.html
・日本史の誕生
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/08/post-799.html
・読み替えられた日本神話
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/02/post-700.html
・日本神話のなりたち
http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/05/post-573.html
・日本古代文学入門
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004835.html
・ユングでわかる日本神話
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004178.html
・日本の聖地―日本宗教とは何か
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004661.html
・劇画古事記-神々の物語
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004800.html
・日本人の神
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003868.html
・日本人はなぜ無宗教なのか
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/001937.html
・「精霊の王」、「古事記の原風景」
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000981.html
・古代日本人・心の宇宙
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/001432.html
・日本人の禁忌―忌み言葉、鬼門、縁起かつぎ...人は何を恐れたのか
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000809.html
・神道の逆襲
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003844.html
・古事記講義
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003755.html
・日本の古代語を探る―詩学への道
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003206.html
写真家ホンマタカシが書いたオリジナルな写真史論と、理解のためのワークショップ、佐々木悟や堀江敏幸との対談、写真関連の私的エッセイなど中身は盛りだくさん。各所に写真資料も散りばめられていて、視覚的にも楽しい本だ。
「写真教育にはブラックボックスが多すぎると、いつも感じてきました。「天才的に撮るべきだ」と言う人がよくいます。教育の現場に身を置いていながら、「写真は教えることができない」と広言する写真家もいます。写真に関する文章も、わざと難しい言葉で書いているんじゃないかと勘ぐりたくなることがしばしばです。」
勘違いしてはいけないが、これはお子様向けのカメラ入門本ではない。ポストモダンの写真史を理解したい大人向けの教科書だ。これまでもモダンの教科書はたくさんあったが、他の分野の文化論と同様に、定説が固まっていないポストモダンはわかりにくかった。
ホンマタカシは歴史の転換点を『決定的瞬間』(アンリ・カルティエ・ブレッソン)と『ニューカラー』(ウィリアム・エグルストン)に置く。小型カメラと大型カメラ、主観的と客観的、モノクロとカラー、瞬間を切りとるシャッタースピードの違い。表現形態の歴史上の変化が年表や写真家紹介によってわかりやすく解説されている。
今日の写真の特徴としては、
(1)ストレートからセットアップへ
(2)大きな物語から小さな物語へ
(3)美術への接近あるいは美術からの接近
(4)あらゆる境界線の曖昧さ
の4つが挙げられている。
こうしたポイントを理解するためにいくつかのワークショップが用意されている。たとえば、「Q:あなたの好きな写真集の中から1枚の好きな写真を選んで、それがどのように成立しているかを言葉で説明し、次いでその1枚と同じ構造の写真を撮影してください。」という出題対する生徒と先生の回答例が示される。実際に自分でやってみたくなる楽しそうな出題ばかり。
自分なりの写真観、写真史観を持ちたいという人に特におすすめ。
というわけで、この本に興味を持つような方のために、明日の月曜日に「写真の境界線」というイベントを執り行いますので、興味関心のある方の積極的なご参加をお待ちしております。下記が案内です。私は司会兼発表者です。
・オーバルリンク写真部主催 2009 Vol.1 写真の境界線
http://blog.ovallink.jp/2009/08/photoevent.html

スーザンソンタグによる写真論の古典。
脱線的な箇所ではあるが、旅行と写真について鋭い考察が大変に印象に残った。ソンタグはこう言っている。
「写真撮影は経験の証明の道ではあるが、また経験を拒否する道でもある。写真になるものを探して経験を狭めたり、経験を映像や記念品に置き換えてしまうからである。旅行は写真を蓄積するための戦略となる。写真を撮るだけでも心が慰み、旅行のためにとかく心細くなりがちな気分を和らげてくれる。観光客は自分と、自分が出会う珍しいものの間にカメラを置かざるをえないような気持ちになるものだ。どう反応してよいかわからず彼らは写真を撮る。おかげで経験に格好がつく。立ち止り、写真を撮り、先へ進む。この方法はがむしゃらな労働の美徳に冒された国民であるドイツ人と日本人とアメリカ人にはとりわけ具合がよい。ふだんあくせく働いている人たちが休日で遊んでいるはずなのに、働いていないとどうも不安であるというのも、カメラを使えば落ち着くのである。」
カメラを持ち歩く旅は、何かを獲得しようとしていながら、何かを失っている。カメラは構えずに、肉眼で見て現実を経験する方がずっと獲得できるものが豊かなのかもしれないのに、だ。(ま、カメラが好きな人は写真撮影という経験を獲得するために旅行をするのでもあるのだが。)
ソンタグは別の箇所で、写真による獲得とは、
1 写真の中の大事なひとやものを代用所有する
2 出来事に対して消費者の関係をもつ
3 経験から切り離して、情報として獲得する
だよと言っている。おそらく1は記念写真、2は広告写真、3は報道写真などといってよいのだろう。写真とはメディアであるが故にからっぽなのである。一枚の写真に意味を無限に読み取ることもできるし、どんな意味を与えることもできる。
「自分ではなにも説明できない写真は、推論、思索、空想へのつきることのない誘いである」
「写真家にとっては結局、世界を飾る努力と、その仮面を剥ぎ取る反対の努力との間に違いはない」
それが絵画芸術と写真芸術の違いでもある。よい絵画と悪い絵画、良い写真と悪い写真を区別する基準は根本的に異なっている。だが視覚芸術として共通する部分ももちろんあるという。
「絵画と写真が共有するひとつの評価の基準は革新性である。絵画も写真もともに、それらが視覚言語における新しい形式上の計画や変化を与えるが故に評価されることがしばしばある。もうひとつ両者が共有できる基準は存在感の質である。」
わかりやすい部分を引用してみたが、これが書かれた1970年代後半の時代文脈を総括する部分(かなり多い)を読み解くには、事前に20世紀中葉までの欧米の代表的写真家の主張や作品についての予備知識が必要である。結構、敷居の高い読み物ではある。
さて、ソンタグは本書冒頭、人間の認知についてプラトンの洞窟のたとえを出した後、
「この飽くことを知らない写真の眼が、洞窟としての私たちの世界における幽閉の境界を変えている。写真は私たちに新しい視覚記号を教えることによって、なにを見たらよいのか、なにを目撃する権利があるのかについての観念を変えたり、拡げたりしている。」
と言っているのですが、このたび来週の月曜日に「写真の境界線」というイベントを執り行いますので、興味関心のある方の積極的なご参加をお待ちしております。下記が案内です。私は司会兼発表者です。
・オーバルリンク写真部主催 2009 Vol.1 写真の境界線
http://blog.ovallink.jp/2009/08/photoevent.html

写真に関する過去の書評。
・明るい部屋 写真についての覚書
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/07/post-1038.html
・撮る自由―肖像権の霧を晴らす
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/08/post-1048.html
植田正治 小さい伝記
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/03/post-726.html
・写真家の引き出し
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/03/post-728.html
・心霊写真―メディアとスピリチュアル
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/06/post-1016.html
・いま、ここからの映像術 近未来ヴィジュアルの予感
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/03/post-952.html
・植田正治の世界
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/03/post-717.html
・不許可写真―毎日新聞秘蔵
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/03/post-724.html
・写真批評
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/005242.html
・土門拳の写真撮影入門―入魂のシャッター二十二条
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004954.html
・東京人生SINCE1962
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/005034.html
・遠野物語 森山大道
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/005029.html
・木村伊兵衛の眼―スナップショットはこう撮れ!
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004923.html
・Henri Cartier-Bresson (Masters of Photography Series)
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004931.html
・The Photography Bookとエリオット・アーウィット
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004958.html
・岡本太郎 神秘
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004986.html
・マイケル・ケンナ写真集 レトロスペクティヴ2
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/005007.html
古代の甲骨文字や碑文から、現代のデジタルテキストまで、古今東西の読書と読者の歴史を博覧強記の著者が、次のようなユニークな20のキーワードで語っている。いつか書かれる「決定版 読者の歴史」のため敢えて未完の体裁をとっているが、極めて網羅的で完成度の高い歴史書である。名著。
20の章立て:
「陰影を読む」「黙読する人々」「記憶の書」「文字を読む術」「失われた第一ページ」「絵を読む」「読み聞かせ」「書物の形態」「一人で本を読むこと」「読書の隠喩」「起源」「宇宙を創る人々」「未来を読む」「象徴的な読者」「壁に囲まれた読書」「書物泥棒」「朗読者としての作者」「読者としての翻訳者」「禁じられた読書」「書物馬鹿」
現代人が普通だと考えている読書スタイルは、長い文字文化の歴史の中で比較的最近になって確立されたものだということがわかる。
西欧では10世紀くらいまで、読書は原則音読であったそうだ。アウグスティヌスもキケロも読書とは声に出す行為であると考えていて、当時の文化人に黙読は珍しかったらしい。死んだ書き言葉に対して生きた朗誦の言葉があり、キリスト教でもイスラム教でも、教典や神の言葉を声に出して読む行為は重んじられてきた。
「中世もかなり時代を下るまで、文筆家は、自分が文章を書いている時にそれを声に出しているのと同じく、読者も、たんに読者も、テクストを見るのではなく、それを聞くものだと考えていた。もっとも、文字を読める人が少なかったため、文字を読める人物が他の人々に読み聞かせるという方法が一般的であった。」
音読するということは聞き手がいることが前提されているということでもある。聞き手は気になる部分を質問したであろうし、読み手はそれに答える必要も生じたかもしれない。一人で内面的に知識を吸収していく現代人の読み方とは、大きく異なる読書形態も長い歴史があったのだ。
この長大な歴史から、書物の分類と内容の解釈が、テクストの意味や価値に無限の広がりをもたせるということに改めて気づかされた。古代シュメールの図書館で目録作成者は「宇宙を創る人々」と呼ばれていた。書物の分類とは、ある世界観に基づいて万物と事柄を体系化する行為だった。そして、分類された本は、分類の軸上で特定の価値や傾向を持つものと評価される。
「分類基準とは、そこに属さない部分を排除するものだが、読書はそうではない。否、そうであってはならないのだ。どんな種類の分類がなされたところで、そうした分類は読書の自由を抑圧することになる。だから、好奇心旺盛で、注意深くある読者ならば、決定づけられてしまった範疇から書物を救い出さなければならないのである。」
「ガリヴァー旅行記」をフィクションとするか社会学とするか、児童文学とするかファンタジーとするか、それによって本の意味が大きく変わってくる。どういう本として紹介するか、だから前提を考え抜くことは大事だ。書評を書く人間も常に意識していなければならない大きな問題である。
そしてこの本から学んだ最大のポイントは読書は創造行為であるということ。
「読書において、「最後の決定的な言葉」というべきものがないのなら、いかなる権威も「正しい」とされる読みを我々に押しつけることはできない。」
ユダヤのタルムード研究者たちは原典に対して注釈を加えたが、常に古い注釈を批判的に読み、原典に立ち戻った再解釈を加えていった。結果としてひとつのテクストから無限ともいえるような創造が行われていく。
「あのはるか昔の聖金曜日にコンスタンティヌス帝が見いだした永遠の真理とは、テクストの意味は読者の能力と願望によって拡充されるといういうものである。テクストを目にした読者は、そこに記された言葉を、歴史的にみれば、そのテクストとも作者とも関係のない、読者自身の問いかけに対するメッセージへと変換する。この変換こそ、もとのテクストの内容を豊かにもしまた台無しにもするわけだが、いずれにしてもそのことは、読者が置かれた状況というものをテクストに吹き込むことにほかならない。ときには読者の無知により、またときにはその信仰によって、あるいは読者の知性や策略、悪知恵、啓蒙精神などにより、テクストは、同じ言葉でありながら別の文脈に置き換えられ、再創造される。まさにその過程で、テクストはいわば生命を与えられるのである。」
読書・読者の歴史は単なる記録媒体と受け手の歴史ではなかった。私たちが慣れている情報のインプットとアウトプットという分け方は本当は単純すぎるのだ。読むということは本質的に創造行為であり、ひとつのテクストは無限の意味と解釈を生む、パターンが生み出すパターンなのだ。
・読書論
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/02/post-932.html
・読書について
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/01/post-913.html
・読書という体験
http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/05/post-569.html
テキヤ稼業(的屋、香具師ともいう)のドキュメンタリ。間道(カンドウ)とはわき道、抜け道、隠れ道、裏街道のこと。日本の伝統文化の隠れた側面を描き出す物凄く面白い内容。
1979年に東京芸術大学彫刻家を中退した著者は、蝋人形をトラックに乗せて見世物小屋を興行する旅に出た。「高物(見世物小屋)」「高市(大きな祭り)」「三寸(露店)」「ネタ(商品)」「太夫(芸人)」。その世界の言葉の意味さえ知らなかった新参者は古株から怒鳴られながら、少しずつ流儀を覚えていく。
「見世物小屋の旅に私はカメラを持って出ている。旅は思いのほか厳しいこともありカメラを紛失したのは旅に出てすぐのことだ。記録しようとする自分にうしろめたさを感じていたかもしれない。異質へのあこがれはたちまちに打ち砕かれる。生きるために禁忌を犯す人たちに共感を強くしていった。歴史は異才、異能の人たちをそれまでの私に見せてはくれなかったのだ。」
各地の祭りの縁日を仕切っているのは極道者も多い。間道に生きる人たちにとって極道も共生関係の仲間である。テキヤとして一人前になって極道とのつきあいがちゃんとできるようになった自分を誇らしげに感じているなどという記述もある。
祭りを追って各地を転々とする旅は決して楽ではない。だがその厳しさがテキヤの迫力を生む。
「ときには野草の雑炊も食べた。移動する夜汽車の中で飯を炊いたこともある。博多のような大高では、見世物小屋は唾に血が混じるまで啖呵を吐き続ける。そのために喉は潰れ声は掠れる。 潰れるのは声だけではない。移動から移動を続けてきた人には、物事にこだわらず通り過ぎる心得のようなものが身についている。自分はどこにいようが、何者であろうがかまわない。それがまた啖呵に反映するのだ。」
この著者は、文化人に働きかけてパリでの縁日興業を成功させたり、本を書いたりと、さすがに元芸大インテリな面もあるのだが、文章からは衒学的なカラーがまったく感じられないのがいい。好きで入ったテキヤ歴20年以上と言うこともあって、すっかりその道の内側からの視点、価値観で、間道に脈々と受け継がれてきた伝統を語ることができるのだ。
表社会と裏社会の間にある周縁文化に関する貴重な証言であると同時に、その魅力にとりつかれた異能者の読み応えのある自伝でもあり、読み始めたら止まらなかった、5つ星な一冊。