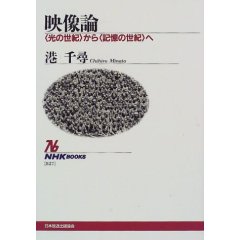Books-Culture: 2007年6月アーカイブ
谷崎潤一郎が日本の伝統美について語った古典的名著。日本的情感の本質をとらえたエッセイ。
難しい本なのではないかと少し構えて読み始めたが、意外にも、とてもわかりやすい内容でびっくりした。
「漱石先生は毎朝便通に行かれることを一つの楽しみに数えられ、それは寧ろ生理的快感であると云われたそうだが、その快感を味わう上にも、閑寂な壁と、清楚な木目に囲まれて、眼に青空や青葉の色を見ることの出来る日本の厠ほど、恰好な場所はあるまい。そうしてそれには、繰り返して云うが、或る程度の薄暗さと、徹底的に清潔であることと、蚊の呻り声さえ耳につくような静かさとが、必須の条件なのである。」
「思うに西洋人のいう「東洋の神秘」とは、かくの如き暗がりが持つ不気味な静かさを指すのであろう。われらといえども少年のころは日の目の届かぬ茶の間や書院の床の間の奥を視つめると、云い知れぬ怖れと寒けを覚えたものである。しかもその神秘の鍵は何処にあるのか。種明かしをすれば、畢竟それは陰翳の魔法であって、もし隅々に作られている蔭を追い除けてしまったら、忽焉としてその床の間はただの空白に帰するのである。われらの祖先の天才は、虚無の空間を任意に遮蔽して自ら生ずる陰翳の世界に、いかなる壁画や装飾にも優る幽玄味を持たせたのである。」
「「掻き寄せて結べば柴の庵なり解くればもとの野原なりけり」と云う古歌があるが、われわれの思索のしかたはとかくそう云う風であって、美は物体にあるのではなく、物体と物体との作り出す陰翳のあや、明暗にあると考える。」
薄暗くて、清潔で、静かなところに日本の陰翳の美はあらわれる、というのが陰翳フェチの谷崎の主張である。
日本の古風な離れにある厠(トイレ)や茶室がそうした建築の代表例として挙げられている(この人は相当のトイレフェチで、この本には「厠のいろいろ」というエッセイも併録されているが、そちらでも排泄や便所そのものに相当のこだわりを見せている)。「もやもやとした薄暗がりの光線で包んで、何処から清浄になり、何処から不浄になるとも、けじめを朦朧とぼかして置いた方がよい。」という。
天に対して屹立する西洋の建築は光に向かう様式美だが、まず瓦や茅葺の大きな屋根を作ってその下に四隅の暗がりを作り出すのが日本建築の本質だと指摘する。暗がりの中に、薄ぼんやりと見えそうで、見えないようなのが日本の、わびさび的な陰翳の美なのである。谷崎はそれを礼賛する。
谷崎は抽象論にいかず、ディティールにこだわる。蝋燭の明かりに映し出された味噌汁って色がうまそうだろう、日本女性の身体のつくる陰って白人女性にはない隠微さがあるだろう、漆器や金蒔絵なんかも暗いところの方がきれいに見えるものだ、とか書いている。明るくて清潔で騒々しい部屋の生活に慣れた現代人が忘れかけている闇の中の美をずばり言い当てているのが凄い。
そして、その闇の中には何があるのかというと、何もないのである。神社の結界が張られた聖域の中が、からっぽな空間であるのに似ていると思った。そこに何かがあると感じる心性こそ日本文化を生みだした日本人の精神の本質ということなのだろう。
「味わい深いもの」を作りたい人は必読の名著だと思う。
人類学者で「京都学」の提唱者 米山俊直の遺作。日本文明の本質を語る読みやすいエッセイ。
「日本文化は稲作文化が主流であると、私たちは思い込んできたふしがある。これは江戸時代の米本位制経済と、土地ことに水田所有にもとづく明治以降の地主制が確固たる私有財産の基礎となり、また食生活でも米が”主食”という観念が根強くつづいてきたためである。」
「日本人はお百姓さんだからリズムが二拍子なんだ」などという俗説をよく聞くが、百姓=農業という思い込みは間違っていると著者は指摘する。中世の「百姓」は多くが兼業農家で、農業以外の多様な職業も含まれていた。稲作の農家ばかりという一般的なイメージは実態と違っていたようだ。「縄文商人」が活躍した時代もあったという話もある。
「日本文明はふつう弥生以来、すなわち今から二三〇〇年ほどのものとされてきた。しかしその補助線としてみるならば、三内丸山遺跡の示すものは限りなく大きい。<中略>これまで二三〇〇年しかないと思われていた文明史に、縄文時代の三内丸山をつけ加えてみると、それが一挙に五五〇〇年も引き伸ばすことになる。それによって、これまで”古代”ということで幽冥のかなたに押しやり、古事記、日本書記あるいは風土記や万葉集を終点としてきた日本の歴史を、長い時間の中で見直すことができるのではないか。」
日本文明の連続性をみていくと縄文時代までを含めた長期でとらえなおすのが正しいと著者は提案している。メソポタミア文明に比肩するスケールで日本史を再評価するという大胆な考え方。
「『小盆地宇宙と日本文化』(岩波書店 一九八九・一・三一発行)で私は、”日本文化”は単一ではなく、およそ百の盆地を単位に成立していて、それぞれが小宇宙=地域文化を形成していると述べた。その単位を”小盆地宇宙”と呼んだのである。日本文化を大脳に見立てるならば、小盆地宇宙はその古い皮質にあたり、新しい皮質としての日本文明がその上に成立しているのであると主張した。」
著者は日本を、単一民族を天皇が支配してきた国というイメージではなく、多様なミクロコスモスの集合とみなすべきだという。大きなレベルでは、古代であれば北九州と近畿、中世には東日本と西日本というふたつの世界が相互に影響しあうダイナミズムの中で、日本の歴史を再定義する。
ところどころで日本とアジア、ヨーロッパの古代史、中世史の類似性を指摘し、生態史観、海洋史観というグローバルなパースペクティブを論じている。日本の常識的なイメージがつぎつぎに覆されていく。
「わたしたちは文字通り「映像の地球時代」に生きている。地球上のどこにいても、特定の地域の特定の情報を、いながらにして手に入れることが技術的に可能なのだ。」
テレビやインターネット、DVDを通じて、私たちはおよそ考えられる限りの映像を入手可能になった。その状況を著者は「ピクチャープラネット」と呼び、写真誕生から現在までの映像史を振り返るとともに、「そこでは見るという行為が、身体的な移動の経験と切り離されて、独立してしまう危険が常にある。」と問題提起をしている。
写真や映画は大衆心理の操作の道具として、前世紀から利用されてきた。戦争報道の写真を新聞に掲載したり、犯罪者のモンタージュで優生学の正当性を主張したり、プロパガンダは映画を積極的に取り込んだ。誰かが作り出す「スペクタクル」映像を人々は信じるようになった。
フランスの思想家ギー・ドゥボールが1967年に「スペクタクルの社会」の中で
「スペクタクルは、社会そのものとして、同時に社会の一部として、そしてさらには社会の統合の道具として、その姿を現す。社会の一部として、それはあらゆる眼差しとあらゆる意識をこれみよがしに集中する部分である。この部門は、それが分離されているというまさにその事実によって、眼差しの濫用と虚偽意識の場となる。」
と書いている。
これはピクチャープラネット化が進んだ現在、ますます重要な問題だと思う。たとえば世界で最近起きていることは無数にあるが、テレビが報道する映像の長さや頻度で、私たちはそれぞれの事件の重大さをとらえがちである。今がどんな時代かという同時代イメージもまた映像に強く影響されていると思う。
この本では、映像とは何かを、映像技術、記憶、身体性などの観点から歴史的に整理して、映像社会の問題を指摘する。
エピローグに登場する、全盲の写真家ユジュン・バフチャルのエピソードは印象的だった。
眼が見えない写真家がカメラを向けると、撮られる人の顔がこわばることを、彼は知っていて逆手にとっている。音などを頼りに自らレンズの絞りを合わせる。撮影後はコンタクトプリントをつくり作品を選ぶ。その作業は対話の中で行われる。そうしてできた写真を彼自身は見ることはない。しかし彼は自分が見たものを信じている、共同作業を信じている。強い印象を持った作品が次々に出来上がる。社会的な盲目状態の人たちと比べて、何倍も見ることを意識している。