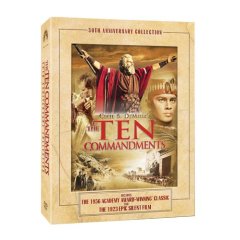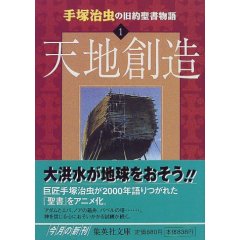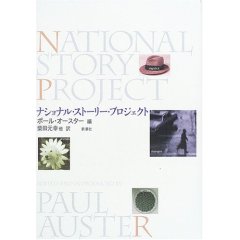Books-Culture: 2007年3月アーカイブ
「写真の誕生から20世紀までの写真の流れを、代表的な写真家の作品を通してわかりやすくたどる。写真家のエピソードや言葉を紹介しながら、隠された姿を浮き彫りにし、同テーマの日本の写真家もとりあげる。 」
現存する世界最古の写真はこれ。
1827年にニセフォール・ニエプスが自宅の窓から撮影した。
ニエプスは、写像をスケッチするために画家が使っていたカメラ・オブスキュラ装置を改良し、金属板に画像を定着させることに成功した。この時期は長時間露光(8時間〜20時間といわれる)が必要であったので、黎明期の写真は風景写真が多い。
そして世界最初の実用的写真技法であるダゲレオタイプが発明され、露光時間は1、2分になり、一般人も使うことができるようになった。これは1837年のダゲレオタイプ作品。
この本は、この一枚から始まって現代まで、60人の代表的な写真家と作風、作品紹介が続く。南北戦争の戦場の写真まである。地面に死体が転がって、遠く向こうに騎兵らしき姿がぼんやりと見える。既に写真があったのかと驚かされた。
・南北戦争−死の収穫、ゲティスバーグ
http://www.rekibun.or.jp/promotion/archive/arch-photo4.html
東京都写真美術館提供で実物が見られる。
記録に始まった写真だが、早い段階で芸術表現のひとつにもなる。各時代の写真家たちは、当時の最先端技術を取り入れながら、今見ても斬新な表現に取り組んできた。たとえば画像処理の技術は100年以上前からあった。30枚以上のネガを合成して絵画のような作品に仕上げたオスカー・ギュスターヴ・レイランダーの「Two Ways Of Life」は、今ならばフォトショップの達人の技である。
REJLANDER, OSCAR GUSTAVE: A History of Photography, by Robert Leggat
http://www.rleggat.com/photohistory/history/rejlande.htm
実物の「Two Ways Of Life」が見られるページ。
多数の歴史的傑作が大きく鮮明に掲載されているため、理屈だけではなく写真の歴史を学ぶことができる名著だと思う。
・ ピンホールカメラ
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004930.html
・Henri Cartier-Bresson (Masters of Photography Series)
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004931.html
・木村伊兵衛の眼―スナップショットはこう撮れ!
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004923.html
・Yahoo!インターネット検定公式テキスト デジカメエキスパート認定試験 合格虎の巻
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004918.html
・Henri Cartier-Bresson (Masters of Photography Series)
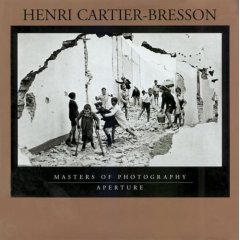
アンリ・カルティエ・ブレッソンは20世紀を代表するフランス人写真家の一人。小型カメラのライカを片手に世界の人々のスナップ写真を撮影し「決定的瞬間」という言葉を作った。この本はその傑作を集めた写真集。洋書。長生きした写真家であったがここに収められたのはすべて白黒写真の時代のもの。約40枚を1時間かけてじっくり鑑賞してみた。被写体の人物に、吹き出しをつけてセリフを書き入れたくなる。ドラマチックだ。
この本の冒頭に2ページほど、アンリ・カルティエ・ブレッソン本人が、自らの写真論を語っている。その中で気になった一節を訳してみた。
「私は「つくりもの」や演出された写真とは無関係だ。敢えて言わせてもらえば、そういう写真はせいぜい心理学的、あるいは社会学的なレベルのものでしかない。事前に準備された写真を撮る写真家と、イメージを発見するために出かけて、それを掴まえる写真家とがいるのだ。私にとって、カメラはスケッチブックであり、直観と自然の道具であり、疑問と決断を、文字通り同時にこなす瞬間の主人である。世界に"意味を与える"ために、写真家は自分自身がファインダー越しにフレームに収める何かと一体感を感じていなければならない。その態度には、集中力と精神の鍛練、感受性と幾何学のセンスが必要である。そして偉大な倹約によってこそ、表現のシンプルさに到達するのである。写真家は、常に被写体と自身に対して最大限の敬意をもって写真を撮らなければならない」
作品を見ていると、被写体と背景という文脈の情報量をいかに簡潔に整理するか、それが切れ味のある写真の極意なのだなと気がつかされる。「決定的瞬間」の元祖の写真は、絞り値を高くした作品が多く、現代のポートレートのように背景をぼかしたものがこの写真集にはほとんどないのである。だから人物スナップであっても時代背景を絶妙に切り取っている。当時の白黒写真は無駄な情報を省くという意味でも、この手法にマッチしたものであったと思う。
どんな作品かをプレビューしたい人は、アンリ・カルティエ=ブレッソン財団に代表作のサムネイルがたくさんある。Googleのイメージ検索でもなぜか大量に見つかる。
・アンリ・カルティエ=ブレッソン財団
http://www.henricartierbresson.org/hcb/home_en.htm
・Googleのイメージ検索
http://images.google.co.jp/images?q=henri+cartier-bresson&hl=ja&lr=lang_ja&um=1&sa=X&oi=images&ct=title
この写真家の「決定的瞬間」として有名なのは、男性が水たまりに向かってジャンプする逆光の写真「behind the saint-lazare station」である。この作品集にも、財団のページにも掲載されている。私は最初この作品を雑誌上で小さなサイズで見た時に、何がいいのか分からなかったのだが、この作品集で大きなサイズで見て、面白さがわかった。
奥にあるポスターに描かれた女性の跳躍と、男性のポーズに最初に注目するといい。奥行きのある左右対称である。同時に水たまりの映りこみが上下の対称を構成している。そのほかにもいくつか対称性を発見できる。偶然のようでいて考えられた幾何学構図なのだ。(しかし、この作品が他の作品と比べて特別優れているわけではないと思うのだが)。
アンリ・カルティエ=ブレッソンの作品には一枚一枚にドラマ性がある。説明がなくても、被写体の人物の生き方や人柄が想像できるものが多い。激動の時代を写した写真家だが、社会的テーマを野暮に掲げる問題意識はまったく感じられない。そうではなくて、それぞれのドラマを背負って生きている人間を、時代の背景と一緒に写すことで、あとは見る者に解釈を任せている。
同時代の日本の写真家、木村伊兵衛とブレッソンは親交があり影響を与えあったと言われる。共通点は多く見出せる。
・木村伊兵衛の眼―スナップショットはこう撮れ!
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004923.html
・Yahoo!インターネット検定公式テキスト デジカメエキスパート認定試験 合格虎の巻
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004918.html
・聖書の謎を追え RIDDLES OF THE BIBLE
http://nng.nikkeibp.co.jp/nng/shop/dvd/bible.shtml

「人類にとって最も重要な物語の一つである聖書。その物語は果たして史実に基づいて書かれたのでしょうか?この史上最大のベストセラーを、あらゆる角度から科学的に解明していきます。聖書を研究するのは今や、聖書考古学者や宗教学者、熱狂的な信者たちだけではありません。地質学者や天文学者、昆虫学者、気象学者、生物学者、物理学者、地震学者、火山学者たちといった科学者も聖書をテーマに研究をし、そこに秘められた謎を解こうとしています。
DVD-BOX『聖書の謎を追え』では、大洪水とノアの箱舟(旧約聖書創世記)、退廃の町ソドムとゴモラの滅亡(旧約聖書創世記)、エジプトから約束の地カナンへの道のり(旧約聖書出エジプト記)、契約の箱アークの行方(旧約聖書出エジプト記ほか)、ヨハネの黙示録の暗号(新約聖書ヨハネの黙示録)の5つの物語を取り上げ、検証していきます。
今年のお正月休みに観た5枚組みDVD BOX。」
●「ノアの箱船」の大洪水は本当にあったのか
●退廃の街ソドムとゴモラはなぜ滅びたのか
●モーゼが奇跡を起こした出エジプト記の真実は?
●十戒の石版を納めた契約の箱はどこに消えた?
●「ヨハネの黙示録」は人類の未来を予言している?
聖書の謎に科学で迫るナショナルジオグラフィックの大特集。購読者割引で購入。
CGも使った聖書時代の再現映像が素晴らしい。
科学者や考古学者が、ノアの箱舟の痕跡を探したり、モーセが海の水を動かした奇跡は本当に起こりうるのか実験したり...。聖書の記述は歴史的根拠があるはずだという信念のもとで、聖書の有名なエピソードを検証する人たちのドキュメンタリである。
科学的アプローチとは言っても、「神々の指紋」のグラハム・ハンコックが有識者として登場するので、どこまで本気か分からないのだが、「ダヴィンチコード」が好きな人には、ちょうどいい娯楽性が入っている。そもそも登場する専門家たちも、ワクワクしながら研究しているように感じた。
西洋の古代史として聖書があるとすると、日本における古代史は、古事記・日本書紀だろう。邪馬台国や卑弥呼の謎を検証するノリに近い気がする。ただキリスト教の信者の多さと、聖書という前提を無条件に信じる思いの強さが、研究の幅を広げ、深いものにしているように思った。その世界の多数が信じているなら、それは事実でなくても真実になる。世界の3分の1くらいの人にとって、それは真実でなければならないこと、なのだな。
学生時代に聖書は通読したことがあるが、長すぎて覚えていられない。映画、アニメや漫画でよかったものを紹介。なんにせよ聖書は知っておくと西洋文化の理解に役立つなあと思う。
これは今見ても物凄い迫力。映画史に残る傑作。
関連書評:
・ユダの福音書を追え
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004582.html
・グノーシス―古代キリスト教の“異端思想”
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004060.html
この写真集を見て心を揺さぶられない人はいるのだろうか?
20年前に出版された、藤原新也の伝説的な傑作。
メメント・モリ=死を想え。
インドの野原で焼かれ、川原で野犬に食われる遺体の写真。「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ」「遠くから見ると、ニンゲンが燃えて出す光は、せいぜい60ワット3時間。」というコメントがつけられている。行き倒れの行者の遺体に「祭りの日に聖地で印をむすんで死ぬなんて、なんてダンディな奴だ。」。
思わず眼を伏せたくなる、生々しい死の現場がある一方で、数百年、数千年変わらない気がする原風景の懐かしさや、この世と思えぬ、天上の楽園のような美しい風景もある。死を意識することは生の喜びを確認することにつながるんだという、著者の視覚メッセージに、まず頭をぶん殴られ、言葉を失い、そして魅了される。
露出不足気味の暗い画面に、ぼうっとインドの、日本の、生と死が浮き上がっている。ピントをあえてはずしていることで、読者の想像の余地を残す。著者が後日談として発表した「黄泉の犬」を読んでおくと、一層イメージが伝わってくる。
この本が出版されて以降も、現代人の日常から死はどんどん遠ざかっている。同時に生の手ごたえも弱まっている。昔よりも今の方がこの古い写真集の衝撃は大きくなっている気がする。
・写真家 藤原新也オフィシャルサイト -fujiwara shinya official site-
http://www.fujiwarashinya.com/main.html
メメント・モリの一部がオンラインで見られます。
・黄泉の犬
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004906.html
すばらしい企画だと思う。3ヶ月かけて毎晩少しずつ読んだ。
ポール・オースターがラジオ番組から、全米のリスナーに対して、あなたが語るべき人生の物語を投稿してほしいと呼びかけた。あらゆる年齢、性別、職業、人種の人々から、何千編もの実話の投稿が集まった。どの話も、語り手にとって人生の中で人に語りたいことが数ページに濃縮されている。オースターはその中から珠玉の180編を選び出して番組で放送した。そしてこの本ができた。
初恋のときめき、愛する人との別れ、壮絶な戦争体験、犯罪や暴力の体験、信じられない奇跡体験、動物の話、学生時代の思い出、九死に一生を得た事件事故など、ストーリーはバリエーションが豊かである。なにげない日常生活の中に自分の人生の意味を見出した話もある。「アメリカが物語るのが聞こえる」。20世紀のアメリカが丸ごとこの本に入っているのだ。
各国でナショナル・ストーリー・プロジェクトを立ち上げて、外国のストーリーを読みあったら有意義だろうなと思った。第二次世界大戦を描いた映画「硫黄島からの手紙」には、捕虜のアメリカ兵の残した母親からの手紙を日本兵が読む場面がある。出征した息子へのアメリカ人の母親の手紙は、敵は鬼畜ばかりだと思っていた日本兵たちの心をうった。
小説や映画原作を書きたいという人にとっても、この本は話のタネが満載だから、かなり参考になるのではないかと思う。
東京大学教授の建築学者が、人類が建築を生みだした起源について大胆な仮説で迫る本。中学、高校生向けにルビつきで平易に書かれているが、人間の精神性と建築の関係について深く考えさせられる内容である。20世紀に入ってからの近代建築史は最後にわずかに記述があるだけで、90%は古代建築について語っている異色の構成。
時代が下るにつれて建築は地域ごとに多様化してしまうので人類共通の建築の歴史と呼べるものは数千年前でしか論じられないと著者は考えたようだ。宗教と建築の関係について特に詳しい。
日本の最高神、アマテラスは太陽神である。高さ48メートルあったと言われる出雲大社はなぜその高さになったのか。出雲大社の周囲には30数メートルの杉の森があった。それより高くすることで天上世界との境界をつくりたかったのではないかと著者は考えている。中心には太い柱があるが不思議なことに屋根を支える構造になっていない。この柱は王者の亡骸を安置し、その魂を天上へ発射するための呪術的装置の意味があった。太陽神を信仰する他の巨石文化のスタンディングストーンと同じ役割を果たしていたのではないかと著者は論じる。
ストーン・サークルやピラミッドはなぜつくられたのか、など古代の建築物についてとても詳しく考察されている。写真も多い。考古学的にはそれらの起源はまだ不明であるはずだが、著者は古代人の心理を想像し、説得力ある仮説を物語る。
たとえば新石器時代に家が出現したことについて、
「久しぶりに見た家が昔と同じだったことで、今の自分が昔の自分と同じことを、昔の自分が今の自分まで続いていることを、確認したのではあるまいか。自分はずっと自分である。人間は自分というものの時間的な連続性を、建物や集落の光景で無意識のうちに確認しているのではないか。新石器時代の安定した家の出現は、人間の自己確認作業を強化する働きをした。このことが家というものの一番大事な役割なのかもしれない。」
どういうことを考えて建築をつくったか、ということと同時に、そういう建築に住まうとどういうことを考えるようになるか、というフィードバックの視点は有意義である。人々のニーズで建築が生まれるが、建築は人々の精神に影響を及ぼすものでもある。そして、インターネットという新しい建築が、そこに住まう人に影響を及ぼしているのだなあ、と思う。
アメリカ史の大家 猿谷要教授の最新刊。なんと御年83歳である。渡航が制限されていたため意外にも43歳ではじめて渡米。それ以降、アメリカの大学に在籍して歴史を研究し、日本に大国アメリカの光と影を紹介してきた。自身が体験した戦後の古きよきアメリカから、次第に軍事力を背景にした帝国主義に染まりつつある今のアメリカまでの変遷を、回想で辿る。
共同通信の調査によると、世界で最も悪い影響を与えていると見られている国としてアメリカはイランについで第2位だそうである。過去に学ばず、大義なき戦争を繰り返している。
「おそらくアメリカ人の多くは、今の超大国のまま永遠に続くと考えているかもしれない。ちょうどローマ帝国の人たちと同じように。」
「しかし今のように他の国から嫌われたまま初老を迎えれば、やがて世界に老醜をさらすようなことになりかねない。これだけ世界中から憎まれ嫌われては、決して美しく老いることなどできはしないだろう。」
モンゴル帝国、スペイン、イギリスなどかつての覇権国家も今は小国である。歴史家の目にはそろそろアメリカも全盛期を過ぎて老いる時期であると写っている。老いて何を残せるのか、アメリカを友のように愛した著者は、軍事力より文化力に重点を移すべきだと苦言を呈する。
前半の古きよきアメリカの思い出話が上質のエッセイとして楽しい。建国以来の歴代大統領の逸話や歴史的事件がしばしば言及される。後半は経済大国でありながら貧困層を20%も抱える今のアメリカの実態や、人種問題の複雑さ、為政者たちの驕りぶり、などが語られている。この230年間のアメリカの全体像を遠近感を持って大局で知ることができる内容になっている。
それにしても83歳で、これだけ明晰な文章って書けるものなのか。著者自身が美しく年をとっているよなあと感心してしまう。