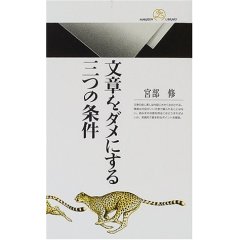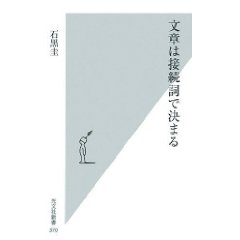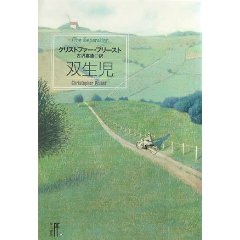Books-Creativity: 2008年10月アーカイブ
文章術の類書は多いが、こうすると文章がダメになるという作文の「べからず」という視点で書かれているのが本書の特徴だ。著者は元読売新聞社のデスクで、大学や文化センターで作文を教えるベテラン。豊富な授業経験から学生たちが陥りがちな悪い傾向を3つみつけたという。
1 文章の意図がつかめない事実や印象の羅列
2 読み手が退屈する理屈攻め
3 読み手の興味をひかない一般論
私も学生時代は作文はあまり得意ではなかった。今思えば、授業という文脈では、書く動機が弱すぎるのだ。提出した作文にはそもそも書く意図などなかった。だから、原稿用紙を埋めるために理屈と一般論を展開していた。
こうした傾向を避けるためのコツとして、書くポイントをひとつに絞ること、書き手の特異な個人的体験に逃げ込むこと、細部の観察にこだわること、など多くのポイントが、学生の作文例を肴にして明解に語られている。
著者の特異体験である新聞記者時代の経験談がやはり光っている。
「記者時代に先輩からこういわれたことがある。「取材が完全にできたときは、できるだけ易しく書け、どこか腑に落ちない取材のまま書かなければいけないときは、理屈っぽく難しく書いておけ」と。理屈は不完全な取材をごま化す一つの手法であり、逃げの一手でもあるのだ。」
材料が十分でなくても書かなければいけないという事態は、新聞記者でも学生でも一緒といえる。そんなときは高度な名文のコツよりも、まずはダメにしないコツの方が、多くの作文シーンで役立つものであると思う。
特異な体験をベースにせよという指摘はやっかいであるが肝である。
「よく"お役所仕事"という言葉が悪いイメージで使われる。これは"前例がないのでできません""人が一般的にやらないことなので、できません"といった消極的な態度を指していうのだが、作文では"前例のないこと""一般的でないこと"を掘り下げて書いてこそ、読むに耐えるものとなるのだ。」
著者の生徒には、自身の堕胎体験を綴った人がいたということだが、人生経験の棚卸しと同時に、内面をさらけだす勇気やノリが大切ということだろう。だからよく書かれた文章には自然と人柄がにじみ出てしまうのだ。
後半で、著者は、自分にはできないがと前置きした後、実は主語が明確に出ていない文章こそ、日本語の非論理性を自然に表した文章であると述べている。ただしそれは文章の巧みな人にのみ許される高度な技である、とも。
私もこのブログで、なるべく文頭が「私」にならないように書こうと日々気をつけていたりするのだが、かなり難しい。主語を隠すと文章の骨格がぐずぐずに崩れてしまうのだ。こればかりは天賦の才能か、相当の練習努力が必要なのだろうな。このブログは1900日を超えたがまだまだ私の文章修行は続く。
「「てか」を好んで使う人は、すぐに新しい話題に移りたがる飽きっぽい人かもしれませんし、「ようするに」が口癖の人は、結論を急ぎたがるせっかちな人なのかもしれません。「でも」をよく使う人は、他人の言うことを素直に受けいれるのが苦手な頑固な人である可能性があります。「だから」を使いたがる人は、自分の主張を人に押しつけたがる押しの強い人かもしれませんし、「だって」を好む人は、言い訳が癖になっている、自己防衛本能が強い人かもしれません。」
接続詞の使い方を見ると隠れた性格がわかるという話。特に講義のような独話では接続詞は書き言葉の2,3倍も多く使われるそうだ。シーン別によく使われる接続詞ベスト5の比較が面白かった。文章のらしさは接続詞が決めている部分も多そうだ。
新聞:しかし、また、だが、一方、さらに
小説:しかし、そして、それで、だが、でも
講義:で、それから、そして、つまり、だから
著者は、対話では接続詞の多用はリスクが高いと注意する。相手の発話権を奪う、言い方を訂正して気分を逆なでする、逆接の使用で無用な対立を生む、自己正当化を目立たせる、という危険性に気をつけて使うべきだと説いている。(私は気をつけていないと「要するに」「つまり」「絶対に」を多用してしまう癖があるなあと自覚した。この注意は耳が痛い)。
普段は意識することがなかった文章や会話の中の接続詞について、深く考える機会を与えてくれる良書である。そもそも接続詞って何?から、「しかし」「だから」「たとえば」「あるいは」「ところが」「さらに」「また」「まず」「したがって」など多数の接続詞のひとつひとつを用例から説明する。「しかし」や「だから」の説明なんて初めて読んだが新鮮である。
接続詞の一般的な定義は「接続詞とは、文頭にあって、直前の文と、接続詞を含む文を論理的につなぐ表現である」というほどのものだが、本書では「接続詞とは、独立した先行文脈の内容を受けなおし、後続文脈の展開の方向性を示す表現である」と再定義している。接続詞は必ずしも論理的ではないということでもある。
接続詞の読み手のための機能として次の6つを挙げる。
・連接関係を表示する機能
・文脈のつながりをなめらかにする機能
・重要な情報に焦点を絞る機能
・読み手に含意を読みとらせる機能
・接続の範囲を指定する機能
・文章の構造を整理する機能
そして接続詞を論理の接続詞、整理の接続詞、理解の接続詞、展開の接続詞、の4種をさらに10類にグループ化して、それぞれに豊富な用例と効能書きが続く。こんなにあるのかというのが素直な感想。著者曰くこれだけ接続詞だけを語った本は類例がないそうだ。接続詞のすべてがここにあるといってもよいかもしれない。というわけで、つまり、だから、それで、とりあえず、まずは........これだけ読んでおけば、もう一生接続詞で困ることはない、でしょうね。
演出家 鴻上尚史が早稲田大学などで教えてきた表現力向上のレッスンを書籍化したもの。20のワークショップを紙上で体験できる。舞台出身らしく声と身体を使った表現力に徹底的にこだわる。
レッスンでは身体接触がやたらと多い。後ろのパートナーの支えを信じて倒れ込む「信頼のエチュード」に始まって、パートナーを彫刻に見立てポーズを作る、とか、目隠ししたままパートナーの姿勢を手で触って真似する、など、自分や他人の身体で遊ぶレッスンが基本である。こうした日常にない身体体験を通して、隠れていた自分の身体の表現力や感情を発見するのがねらい。
これを男女混ざった大学の授業でやっていると学生達はさぞドキドキ・ワクワクだろうなと、想像してしまった。実際、授業では過剰に意識する男女がいるので、鴻上が「異性を触りながら飢えてるぜ光線を出さないように気をつけましょう」などと注意している様子が可笑しい。
日本人の身体接触下手について鴻上は「中学生のフォークダンスの無残さ」をひきあいにこう言う。「日本人は、セックスを前提としない男女は皮膚接触しない」という文化を持ちながら、無条件にフォークダンスを輸入してしまったのです。驚愕の自殺行為です(笑)。体育の時間や運動会の時のフォークダンスが、どうしてあんなに恥ずかしく、居心地が悪かったのか、今なら分かります。」
でも、このちょっとドキドキの高揚感や楽しさがあるから効果がありそうなのである。ここに紹介されているレッスンのほとんどは真面目な顔で一生懸命やるよりも、楽しみながら生き生きとした表情で遊ぶ方が効果がありそうなのだ。生き生きとした表情や感情を見つけることが趣旨なのだから。
教育関係者から「楽しいだけでいいんですか?」と質問されて鴻上は少しムッとしたという。
「ムッとしたのは、「楽しければいいのか、教育目標はないのか?」という考え方が、日本人をどんどん表現下手にしたからです。<中略>表現とは、まず、本人が楽しむことが大前提です。楽しければ、放っておいても、本人はそのことを続けるのです。音楽が楽しければ、作文を書くのが楽しければ、放っておいても、音楽や作文を続けるのです。続けることで、どんどんと表現は上達するのです。」
鴻上のまとめたレッスンはどれも実際に試してみたくなる。ムチャクチャ語で意思疎通をはかるとかその横で勝手に通訳をするとか、ひと言も話さず目だけ手だけ足だけ胸だけで会話するとか、遊んでいるうちに表現法が自然に開発されていきそうだ。この授業を受けたかったなあ。
・真実の言葉はいつも短い
http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/07/post-787.html
複雑、緻密な構成にうならされること間違いなしの大傑作。私などは読み終わって1時間くらい紙に物語の構造を図式化しながら考え込んでしまった。それがまた最高に楽しい時間だった。英国SF協会賞とアーサー・C・クラーク賞を受賞。
1999年、英国のノンフィクション作家スチュアート・グラットンは、第二次世界大戦中の記録に登場する空軍大尉J・L・ソウヤーなる人物のことが気になっていた。チャーチル首相の回顧録にその名前はあった。ソウヤーは良心的兵役拒否者であると同時に空軍爆撃機操縦士でもあったという。そんな矛盾したことはあり得ないはずである。ソウヤーの娘と名乗る女性があらわれグラットンに父の書いた古い原稿を託していく。
タイトルから推測できるように、案の定、ソウヤーの正体はジャックとジョーという双生児であった。この二人の人生が複数の記録や証言によって少しずつ明らかになるのだが、そのプロセスは一筋縄ではいかない。伏線の縄が十本、百本ある感じでそれらが錯綜している。メビウスの輪のように不思議な結び目が幾つもあらわれる。
この作品は物語りというより物騙りである。読者は少しずつずれた同時期の物語を何度も聞かされる。矛盾する語り。それは記録が虚実入り乱れているからなのか、平行世界が幾つも存在しているからなのか。根本的な疑問を抱えたまま現在と過去を何度も往復するうちに、緻密に設計された物語の重層的な迷宮構造が少しずつ姿を現していく。
とてつもないものを読まされたというのが素直な感想。
この読書体験はアゴタ・クリストフの「悪童日記」三部作に似ている気がした。このシリーズの騙り感覚が好きな人に特におすすめである。
・「悪童日記」「ふたりの証拠」「第三の嘘」
http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/02/post-529.html