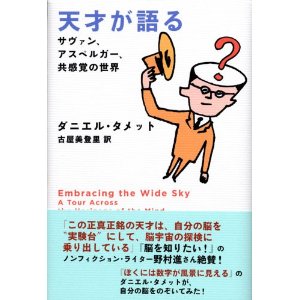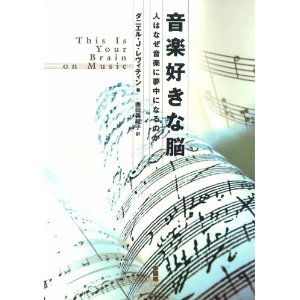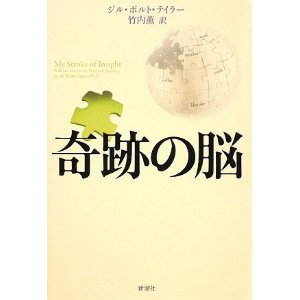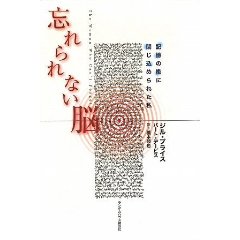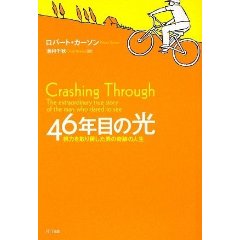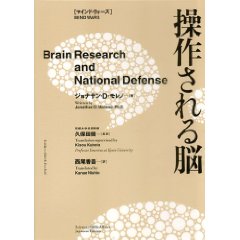Books-Brainの最近のブログ記事
・知性誕生―石器から宇宙船までを生み出した驚異のシステムの起源
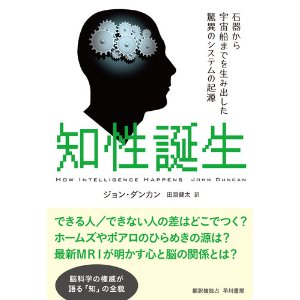
語彙、記憶力、計算、論理思考、反応時間テスト、空間テスト、迷路など、多数の被験者に多様な知的作業をやらせると成績は全体として正規分布を描く。そして何十、何百の項目において正の相関関係がみられる。あることがとても上手にできる人は、べつのことも上手であることが多いのだ。たとえば国語(他の科目でも良いが)ができる子は、算数も英語も社会もできる子である可能性が高い。俗に言う地頭の良さ、要領の良さである。
実験心理学の創始者チャールズ・スピアマンは、無数の能力の相関を調べ上げ、人間の知能には二種類の要素があることを発見した。取り組むどんなことにもその人が用いる一般因子gと、音楽のように他の要素と相関を持たないsである。地頭の良さ、要領の良さは、高いgの賜なのだ。一方、音楽家はいくら作曲や演奏の才能sがあっても、数学や国語ができるとは限らない。sは異なる種類がいっぱい、ばらばらにあるのだ。
ある人物が一般的な仕事をうまくこなせるかどうかは、ある程度、gをみる知能検査の結果で予測できるということになる。次のような凄い事実が紹介されていた。
「考えうる多くの仕事を集めてリストを作り、それらの仕事がどのくらい望ましいか順位を付けるように一般の協力者に頼む。そして、その人たちがどれくらいその仕事に就きたいかに関して、一位から最下位まで仕事の順位表を作成する。次に、実際にそれぞれの仕事に就いている人たちの平均IQの順位で、もう一つの順位表を作成する。何が分かるかというと、この二つの順位はほぼ完全に一致するということだ。さらに言えば、二つの相関は0.9を超える。ある特定の仕事が、一般の協力者が就きたいものであればあるほど、仕事は実際にgの点数が高い人が就いている。」
とすると...。
ある程度、若い頃に自分はgが高いのかどうか見極めて進路選択、職業選択をすることは重要なのかもしれないと思った。gが低いのであれば、sをみつけて伸ばし、芸術や職人や専門的な職業へいくなど、なりたいものと、なりやすいもののすりあわせを早期にすることが大事なのではなかろうか。今の学校教育は絶対にそんなふうに子供を指導しないわけだけれども、この本がとりあげた知能測定と統計分析の科学が正しいのならば、gとsを知ることは可能性を伸ばすことだと考える。
自閉症でサヴァン症候群で共感覚者で、円周率22500桁を暗唱し、10ヵ国語を話す天才・ダニエル・タメットが語る脳の働きと可能性についてのエッセイ集。前作『ぼくには数字が風景に見える』は世界的ベストセラーになった。
最新の脳科学の実験の紹介や、自身の特異な脳の体験に基づく仮説の提示、人間の知性の構造特性の考察、記憶力や創造性の向上に向けたアドバイスなど、博覧強記の天才ならではの幅広い内容になっている。
ベテランの俳優が長い台詞を正確に覚えるコツの話が面白い。彼らは長文を機械的に覚えるのではなく、なぜ登場人物がそれを言うのか、という文脈を理解することで、記憶の「精緻な符号化」を行っているのだという。
「「肉体と精神と感情のすべてのチャンネルを使って、実際にいる相手や、想像上の人物に向かって台詞の意味を伝えるようにしなさい」と指示された学生は、台本をひとりで読んで理解した学生と比べて台詞を覚える力が飛躍的に向上することが実験で証明されている。」
精緻な符号化とは、予備知識と新しい情報を結び付けることだ。ダニエル・タメットが10ヶ国語を覚えられたのも、既に知っている外国語の単語との類似性で、新しい外国語の単語を記憶しているからだという。
タメットの場合は精緻な符号化に共感覚が深く関係する。多くの円周率暗唱者は語呂合わせを記憶に利用するが、数字がカタチとして認識できる彼の場合は、数字や数列を三次元の形状に結びつける。そのイメージを再現することで、円周率を再現できる。精緻化に使える次元が一般人よりひとつ多いのだ。そして数字への本能レベルでの偏執的こだわり。天才の秘密が垣間見えた。
この本は前作よりは天才の自分が足りが減って、天才と脳の研究者としての側面が強くなっている。
・ぼくには数字が風景に見える
http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/07/post-602.html
認知心理学者、神経科学者であると同時にレコード・プロデューサーとしての異色のキャリアを持つ著者が、音楽を脳はどうとらえているのか、研究成果を一般向けにわかりやすく語る。クラシックだけでなくロックやジャズなどのポップスを研究材料としてしばしば取り上げている。ビートルズやストーンズ、ジミ・ヘンドリクやチャーリー・パーカーが脳にどういう影響を与えるかという本なのだ。
音楽の魅力はどこから来るのか?。それは脳にとっての予測可能性と意外性のバランスであると著者は答えている。
「音楽は、期待を体系的に裏切ることによって私たちの感情に語りかけてくる。このような期待への裏切りは、どの領域──ピッチ、音質、音調曲線、リズム、テンポなど──でも構わないが、必ず起こらなければならない。音楽では、整った音の響きでありながら、その整った構成のどこかに何らかの意外性が必要になる。さもなければ感情の起伏がなく、機械的になってしまう。たとえば、ただの音階は、たしかに整ってはいる。それでも、子どもが音階ばかりを飽きもせず弾いているのを聞けば、親は五分もしないうちにうんざりしてしまうにちがいない。」
ピッチ、音質、調性、ハーモニー、大きさ、リズム、拍子、テンポ。私たちは音楽の時間に、音楽の演奏や鑑賞に必要な要素は一通り教えられている。しかし、これらの科学的な意味や、認知心理学的に持つ意味は、知らないことばかりだ。
たとえば、楽器の音の先頭部分は楽器ごとに特徴的な音色を持ち「アタック」と呼ばれている。このアタック部分を取り除いて、その後の持続する音だけにしてしまうと、人間の脳は楽器を区別することができなくなってしまうそうだ。
人間は絶対音感がなくても、自分の好きな歌は、かなり正確なピッチとテンポで歌うことができるという実験結果も興味深い。ハッピバースデーなど"オリジナル"として決まったキーがない曲以外は、だいたいオリジナルキーで歌いだせるものらしい。
音楽の好みについての研究もある。人は十代の頃に聞いていた曲を懐かしいと思う曲、「自分の時代」の曲として生涯覚えているという話は納得。アルツハイマーの老人も多くは14歳のときに聴いていた曲ならば歌える人が多いという。幼いころに聴いた音楽が自分の文化で決められた正しい音の動きとして、脳がスキーマをつくりあげてしまうため、その音楽は特別なものになるからだそうだ。音楽の好みに関して、親の責任は重大なのだな。
この本、実験と研究で解明されたことがいっぱい示されていて面白いのだが、同時に音楽と脳の関係には未解明の要素が多いこともわかる。ま、音楽も絵画も美は、ちょっとはベールに包まれていた方が神秘的でいいのかもしれない。
著者は脳が専門の神経解剖学者。37歳の時、脳卒中に襲われて、まともにはなすこと、歩くことさえできなくなるが、大手術と8年のリハビリで奇跡の復活を遂げた。自分の脳が損傷を受け、そして回復していく体験を生々しくドキュメント化した本書は米国でベストセラーとなった。
脳卒中に襲われた朝、著者は朦朧としていく意識の中で、客観的に自分の身に何が起きているのかを把握していた。一人暮らしの彼女は異変に気づいて助けを呼ばなくてはならないことを理解するが、論理的思考の左脳が破壊されていて、具体的にどうしたらいいのかわからなくなる。
「できごとを順序立てて並べるため、絶え間なく指示を出してくれていた左脳の司令塔が沈黙してしまったので、外部の現実との結びつきを維持すべく、わたしは知覚を総動員しようと懸命になっていました。過去、現在、未来に分かれるはずの時系列の体験は、順序よく並ばずに、全部が孤立したままになってしまっています。言葉による手がかりも得られないので、日常の様々なことまで分からなくなってしまったかのよう。瞬間、瞬間のあいだの知覚的な結びつきを保つことですら、おぼつかない。幾度も幾度も、脳に残されたメッセージをくりかえしました。 (なにをしようとしてるの?助けを呼ぶの?ちゃんとじゅんじょだてて、たすけをもとめようとしてるのよ。なにをしてるんだっけ?てじゅんをふんで、たすけてもらわなきゃ。そうよ、助けをよななくちゃ)」
失われたのは言語能力だけでなく、3次元を認知する能力や、さまざまな感情を感じる能力など、生活に必要な多くのことが、卒中によってできなくなっていた。感情が失われたので喪失や絶望を感じることもなかった。代わりにあったのは、左脳が失われたかわりに支配的になった右脳による宇宙との一体感、不思議な至福の感覚だったという。
彼女は元同僚の医師や母親の力を借りながら、大手術と長いリハビリに耐えて、専門家として現場復帰できるまでの知的能力を取り戻す。この本は、専門家が自身の脳卒中体験を明瞭に言語化できたほぼ唯一の例であるらしい。
驚くべきは回復の過程で自身の人格を作り直すことができたということ。リハビリでは破壊された脳の回路を作り直すわけだが、その際、負の感情やマイナス思考を引き起こす回路の復活を拒むことで、倒れる前よりもポジティブで建設的な自分を作り上げることに成功したと振り返っている。卒中で体験した至福の宇宙との一体感を完全には失わぬように、右脳の働きに重きをおいた作り直しをしたのだ。
原題はMy Stroke of Insight(私の脳卒中によるひらめき)。
「脳卒中によってひらめいたこと。それは右脳の意識の中核には、心の奥深くにある、静かで豊かな感覚と直接結びつく性質が存在しているんだ、という思い。右脳は世界に対して、平和、愛、歓び、そして道場をけなげに表現し続けているのです。」
脳が破壊されるとどうなるかを知ることができる貴重な体験談である。
世界でも稀なハイパーサイメスティック・シンドローム(超記憶症候群)第1号認定患者の自伝。この症候群の患者は物事をすべて覚えていて、忘れることができない。著者の場合は8歳からの人生のすべての出来事を鮮明に記憶している。どんなことでも優劣をつけずにすべて保存しており、いつでも細部まで正確に呼び出すことができる。
想起は何かのきっかけで本人の意図しないときに始まることもあり、脳内の映像再生が止まらなくなるそうだ。その時、記憶に付随して当時の喜怒哀楽も追体験するため、心休まることがなく苦しい人生を過ごしてきた。自らを記憶の囚人と呼んでいる。悲しい思い出が芋づる式にでてきて止まらないのだ。またその記憶力は勉強の暗記ではまったく働かない。学校の成績に記憶能力は反映されなかったこともあって、大人になってから異常な能力が発見された。
彼女の記憶で実に不思議なのは、日付と曜日が想起のための鍵になっていることだ。
「たとえば、2007年7月4日の独立記念日は水曜日だった。その日の記憶を思い出そうとすると、それにつながって私のこれまでの人生のすべての7月4日の独立記念日のことが次々とよみがえってくる。しかもその日が水曜日である年が優先されて、1990年、1984年、1979年と浮かんでくる。」
人間がつくった文化であり後天的に学習するカレンダーが、自然に脳に組み込まれているのが奇妙だ。しかも彼女の脳内にはかなり風変りな屈折カレンダーがインストールされているそうで、そのかたちを絵に描いている。なぜか1970年を境に90度回転する。なぜなんだろうか?
そのほか著者にはかなりの度を越した収集癖と、異常なほど細部まで書きこむ日記の習慣がある。日記は記憶の補助ではなく(彼女には不要なのだ)、それを書いている間は平穏な気持ちでいられるから続けているという。
彼女と同じ症状の患者は世界にも数えるほどしかいないため、異常な記憶力の原因はまだ未解明だが、こうした症例の研究成果から、普通の人間も圧倒的な記憶力を持つ方法が見つかるかもしれない。事実、ネズミの実験では記憶力増強がすでに実現されているそうだ。
そして、想起に基づく生々しい追体験は彼女を苦しめてきたが、子供の面倒を見る仕事を得意にした面もある。いい先生をつくりだす技術としても発展する可能性があるのかもしれない。
「私の特異な記憶力は、私を扱いやすい娘や扱いやすい生徒にはしなかった。しかし、いつまでも子どもと同じ目線で、子どもの心に同化することができる感覚があることで、私は今、子どもと大人を結ぶパイプ役をつとめることができる。」
・書きたがる脳 言語と創造性の科学
http://www.ringolab.com/note/daiya/2006/02/e-eaeniew.html
・ぼくには数字が風景に見える
http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/07/post-602.html
・共感覚者の驚くべき日常―形を味わう人、色を聴く人
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000533.html
3歳の時に事故で失明した男性メイが、46歳の時に手術で奇跡的に視覚を取り戻した。物心ついてから、はじめて見る光に満ちた世界。長年暮らしてきた妻や子供たちの姿を見ることができて感激する。だが46年間の失明状態は、メイの脳に深刻な影響を与えていた。ものが見えるようになっても、それが何なのか視覚以外の手がかりがないとわからないのだ。目に見える世界を解釈するのに大変な努力が必要になった。
これだけ長期的な失明の後に回復した事例は、有史以来20件程度しか記録がないという。メイの視覚や脳に何が起きているのか、正確には誰にもわからない。メイの症例の研究は、人間の脳と視覚の謎の解明に迫る貴重な情報源だった。
メイは雑誌の3ページにわたる折り込み写真を見て「信じられない、この人、体の真ん中に折れ目が入っている」と驚く。紙の折り目が区別できなかったのだ。「いま歩いてくるのは男なのか女なのか」。スカートやアクセサリのようなヒントがなければ男女を見分けられない。だからメイは街を歩く人の性別や美人かどうかを判別して、奥さんに正解を教えてもらう練習をする。
「よーし、こっちに歩いてくる人がいる。髪の長さは中くらいでブロンド。ハンドバッグをもっているみたいだ。お尻を揺らして歩いている」と、メイは分析した。「女性だと思う。セクシーな女の人なんじゃないかな」「よくできたわ、マイク、そう、セクシーな女性よ」
メイは動きと色はうまく見て取ったが、顔の認識、奥行き、物体の識別をたいへんな苦手とした。それらは一目瞭然ではなく、脳が視覚から受け取ったデータを瞬間的、無意識的、自動的に膨大な量の知識を処理した結果、知識が「見る」ことを可能にする要素だったのだ。たとえば脳は対象物の大きさを認識するために 【網膜上の大きさ×距離】を計算しているのだ。メイにはその脳の処理系が欠落している。眼の錯覚にひっかからないのもその証拠だ。
本書は人類史上においても稀有な体験をしたメイの半生のドキュメンタリである。目が見えずとも持ち前の明るさと勇気で道を切り開いてきた子供時代、ぶつかることをおそれず全速力で走った学生時代、生涯の伴侶との運命の出会いと子供たちの誕生、起業家としての挑戦。眼の手術は彼の人生の一部にすぎない。多くの視力回復者は鬱状態に陥るというが、彼は常にポジティブ・シンキングで術後の苦難を乗り越えていく。
実話だがフィクションのような感動的な物語。
・視界良好―先天性全盲の私が生活している世界
http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/07/post-616.html
・眼の誕生――カンブリア紀大進化の謎を解く
http://www.ringolab.com/note/daiya/2006/05/post-380.html
・つきはぎだらけの脳と心―脳の進化は、いかに愛、記憶、夢、神をもたらしたのか?
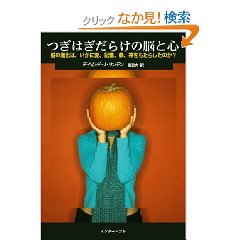
愛情、記憶、夢、楽しむセックス、神(宗教)など多くの「人間らしさ」は脳の進化上の制約(設計ミス)から生じたとする刺激的論考。著者は脳の可塑性研究の国際的リーダーのデイビッド・J・リンデン教授。
脳の進化上の制約とは、
1 既存のもののうえに新たな部分を付け加えるしかない
2 いったん持たせた機能を「オフ」にするのが非常に難しい
3 ニューロンの処理速度が遅く信頼性が低い
ということ。「その場しのぎの対策」のためのつぎはぎによって、脳は大きくなり、ネットワーク構造は複雑になり、万能機械になっていったが、燃費は悪く非効率で、予想外の副産物を多く生み出していった。
へんてこなシステムとして夢がある。著者によると、人間は毎晩夢を見ることで膨大な記憶を整理していく。レム睡眠とノンレム睡眠の反復によって記憶の定着と統合を行っているというのだ。そして、非論理的で奇想天外な物語が夢の中で展開されることで、超自然的な物語が脳に定着し、宗教を信じる脳ができあがったと説く。
こうしたユニークな見方が幾つも提示されるのだが、記憶の想起はグーグルと似ているという話も特に印象に残った。
「たとえば「去年の夏、海岸に日帰り旅行に行ったとき、一緒だったのは誰?」と入力すると、「海岸」や「去年の夏」といったキーワードに関わる記憶の断片が数多くヒットするというイメージだ。これが「去年の夏、海岸に日帰り旅行に行ったとき、雷雨にあって、家に向かう車のなかで気分が悪くなって戻った時、一緒だったのは誰?」だと、キーワードの下図がさらに増えることになり、出来事についての記憶が多く蘇る可能性が高くなる。同じ出来事でも、そのさまざまな側面について思い出せる可能性が高まるのだ。もちろん、記憶(宣言的記憶)の検索の場合、通常、文字を使って検索するわけではないところがグーグルとは異なる。」
ただし想起のプロセスは似ていても、記憶と記録ではその後がかなり異なる。人間の脳はグーグルと違って、正確に記録データを再現するわけではないからだ。ついつい物語をつくろうとする性質がある。さまざまな記憶の誤りや、過大・過小評価も伴う。
「記憶の検索は、蓄えてあるものをただ見つけ出して取り出すようなものではなく、もっと積極的、能動的な活動である。過去の出来事についての記憶に後から修正を加えることもある。」
進化上の制約によって、人間の脳にはさまざまな記憶のエラーが起きやすくなっている。かつては生存のために有利だった認知バイアスも、現代では判断を誤らせるだけの設計ミスになっている。脳の成り立ちや仕組みというハードウェアの理解は、脳の誤りを意識的に補正して考えるソフトウェア設計の知恵になるだろう。
また、記憶のエラー、非論理的な夢はともに設計ミスではあるが、おそらく創造性の源でもあるはずだ。本書が集中的に論じている脳の非合理性を、もっと突き詰めて研究したら、天才的ひらめきを連発する脳も作れるようになるのかもしれない。
・脳はあり合わせの材料から生まれた―それでもヒトの「アタマ」がうまく機能するわけhttp://www.ringolab.com/note/daiya/2009/04/post-973.html
・脳はあり合わせの材料から生まれた―それでもヒトの「アタマ」がうまく機能するわけ
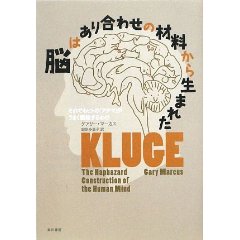
人間の脳はその場しのぎの改変を重ねてたまたま今の形になったという脳科学+進化心理学の書。原題は"KLUGE"。クルージ(kluge)とは「エレガントにはほど遠く無様であるにもかかわらず、驚くほど効果的な問題解決法」という意味。
ヒトの身体は明らかに最適化されていない。たとえば四足動物の脊椎を二足歩行に転用したため、速くは移動できず、多くの人が腰痛に悩まされている。呼吸と食事のために使う器官を発声に転用したので人間の言語は混乱している。目は受光部が後ろ向きのため盲点が存在してしまう。そして脳には反射や衝動を司る古い部分にのっかって思考を司る新しい部分が加わっているから、純粋な推論が下手だ。
進化の歴史の上でいきあたりばったりに、古い技術の上に新しい技術をぬり重ねたのが、ヒトの身体なのだ。この姿からだけでも全能の神が未来を見越して最適の姿にヒトを設計したわけではないことがわかる(米国で盛んなインテリジェントデザイン説を否定している)。
なんでこんなことになっているのか?著者はヒトがたどった進化の道は「完璧であることが最善策ではない」からだと分析する。「進化は一番高い頂きとは異なる山頂(局所最大)で身動きできなくなっていることも大いにありうる」。四足が最適だった時代は四足であることで最高の山を越えたが、次の頂は二足歩行が最適な山だったというわけだ。複数の山あり谷ありの長い進化の過程では、不完全もまた良策ということになる。
最後に進化した脳は、高い山頂と次の山頂の間で身動きできなくなったクルージの代表例である。私たちはコンピュータのように論理的に考えることが苦手である。論理的に考えるには相当の訓練を必要とする。そうでなければ感じたことを信じてしまいがちだ。その理由は、ヒトは知覚に使われていた装置を思考に転用したからだという。我々が日常に目にするものの大半は正しい(見たものは存在する)わけだから、とりあえず見たものを信じることで生き残ることができた。
「最適にデザインされたシステムならば、信念と推論(やがて新しい信念になるもの)の導出過程は別個に保たれ、両者のあいだを鉄の壁が隔てているはずだ。そのような系では、直接証拠のある事柄と、単に推論で導き出したものをたやすく区別できるだろう。ところが、進化はヒトの心が発達する過程で別の経路をたどった。ヒトが完璧に明示的な形式論理論をさほど内省することもなく、無意識のうちに行っていたに相違ない。リンゴが食べられるなら、たぶんナシも食べられるだろうといった具合に。」
進化上で古い"反射型システム"と、新しくできた"熟考型システム"の二つから人間の脳はできあがっている。動物的な反射型システムのふるまいを研究することによって、ヒトの進化の過程や脳の動作原理の解明ができるはずだという。
「熟考を要する決断を、意識を持たない反射型システムへと毎度のように委ねるのは賢明な策ではない。反射型システムは脆弱だし、バイアスにもたやすく染まる。反対に原初の反射型システムをすべて捨て去るのもまた愚かな振る舞いである。<中略>反射型システムが日常の処理に優れる一方で、熟考型システムは経験したことのない事態に対処するうえでの助けとなる。」
そして二つのシステムの長所を組み合わせる方法論を13の叡智としてまとめている。不完全であり多様であることが種としては最善の戦略なわけだが、個としてはその不完全さを克服していかねばならないということ。結局、それが人生が思うようにならない理由のような気がしてきた。
本書が紹介していくDARPA(米国防総省国防高等研究計画局)の最先端脳科学研究は、人間の脳を意図的に操作する可能性を探っている。脳科学の可能性を示す、興味深い研究事例が次から次に出てくる。
・思考を読み取る技術
・思考だけで物体を遠隔操作する技術
・電子的、薬物的な認知能力の強化
・恐怖や怒りや眠気を感じなくする技術
・敵の脳に影響して戦闘能力を奪う化学物質
ブレイン・リーディング、ブレイン・コントロール、ブレイン=マシン・インタフェースなど脳を操作するテクノロジーの最先端がどうなっているかを、大統領倫理委員会のスタッフをつとめた科学者がレポートする本である。
実験マウスのレベルでは脳に電極をつけることで体を無線制御することが可能になっているらしい。脳画像解析によって何を考えているかを機械が判断する技術も、思い浮かべた数字を当てるくらいならば実現されつつあるという。
こうした技術が進めば脳のレントゲンのようなものになる。将来的には悪意のテロリストを飛行場のゲートで脳スキャンして発見するなどの用途が期待されているようなのだが、心の中まで丸見えになると社会のあり方、人間関係もずいぶん変わらざるを得ないだろう。
悪意を持つ人がセンサーで検出されたら即逮捕、人間はそもそも悪意が発生しないように電子的に脳を自己制御することが義務づけられる、などという暗黒SF時代がくるのだろうか。研究の現状を見る限り、可能性としてはゼロではないが、まだ時間はかかりそうで少しほっとする。
私がいま欲しいのは脳の中身をすべてWiki形式にエクスポートする機能である。"ROM吸い出し"みたいな要領でできるようにならないであろうか。そうやってみんなの頭脳が外部化されてつながっていけば知識の革命が起きると思うのである。Webどころの騒ぎじゃないと思うのだが、これも実現はまだ遠いか。
DARPAの研究の本来の目的は最強の兵士や兵器を作りだすためだ。その政府の軍事目的のために研究に従事しているのは、ほとんどが民間の大学の研究者達である。当然、倫理的な問題が発生する。著者はこの本の中で科学の最前線を紹介すると同時に政府や軍部と民間の研究期間がどういう関係を構築していくべきかを大きなテーマとして扱っている。
「民主的な社会が秘密主義の最小化を実現する方法は、国家安全保障諸機関を、より大きな、アカデミックな科学界に結びつけておくことだ。DARPAは外部への資金援助から手を引くべきだと議会やその他の場で提案されているが、同じ理由からこれには抵抗すべきである。アカデミック世界と国家安全保障に係わる体制側とのあいだがつながっていれば、両者が隔離されれている場合に比べ、社会はずっと健全なものになるのだ。」
そして何より科学者、技術者が高い倫理意識を持つことが重要になりつつあるのだともいえる。この本はそうした問題提起の書である。
心とは何かを科学者が哲学的に探究する。面白い。
著者は記憶こそ心の基本であるという。記憶には想起、記銘、保持といった機能が生物学的に備わっている。こうした記憶の照合作用から、時空(位置や時間の堆積)、論理(原因と結果の堆積)、感情(快不快の堆積)という3つの基本的な枠組みがでてくる。そしてさらに統合能力としての統覚が、記憶の中の離散的なもの(時刻、位置、事象、快苦)の中から連続的なもの(時間、空間、因果律、好悪)を見出し、世界の認識に至る。
著者のアプローチは心を物質に還元しない。物質世界、生物世界、心の世界が入れ子構造になっているが、それぞれの世界に独自の法則が働いていると考える。心も遺伝子の乗り物と考えるようなドーキンス的アプローチとは一線を画す。
まず各世界を特異点(開闢)、基本要素、基本原理、自己展開といったキーワードで分析していく。物質世界の自己複製のはたらき(例:RNA)が生物世界を開く特異点となったように、生物世界が心の世界を開く特異点は記憶の成立とその自己複製作用だと著者は指摘する。記憶の能力を高めた人類は、経験する世界を統合して理解しようと試みる。だが、個別の経験からは当然ながら矛盾が現れる。
「離散と連続、有限と無限とは所詮は水と油であって、何としても橋渡しが叶わぬものであるのに、統覚がこれらを結び合わせてしまったことは、心の世界観に決定的な矛盾を忍び込ませる結果をまねいた。これは心の世界のその後の展開に測り知れない影響を与えている。というのは、それからというもの絶えず綻びかかる個別と普遍とのあいだの結び目を、際限なく繕っていかねばならぬ破目に陥ったからである。」
基本原理で世界を理解しようとすれば矛盾があるから、それを解決すべく私たちの認識する世界は自己展開し常に新しい世界として開く。これまでの公理を書き換えて新しい公理系を打ち立てようとする。「一つの世界とは一つの公理系であって、新しい世界を開くとは新しい公理系を立てることにほかならない」。このライブな動きこそ私たちの心の原動力なのだ。
まるで証明問題の如く心の世界を極めてロジカルに説明している。一つの説明としての自己完結度、収まりの良さはちょっと感動である。
アマゾン、ブログなどの読者評価はふたつに分かれているようだ。
この本はほとんど哲学なのであるが、難解な哲学用語は出てこない(用語は必ず定義が示される)。哲学者が好む文学的レトリックも少ない。その代わり簡単な言葉の積み重ねなのだけれど複雑な論理式がしばしば用いられる。理系頭の人には高評価で、文系哲学好きにはアプローチ的にちょっと辛いというのが、評価をわけた理由かなと思う。
タイトルから内容がわかりにくいが、タフツ大学の小児発達学部教授で読字・言語研究センター長が書いた「読書脳」の本である。
私たちが字を認識して読書をする能力は、脳の特殊化と回路の自動化のおかげだという。人間は生存に必要な物体認識の古い回路を特殊化して文字認識の回路に再構成した。やがて視覚が受け取った情報を言語として理解するプロセスは高度に自動化されて流暢に読み書きをする能力になった。人間の読字能力の獲得には2000年を要したが、現代人は生まれて2000日でこの言語能力を身につける。
使用言語によって脳の使い方が異なるという点が興味深い。漢字とアルファベットでは脳の別の領域を使う。漢字と仮名が交ざった日本語を使う日本人の脳は、漢字を読むときは中国語に近い経路を使うが、平明な音節文字である仮名部分ではアルファベットに近い経路が活性化する。バイリンガルの人が脳梗塞になると片方の言語能力だけを失う症例もあるそうだ。脳の読書機能は多くが後天的な学習で構成されているのだ。
「流暢に読解する読み手の脳は今まさに、進化した文字を読む脳の最も重要な才能を手に入れようとしている。時間である。解読プロセスをほぼ自動化させてしまった若い流暢な脳は、隠喩、推論、類推、情動というバックグラウンドを経験から得た知識と統合させて、そのたびに時間を1ミリ秒ずつ縮めることを学ぶ。読字発達の過程で初めて、脳が思考と感情を別々に処理できるだけの速さを手に入れるのだ。」
私たちは学校や家庭でこの流暢に読む能力を自然に身につけていくように思える。しかし米国では人口の15%程度が読字能力に問題を抱えているという事実がある。日本でも近年の学習障害研究で、読字能力に問題を抱えるこどもの数が意外に多いことがわかってきた。後半は著者の専門であるディスレクシア(読字障害)の探究の章が続く。
エジソン、ダ・ヴィンチ、アインシュタインなど世紀の大天才達がディスレクシアであったといわれる。読字能力の欠落は天才的な能力と結びつくこともある。そして著者は自身の子供がディスレクシアであると同時に、それが遺伝する家系であること告白している。学者としても個人としても真剣な研究なのだという情熱がこの本からは伝わってくる。
読書脳の可塑性はデジタルメディアの出現によって新たな展開を生むかもしれない。新しい読みの体験は脳の再構成と自動化を進めていくからだ。
「文字を読む脳によって磨かれたスキルが、今、コンピュータの前に座り、目を画面にくぎ付けにして読んでいる新しい"デジタル・ネイティブ"世代のなかで形成されつつあるスキルに取って代わられることになったら、私たちはいったい何を失うのだろう?。」
と著者は心配しているが、私は、失うものよりも何を獲得しつつあるのかのほうが気になる。検索とザッピング、マルチメディアとハイパーリンクを前提とした読みの行為が人生の読書体験の過半を超える時代はもうすぐやってくるだろう。そのとき人間の脳はどう変貌していくだろうか。
それとこの「プルーストとイカ」。プルーストについては詳しいのだが、イカについて記述が少なすぎてよくわからなかった。私の読解能力不足のせいではなさそう。イカについてもっと書かないとイカん。(あ、書いちゃった)
読字に関する最良図書としてマーゴット・マレク賞を受賞。
「最初から百パーセント集中せよ」「相手の攻撃は最大のチャンス」「相手の長所を打ち砕け」「勝負の最中にリラックスするな」。北京オリンピック日本選手団に勝負の勝ち方を講義した有名な脳外科医によるベストセラー。
著者は「意識」「心」「記憶」は連動しているという「モジュレータ理論」を提唱している。脳内のドーパミン系神経群がその三者の連動させていると考えており、それを最適化することで、人間は潜在的な能力を開発できるという。
具体的には「サイコサイバネティックス」と呼ばれる行動理論を応用する。
1 目的と目標を明確にする
2 目標達成の具体的な方法を明らかにする
3 目的を達成するまで、その実行を中止しない
目的よりも目標を心掛けることが勝利の秘訣になる。オリンピックなどで優勝選手が「気がついたら一位になっていた」「結果は気にせずよいプレーを心がけた」というコメントをする選手がそうした原理で成功した人たちだ。精神論で猛練習ではなくて、楽しみながら集中しているうちに上達するということらしい。チクセントミハイのフロー理論にも似ている。
「モジュレータ理論」とともに「イメージ記憶」というキーワードも興味深い。野球のピッチャーが時速150キロ以上のボールを投げるとき、ホームベースに達する時間は0.45秒以下になる。一方、脳がボールを見て身体にスイングを命令し振り切るまでは合計で0.5秒になる。理論的にはバッターは150キロのボールを「よく見て」打つことはできない。見ていたら振り遅れてしまう。
「そのためバッターは、ピッチャーを投球動作をしている段階から、ボールが手元にくるまでの軌道をイメージ記憶をもとに予測して、バットを振るのです。だから、時速150キロ以上の豪速球でも打つことが可能になるのです。 経験を積めば積むほど、ボールの軌道の記憶はたくさん蓄積されていきます。バッティングの達人とは、過去に成功したときのイメージ記憶を膨大に蓄え、それをあらゆるボールに対して当てはめることができる人のことです。」
こうした能力を引き出すには、「意識」「心」「記憶」を適切にコントロールしなければならない。かなり心の持ち方が重要になる。練習では普通でも、大きな試合に出ると神業を繰り出す選手はそうした調整がうまい。勝負脳について著者は、三者を統合するモジュレータを最高に機能させる考え方を中心に教える。頭を使って運動能力と運動神経を鍛える「運動知能」論は科学的な精神論なのであった。
中年女性ジャーナリストが自身の記憶力減退を感じたのをきっかけに脳力開発に取り組んだ。食事改善、睡眠改善、脳トレ、薬やサプリなど、頭が良くなると言われるものを手当たり次第に試しまくった脳トレ体験記。
著者の体験はとても幅広い。脳サプリメントの「ブレインサステイン」だとか、
・Brain Sustain
http://www.healthdesigns.com/brainsustain.html
インターネット上で受けられる脳開発プログラム MyBrainTrainerだとか、
・Brain Exercises, Brain Age Test and Cognitive Exercises by MyBrainTrainer
http://www.mybraintrainer.com/
任天堂DS「脳を鍛える大人のDSトレーニング」の英語版BrainAgeだとか、
・Brain Age
http://www.brainage.com/launch/index.jsp
簡単に入手できる者もあるし、スタンフォード大学の不眠症研究室の治療、ヘッドギアをつけた脳波矯正プログラムだとか、MRIを使った脳の画像検査など、最先端の脳医学の御世話になったものもある。ちょっと怪しい気がする瞑想や気功も試している。
そうした体験の合間に、中年の物忘れとアルツハイマー病について、最新医学が解明しつつあることが説明されている。30代、40代からボケの兆候は見られるらしい。早期に発見して対策することが大切になってきている。
85~89歳の人に言葉の記憶テストをすると、全体の5%は17歳並の記憶力を維持しているそうだ。新しくて難しいことに常に取り組むことが脳をいつまでも若々しく保つ最善の策であるという当たり前の結論なのだが、若い頃に脳をフル回転させることが「認知力貯金」になってボケを遅らせる可能性があることや、子供の頃におでこを打った影響(従来はたいしたことがないと思われていた)でボケが早まるなんていうこともわかってきたようだ。
脳トレについては、ある程度複雑な作業を並行させると、単独で順番にこなすときより時間がかかるという「マルチタスクの非効率」現象についての研究が興味深かった。
「カリフォルニア大学アーヴィン校の研究者グループが、IT労働者を対象に、注意が散漫になったり、作業が中断させられたりする頻度を調べてみた。すると、十五分に一回ぐらいだろうという事前の予想を裏切って、実際は三分の一回の割合で起こっていた。しかも中断した作業のうち、その日のうちに再開できたものは全体の三分の二にすぎなかった。この中断を合計するとひとりあたり一日二時間以上になり、損失を金額に換算するとアメリカ全体で一年間に五千八百八十ドルになるという。」
これはおそらくウィンドウ式のGUIの弊害なのだろう。メールやWebが気になって、肝心の作業の気が散ることは私も毎日のように体験している。メールに書かれていたWebを見に行ってしまって、書こうと思っていた別のメールの返事を忘れてしまう、みたいなことがある。インスタントメッセンジャーや常駐アラートなど原因は増えてきているはずだ。
順番にひとつずつやる。気が散らない。割り込みを許さない。それでいて選択の自由度がある。そういうシングルタスクのデスクトップがあったら、頭が良くなるデスクトップとして、売れるんじゃないだろうか。
この本は女性ジャーナリストの著者が、消費者感覚で率直に、それぞれの効果を語っているので体験レポート集として価値がある。読者が自分で試す手間が省けるのがよい。
個人的にはサプリメントに興味があって、毎日「マルチビタミン」「ブルーベリー」を会社の机の引き出しに入れて飲んでいる。少々寝不足でも大丈夫な気がする。だが、市販のマルチビタミンは効果が弱すぎるとこの本では論じられており、Brain Sustain(57ドル)は気になる。
脳トレということでは子供と一緒にやるものに関心がある。最近買ってきたのはこれ。歴史年号の語呂合わせ(645(無事故)な世づくり大化の改新、とか1192(いい国)つくろう鎌倉幕府とか)が書かれた読み札と、年号と絵の描かれたカルタがセットになっている。語呂合わせを覚えていれば、早く取れる。
基本となる年号を暗記できていると、歴史ものの理解が早いから、生活の中でも結構楽しめる。
脳神経外科医が現代人の脳に起きている異変を語る。
「それが良いことなのか悪いことなのかはともかくとして、私たちはインターネットをあまりにも便利に使うことによって、日常生活の中で、知識を得るまでのプロセスに多様性や複雑さをなくし、思い出す手がかりのない記憶をどんどん増やしてしまっているようなところがないでしょうか。そのために「知っているけど思い出せない」ということが増えた。」という著者の指摘に考えさせられる。
パソコン任せ、インターネット任せの生活は、私たちをさまざまな面倒から解放した。検索すれば容易に情報が見つかる。気になるページはブックマークしておけばよい。わざわざ記憶しなくなった。人にURLを送りつければ自ら説明する手間が省ける。だから内容を深く理解しておく必要もない。脳の負担が減って楽になる=ITを使いこなしている=良いことと考えがちだ。
パソコンとインターネットを人類共通の外部記憶装置として共有する情報管理スタイルは、この10年で世界中いたるところで急速に浸透している。楽に膨大な量の情報を扱うことができるようになったわけだが、一方で人間が物を覚えたり考えたりする時間は減っている。現代人は中途半端にしか情報を受け取っていないから「知っている気がするけど思い出せない」ような体験が増えていると著者は指摘する。脳がパソコンにカスタマイズされてしまっているのだ。
フリーズが多発する脳はパソコンやネットだけが原因とは限らない。会社生活における環境の変化もそうしたボケを招くのだという。
「若い頃には嫌なことをやらされているわけですが、偉くなってくると「これはもう自分でしなくてもいい」と選べる場面が増えてきます。それで面倒な作業を省いていくと仕事や生活がどんどんシンプルになっていく。そうした方が効率よく才能を発揮できそうな気がしますが、そうとは限りません。「忙しかったのにできていた」のではなく、本当は「雑多なことをしていたからできていた」のかもしれないのです。」
雑多なことを自動化簡単化すると生活の中の「新しく組み立てていく部分」がなくなる。脳の回転数が下がってしまう。著者曰く脳の回転数を上げるには、ある程度「社会の歯車である環境」に戻りなさい、意志を持った歯車でいなさいとアドバイスしている。
私はITをフル活用して仕事をしている。またそうしたワークスタイルを授業や研修で積極的に人に勧めてきた。だから、この本のフリーズする脳の問題は日々自分の問題として痛感している。1日中パソコンの画面とにらめっこしていると創造性が減退していくのが自分でも実によくわかるのだ。
パソコンをフル活用して煩雑な作業を自動化すること。インターネットを外部記憶として使うこと。こうしたやり方は決して間違っているわけではないと思う。本来は脳が楽をする分だけ「新しく組み立てていく部分」を増やすべきなのだ。だが人間はつい楽な道を選んでしまう。
数年来フリーズ脳対策として個人的に心がけていることとして、
1 企画の発想はパソコンを使わず紙の上に書いていく
2 仕事中に社内を歩き回るか外を散歩して考えをまとめる
3 情報収集ではネットサーフィンは最小限にして本を読む
4 誰かをランチに誘ってややこしい問題を人に簡単に説明する
5 真面目な会議でもなるべく人を笑わせるよう努力する
がある。この本を読む限りではだいたい方向性は間違ってなかったようだ。
私は「ゲーム脳」はまったく信じないのだけれども、パソコンやネットの過度な利用で脳が怠惰になるという、この本の説には全面的に同意である。かつては人と差をつけるためにITを使ったが、万人が使いすぎな時代には、敢えて使わないことで生産性を高めることにつながるのかもしれない。
ちょっとユニークな読後感の脳科学の本だ。
まえがきに「幼稚園のころ私はIQ検査を受け、「天才」と認められた」という個人的な告白がある。著者は奨学金でハーバードとオックスフォードに進み英文学と医学で博士号を取った。現在はアイオワ大学精神病理学教授として脳の画像解析の最先端で多数の受賞があり、関連する学会の会長を歴任した医学者である。天賦の才能にあふれた人生に思えるが、著者は自分は結局「並外れた天才」にはなれなかったと述べている。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチやシェイクスピア、ニュートンやアインシュタインのような真の大天才になる条件を研究している成果がこの本である。
英文学の専門家でもあるから、科学の本には珍しく各所でルネサンス期や近代の文学の天才たちの作品が、著者の見解を支持するために、しばしば引用されている。文学や芸術の天才の能力にたくさん言及しているのが、理系の天才を評価することが多い他の天才研究本とこの本が異なる独特なところだ。
だから、定量的な生産性で計るのではなく、創造性という部分で、並外れた天才を計る。まずは天才の創造性の定義だが、チクセントミハイの創造性の定義を著者は強く支持している。興味深いのでまるごと引用すると、
「創造性は、ある人物がたとえば音楽、工学、ビジネス、数学など特定の領域のシステムを用いて、新しい思想をいだき、あるいは新しいパターンを発見して、その新しさが、その当該分野によって選び取られ、関連する領域に取り込まれるときに生ずる。」
というもの。「独創性」「有用性」「生産物」がキーワードになる。本人の能力的優秀さだけでなく、その能力を使った作品として成果物を完成させ、それが世の中に有益と認められる必要があると総合している。そして、著者は有名な天才研究の内容に言及しながら、並外れた天才たちによく見られる創造パターンをこう描き出す。
「創造するためには、創造者は非常な集中と熱中状態に入り込む。精神医学の用語ではこれは「分離した状態」といえよう。つまりその人は、精神的に自分自身が環境から離れており、比喩的に言えば、「他の場所に行っている」。通常の言葉では、「現実との接触を断っている」とも言えよう。しかし主観的にはその創造者は、現実よりも本当のものである別の現実に行っているのだ。」
モーツアルトは作曲のときオーケストラの完全な演奏がいきなり頭に思い浮かぶと自ら書き残している。真の天才は部分を集めて作るのではなくていっきに完成形を創造してしているのである。それはもうひとつのリアリティの中で聴いた音楽を、こちらの世界で譜面に書き起こすような作業なのだろう。
「創造性を育てる文化的な環境」として次の5要素を挙げている。
1 自由、新規、先端にいるという自覚
知的な自由が確立されている
2 創造的な人たちの臨界量
他社との相互作用と思想の交換ができること
3 自由で公正な競争的な雰囲気
競い合うことで成長する
4 指導者とパトロン
直接育てる人、支援する人の存在
5 経済的な繁栄
多くの偉大な創造者は経済的繁栄の時期に出ている。
そして「創造的な個人に特徴的性格としては、経験に対して開放的、大胆さ、反抗的、個人主義的、敏感さ、茶目っ気、忍耐強さ、好奇心の強さ、単純さが挙げられる。」ともまとめている。
創造性というものは、個人の中に存在するものではなくて、個人が文化や環境の中に入って相互作用をする過程で出現するものだという視点が興味深いと思った。著者の少女時代と同じように、IQの高い少年少女を半世紀以上追跡調査した研究も紹介されているが、結局、並外れた業績を残した天才はほとんど出てこなかった。個人の能力ではなく社会や時代の文脈が天才を生んでいるということを裏付けている。