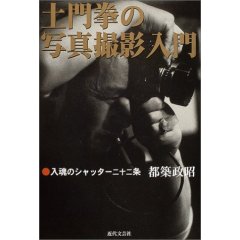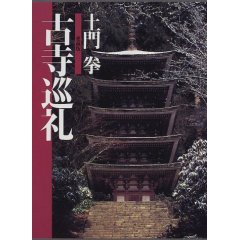2007年04月18日
土門拳の写真撮影入門―入魂のシャッター二十二条

スポンサード リンク
近代写真のパイオニア 土門拳はリアリズムを徹底的に追求する写真家だ。「絶対非演出の絶対スナップ」を信条に、戦前戦後の貧困にあえぐ市井の人々や、原爆の後遺症に苦しむ広島の人々にファインダーを向けた。写真集「筑豊のこどもたち」「ヒロシマ」がその代表作だ。
「少しでも演出的な作為的なものが加わるならば、その写真がどんなに構成的に、説明的にまとまりを示していようとも、長い時間の、くりかえしでの鑑賞に堪えないものとして、つまり底の浅い、飽きる写真になってしまうのである」
「モチーフを発見した時は、もうシャッターを切っておった、というのでなくては、スナップの醍醐味はない」
「ボケていようがブレていようが、いい写真はいい写真なのである。そんな末梢的な説明描写にスナップの境地はないのである。スナップはスリのようなものだ」
土門は禁欲的な求道者であり、自らの肉体をカメラと一体化させるための訓練に熱心であった。愛用する135ミリレンズの距離感をつかむため、すべてを7フィート(人物の全身が入る距離)で撮影して、百発百中になるフレーミング技術をまず身につけた。
そしてピント合わせは夜の窓からみえるライオン歯磨きの看板を使って修行する。
「ぼくはそのために、ライオン歯磨のラの字を目標にして、カメラ保持、ファインダーのぞき、シャッター切りという一連の操作を一組にしたトレーニングを横位置五百回、縦位置五百回、合計千回ずつを毎日晩御飯の食休みにやった。本当に撮影しているときの気分を出して、毎日千回シャッターを切った。それも二ヶ月ほどで完全にものにできた」
絶対スナップで世に出た土門拳だったが、脂の乗った時期に、二度の脳梗塞の発作で半身不随、車椅子生活を余儀なくされる。スナップ写真家にとって大切なフットワークを失った。しかし不屈の精神力と肉体修行で復活し、今度は大型カメラと弟子を引き連れた「大名行列」の撮影スタイルで、全国の寺社と仏像を撮影し、代表作のシリーズ「古寺巡礼」を撮り続けた。
古寺巡礼の写真は画面のすべてにピントを合わせるために、極限まで絞った写真である。絞るということはレンズから光が入る穴を小さくするということである。寺社はもともと暗いから、絞り込んだら普通はちゃんと写らない。
弟子が「暗くて撮影になりません」というと「写る、写ると思って写せば写るのだ」と怒鳴り返す土門。「念力で写すのだ」とまでいう。じゃあ、どう撮りますかと聞かれて、F64からF45というとんでもない高い絞り値でやれと命令する。(一般的に普通のカメラの撮影は1.4から16くらいのはず、しかも当時は高感度フィルムはない)。逆らうとゲンコと怒号が飛んでくる。弟子たちは寒い撮影現場で長時間、ガタガタ震えながら、写るかもわからぬ写真を気合いで撮った、撮らされた。
30分という長時間露光で仏像を撮影し、光不足を補うために何十回もあらゆる角度からフラッシュを焚いた。こうすることで、仏像の質感がはっきりと作品に浮かび上がった。非現実的な光線状態の中で、仏像に魂が宿っているようにさえ見える。土門が撮影技法をどこまで考えていたのかはわからないのだが、結果的には歴史的傑作となった。
リアリズムの土門と、軽妙洒脱の木村伊兵衛は、近代写真の双璧であるが、性格も作風も対極にあった。旦那衆の道楽的な粋を極める木村伊兵衛に対して、貧しい少年時代を送った土門は強烈なライバル意識を持っていたようだ。二人の名前を冠した二つの写真賞が戦後の日本のカメラマンを育てたが、今も両賞の受賞作品はその二つの作風を反映しているようにみえる。
「マチエール」(質感、存在感)を写すために徹底的に絞り込む、肉眼をカメラと一体化する訓練を行う、演出と作為を完全に排除する。それが土門の撮影技法であった。タイトルは撮影技法の本であるが、カメラの操作方法の記述はほとんどない。そのかわり写真芸術とは何かの本質に迫る本である。迫力のある精神論と人生論が読み応えのある名著である。
・木村伊兵衛の眼―スナップショットはこう撮れ!
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004923.html
スポンサード リンク
Posted by daiya at 2007年04月18日 23:59