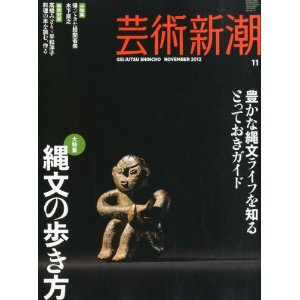芸術新潮 2012年 11月号
芸術新潮という雑誌は特集テーマによって年に2,3回買うのだが、今年はやはりこの25年ぶりという縄文特集号が最高だった。土器、土偶の美しい写真でいっぱいの「縄文の歩き方」。
解説の小林達雄教授の解説がむちゃくちゃ面白い。どこまで史料的根拠があるのかよくわからないところもあるが、なぜ土偶はこんなへんな形に進化していったのか、とか縄文人の日常生活はこうだったとか、きわめてわかりやすい説明をする。
たとえば縄文時代は男はダラダラ、女はテキパキと暮らしていたのだという。男たちは狩りに出ても今日はどうする?とか話しているうちに日が暮れて「今日はもうダメだね」でだいたい帰ってきてしまう。女たちはテキパキ働いて植物性食糧を集めて食事を作っていたはずだと教授は言う。
「それでも肉を食べたいという圧力が強くなってくると、ちゃんと男も狩りに出かけます。狩りは危険も伴いますから、狩猟を担当する男というのは普段それなりに遊ばせてもらえるわけです。狩りがいつも成功するとは限らないが、獲物を獲り尽くさないで持続可能な狩りを続けていけるという利点となる。要はサボっているんだけど(笑)、それが上手い具合に全体のバランスを調整します。 いずれにせよ、しゃかりきに働きすぎることなく、冬場の何もしない余暇の存在が、縄文人の文化力を底上げしたのだと思います。」
頑張りすぎずテキトーに生きていると、環境と調和してよい感じになるよいう説。また土偶がなぜあんなヘンな顔になったかについては、初期は目には見えないナニモノカの気配を表現していただけのものだったが、顔をつけてしまったために人型に進化していったが、飽くまでもこれは人ではないので、人とは違うヘンな顔で進化していったという説。どちらも本当なのか?と思うが説得力のある文章。
MIHO MUSEUMの館長が「これこそ生の芸術。生命の力をひしひしと感じます。今の若い人が土偶に興味を持つのは、自分の中に絶滅危惧みたいなものあって、こういう血の騒ぐような力づよさを輸血しなきゃ、人間として危ないという飢餓感を覚えているからではないでしょうか」といっているが、ハイテクやデジタルなガジェットとは対極の存在感があっていい。

トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 芸術新潮 2012年 11月号
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ringolab.com/mt/mt-tb.cgi/3816