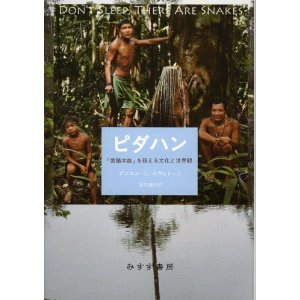ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観
キリスト教伝道師兼言語学者としてアマゾン奥地の少数民族ピダハン族の研究に30年を捧げた研究者が書いた衝撃のノンフィクション。著者はピダハン族と暮らすうちに、彼らの文化に魅了され、西洋文明の価値観を疑いはじめる。そして遂には無神論者となって信仰を捨て去ってしまうに至る。私たちとはまったく異なる世界認知のスタイルがあるということを教えられる。
ピダハン族の言語には数を表す言葉がない。色の名前もない。神の概念もない。我々がよく知る現代の西洋とも東洋とも違う認知世界の住人たちだ。ピダハンの生活は直接経験の原則で貫かれている。経験していないことは考えない。遠い昔のことや未来の話は語らない。空想の話もない。だから彼らの文化に口承伝承や神話、そして儀式がない。ピダハンも夜に夢を見るが、それも寝ている間の幻としてではなく現実の経験として扱う。
ピダハンの血縁関係は単純で狭い範囲に限られる。それは平均寿命45年で実際に出会える関係に限られるのだ。祖父母の話はでてこない。右と左の概念もない。代々同じ場所に住んできた彼らにとって、重要なのは川がどちらにあるかのみ。だから川がある方向に対して自分の絶対的な位置だけを考える。自分がいまどちらを向いているかによって変わってしまうあいまいな右、左という方向感覚を使わないで生きているのだ。色も常に具体的に何かの色という言い方でしか呼ばないから、"赤"や"青"にあたる一般的な色の名称がない。抽象化と無縁の文化である。
ピダハンは人生の節目ごとに名前を変えることで別人になる。子供を小さな大人として扱う。幼児に刃物で遊ばせたままにしておく。保護しないともいえる。死んでしまったらそれも運命と受け入れる。神を持たない彼らだが、日常生活において精霊を見る。精霊はどうやら本当に見えている何かであるらしい。
こうしたピダハンの文化は言語構造に大きな影響を与えているという研究成果が本書の後半部である。ピダハンは十一しか音素がない特異な言語を持つ。音素が少ないので単語や文は長くなる。話の文脈依存度が高い。話し方の構成が一般的な言語とは大きく違う。彼らが何か起きたことを語ろうとするとき、は、時間の順序を重視せず、五月雨式に、いくつもの視点が入り乱れるような話し方をする。記録をみただけで我々の言語体系と明らかに違うことがわかる。これは先に挙げた彼らの文化や世界認知のあり方と密な対応がある。
文化が言語に根本的な制約をもたらすという著者の研究は、人類には普遍的に言語を生成する生得的能力があるとするチョムスキーの言語理論に異を唱えるものだ。具体的な例外を示すことによって、言語というものはチョムスキーが想定していたほど互いに似ていなくて、違いが大きいものだという事実を突きつけてみせた。
「ピダハンはわたしに、天国への期待や地獄への恐れももたずに生と死と向き合い、微笑みながら大いなる淵源へと旅立つことの尊厳と、深い充足とを示してくれた。そうしたことをわたしはピダハンから教わり、生きているかぎり、彼らへの感謝の念をもちつづけるだろう。」。
驚くべきは著者が信仰を捨てるほど魅了されたように、ピダハンが物質的には貧しいながらも、彼らなりの調和をもって現代人以上に幸福に暮らしているということ。グローバリズムを超えた真の多様性を理解するために、この本は有益だ。

トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ringolab.com/mt/mt-tb.cgi/3629