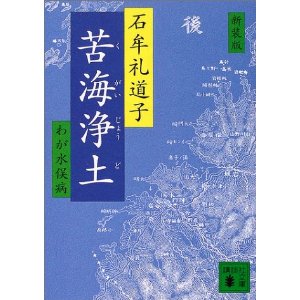苦海浄土
1950年代、水俣市の大企業チッソ(かつて旭化成、積水化学、積水ハウス、信越化学工業の母体であった会社)の工場が垂れ流した水銀により、汚染された魚介を食べた付近の住民は、地獄の苦しみを味わいながら死んでいった。患者たちの生々しい声を軸に、水俣病の悲惨と公害事件の不条理を世に訴えた石牟礼道子の代表作。初版は1968年。
おとなのいのち十万円
こどものいのち三万円
死者のいのちは三十万
水俣病の患者に対して、昭和34年時点でチッソが支払った見舞金の契約内容はたったこれだけであった。患者たちは身体が不自由になり、視覚や聴覚を失い、精神錯乱まで引き起こして、死んでいく。一方的な被害者であるにも関わらず、差別を受ける。賠償を求めた裁判も、工場排水と病気の因果関係の解明や、患者の認定が進まず、なかなか立ち行かない。その間にも死者が増えていく。
重症患者の多くが工場排水口近くの貧しい漁民であった。水俣市の住民の多くはチッソ関係の労働者であり、チッソの功労者は水俣市の功労者でもあった。地元の経済基盤を支える企業に対して、約300世帯に過ぎない漁業水産関係者の立場は限りなく弱かった。
この作品は患者たちの嘆き、怒り、恨み、諦めの声を収録したドキュメンタリ形式である。患者の臨場感あふれる魂のこもった語りが多いので、聞き取りの再現をしているのかと思っていたが、実は著者は、ほとんど聞きとりをしていなかったと解説で明かされていて驚いた。つまり創作なのだ。著者自身が近隣の住民であり、患者たちの気持ちや生活感覚を正確にくみ取ることができ、彼らの心の叫びを自分の内面で自在に再現できたということであるらしい。一種のシャーマンの語りなのである。
内容的には水俣の悲惨を描いているのに、詩的な情感がある。鎮魂歌に美しさがあるのと同じように、鎮魂文学にも美しさがある。その美しさに静かに浸っていると自然と悲しくなってくる。レクイエムとして傑作である。
ただ、どうしても今の状況で読むと、水銀が放射能に、チッソが東京電力にだぶってくる。水俣病の補償と救済は、半世紀が経過した現在でもまだ完全には終わっていない。原発の放射線被害はまだその全貌がわからないが、新たな苦海浄土を生み出しつつある。今度は鎮魂に半世紀かかるだけで終わらず、放射能を鎮めるのに何万年もかかる。企業や政府や住民は、高度成長期の公害問題での経験をどれだけ活かせるだろうか。

トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 苦海浄土
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ringolab.com/mt/mt-tb.cgi/3197