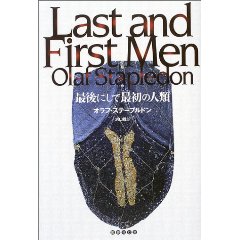最後にして最初の人類
年始にふさわしい壮大な話を読もうと思って今年はこれにした。
オラフ・ステープルドンの人類20億年未来史。素晴らしい。うっとりした。
20億年後の最後の人類(第18期人類)が、遠い昔の最初の人類である我々に語りかける形式で書かれている。現代の人類はこれから1千万年くらい生きた後に絶滅して、さらに進化した第2期人類の時代に入る。
火星人との接触の記述には思わずうなった。これほど現実的にファーストコンタクトを想像した作家が20世紀初期にいたなんて驚きだ。あまりに異なる生命(空を漂うアメーバのような生物)の様式を持った火星人と地球人は、お互いの高度な知性を認識することができない。その数億年先では第5期人類が別の星の知性と出会うが、このときにも相互理解に失敗する。
最後の人類は振り返ってこう語っている。「しかしこの議論はクラゲや微生物にもあてはまるだろう。入手できる証拠をもとに判断が下されねばならなかった。どのみち人間がその問題に判断を下しうる限り、人間がより高次の存在であるのは間違いなかったのである。」。結局、判断基準を設定するものが高次なのだ。
人類と火星人は相互理解には失敗するものの、第一期人類の細胞に入り込んだミトコンドリア(太古には別の生命体だったといわれる)との関係に似た共生関係に入り、共進化を進めていく。しかしそれもたかたか数千万年の間の人類史の初期の出来事。すべてが終わったところから眺めると、第一期と第二期人類などはさして重要な存在ではなかった。
やがて人類は地球を捨てて宇宙へと飛翔する。自らの種を改造して新しい形態に進化していく。私利私欲を制御して高い精神性を持った人類の時代が訪れる。それでも惑星レベルの危機は数億年単位でやってきて、人類の歴史は思わぬ方向へと展開していく。
すべてが地質学的年代のスケールで描かれるため、この長大な物語に名前を持った登場人物は一人もいない。固有名詞もほぼ出てこない(最初の数章には国名がいくつか出てくるが)。世紀の大事件も20億年の大河においては一滴の水に過ぎない。人類史を大きく変えた大発明も、結局は遠からず誰かがそのうち見つけるのだから、誰が見つけたというのはあまり意味がない話になる。
グーグルアースで自分の自宅近辺の地図から、市や県、国、地域、そして地球、宇宙と表示を拡大していくと、自分の見えている空間はなんてちっぽけなんだろうと思ったりするが、この本は、その遠近スケール体験を極限的に味わうツールである。
ステープルドンが代表作となるこの作品を書いたのは1930年のこと。「エーテル」のように科学的な誤りだとか、実際にはそうはならなかった20世紀の歴史予測が含まれるが、話のスケールがあまりに大きいため、そんな多少の間違いは歴史の流れにまったく関係がない。重要なのは人類の普遍的な性質と宇宙レベルの年代スケールである。想像力の限界に挑んだ歴史的な奇書。
・スターメイカー
http://www.ringolab.com/note/daiya/2006/10/post-470.html
『最後にして最初の人類』の次は宇宙の最後を五千億年のスケールで描くステープルドンの究極「スターメイカー」をおすすめ。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 最後にして最初の人類
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ringolab.com/mt/mt-tb.cgi/2734