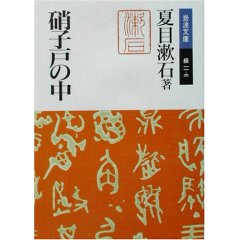硝子戸の中
夏目漱石が1915年1月13日から2月23日まで新聞連載したエッセイ36本。
「硝子戸の中から外を見渡すと、霜徐をした芭蕉だの、赤い実の梅もどきの枝だの、無遠慮に直立した電信柱だのがすぐ眼に着くが、その他にこれといって数え立てるほどのものは殆ど視線に入って来ない。書斎にいる私の眼界は極めて単調でそうしてまた極めて狭いのである。」
この時期、漱石は持病の胃腸病に悩まされて、自宅療養生活を送っている。「自分以外にあまり関係のない詰らぬ」事を書くと断って、日々の生活や追憶を短く綴っている。当時すでに文豪としての地位を確立していた漱石だが、このエッセイ集では意外にナイーブな内面を見せている。
自分が親から疎まれていたのは性格が悪かったからだろう、とつぶやいたり、偏執的な読者から繰り返し送られてくる手紙にほとほと参ってしまったり、あなたの講演は難しかった、わからなかったと言われて、随分落ち込んだりしている。
「今の私は馬鹿で人に騙されるか、あるいは疑り深くて人を容れる事が出来ないか、この両方だけしかない気がする。不安で、不透明で、不愉快に充ちている。もしそれが生涯続くとするならば、人間とはどんなに不幸なものだろう。」
他人の眼をとても気にする人だったのだなと驚く。そんな世間と自分を連載の題名「硝子戸」で隔てた上で、新聞の依頼で書くけどこれは「つまらぬこと」ですよ、という断りまで入れる。何重にも対読者バリアを用意しているわけである。こうしたナイーブな感性が数多くの傑作を書けた理由なのかもしれない。
「ある人が私の家の猫を見て、「これは何代目の猫ですか」と訊いた時、私は何気なく「二代目です」と答えたが、あとで考えると、二代目はもう通り越して、その実三代目になっていた。」という、有名作品を連想させる記述もある。有名作家だからいろいろな人から相談を受けている日常も書かれている。女性の身の上相談に理屈で答えている。カウンセラーとしてはあまりうまくない先生だったみたいだが、物語のネタをそうやって吸収していたのだろう。自分語りが少ないと言われる文豪漱石の、日常と内面がのぞけるのが、このエッセイ集の面白さでもある。
漱石の文体は、エッセイでも、ちゃんと四角いなと感じた。漢字や仮名遣い、接続詞、句読点の打ち方が、なんというか、お手本的である。無駄がない。特に事の顛末を、時系列に、短文を並べて、説明するのがうまいなと思う。
「この小包と前後して、名古屋から茶の缶が届いた。しかし誰が何のために送ったものかその意味は全く解らなかった。私は遠慮なくその茶を飲んでしまった。するとほどなく板越の男から、富士登山の絵を返してくれといってきた。彼からそんなものを貰った覚のない私は、打ち遣って置いた。しかし彼は富士登山の画を返せ返せと三度も四度も催促してやまない。私はついにこの男の精神状態を疑い出した。「大方気違だろう。」私は心の中でこう極めたなり向こうの催促には一切取り合わない事にした。」
という風に数週間を短く圧縮してみる一方で、時間的には一瞬の心理描写を同じくらいの行数で綴ったりする。文章の意味の圧縮率を自在に変えられるから、全体として構成の整った文章になっているように思えた。こういうのを実際に書こうとすると、下手な私は思い入れのある部分が冗長に引き延ばされてしまう。文章のうまさというのは、こういうところでも差が出るのかもしれないなと、文豪の手すさみを読んで思うのであった。