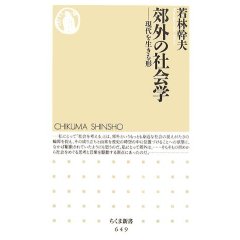郊外の社会学
都市でも田舎でもなくて郊外こそ、テーマにすべきなのではないかと郊外居住者として思ってきた。珠玉混交のネットの集合知を信頼できるものに変える仕掛けとして、地域コミュニティの信頼ネットワークというソーシャルキャピタルがこれから重要になってくると考えている。
それにはおそらく二つの世代が深く関係してくる。ひとつは私の属する30代の世代。郊外に居住して子供もできて、生活環境としても教育環境としても地域コミュニティを無視できなくなったインターネット第一世代。そして、会社を退職して地域の人になる60代の団塊の世代である。
この二つの世代の多くが都心でもなく田舎でもなく、郊外に多くが居住しているはずなのである。その割に郊外の生活の質や内容が政治や社会の論点として取り上げられることが少ないなあと思う。
私が子供時代から住む神奈川県藤沢市には秋に大規模な「市民まつり」がある。「世界最大の金魚すくい」なるイベントが10年くらい前に発案されて人気を呼び、ギネスブックに登録されて話題になっている。一方で伝統的な地元の寺社の祭りもある。これは新興住宅地としての新住民や商工会主体の人工的なコミュニティと、伝統的地元コミュニティによるふたつの祭りである。
郊外のふたつの祭りを通した著者の関わり方に自分の姿がそのまま重なる。
「こうした「新しい祭り」に対する違和感は、旧来の地域の伝統のなかにこそ、「祭り」という名に値するものがあるという感覚に由来する。私もまた石原と同じく、団地やマンション、町内会が主催する「祭り」の神も闇も存在しない白々しさには「嘘っぽさ」を感じる方だ。だがしかし、神と闇のある祭りを「本物」だと感じるからといって、私は地元の神社の氏子ではないので神輿を担いだりして参加することはなく、夜店の間をそぞろ歩き、信心もなしに賽銭箱に小銭を投げ込んだりして、祭り気分を味わうにとどまっている。」
新しい祭りの白々しさ、つくりもの臭さは、不動産デベロッパーの開発した新興地区の「○○台」「○○夕が丘」式ネーミングや「ショートケーキハウス」のような家のデザインにも通じる。郊外のつくりものっぽさは近年の大型ショッピングモールの進出によって加速しているように思える。だが、それが新しい地域文化を作り上げていることも認めざるを得ない。
「こうして郊外という場所と社会が私たちの生きる日常の分厚い膨らみとなるにつれ、「郊外の神話」は地域という構造のなかで年々繰り返される”制度化された祝祭”になっていったのだ」
つくりものっぽさの背景にあるのは、人間関係の希薄さである。良くも悪くもつながらざるを得なかった伝統的コミュニティの人間関係と違って、新しい祭りは希望者の自由参加を主体とする。ショートケーキハウスのクリスマス・イルミネーション現象も個々の家が自分の家だけをデコレーションする。この本ではそうした個々の表現の集まりを「集列体」と呼んでいる。
郊外は都市に従属している。郊外の住民の多くは日中は都市部へ通勤している。地域共同体といっても決して地域を共有しているわけではなく、都市への移動を共有する「共移体」というのが現在の郊外コミュニティの本質なのだと著者は結論している。
集列体、共移体は、地域の濃い人間関係を持たないから、地域を超えたメディアや大衆消費文化の影響を受けて文化が形成されていく。つくりものっぽさ、白々しさはマスメディアとの距離感に由来するものなわけだ。
つくりものは時間の経過で本物になるのか、いつまでたっても偽物のままなのか。全国各地に、地域性が消去された、金太郎飴のような同質の郊外文化が量産されていくのか。ニュータウンという「立場なき場所」の立場がどう定まるかというのは、郊外住民の生活の質に大きな影響を与える日本の、結構大きな論点であると思う。
郊外に住む著者の本音と社会学のキーワードとの紐づけが勉強になる本だ。